「中学受験、そろそろ志望校を考えないといけないけど、学校が多すぎて何から手をつければ…」 「偏差値だけで選んでしまって、本当にこの子に合う学校なのだろうか?」
小学4〜5年生のお子さんを持つ保護者の方なら、誰もが一度は抱える悩みではないでしょうか。大切な我が子が6年間を過ごす場所だからこそ、絶対に後悔したくない。そのお気持ち、とてもよく分かります。
この記事は、そんな悩める保護者の皆さまのために作られた「後悔しない志望校選びのための完全ロードマップ」です。
中学受験における志望校選びは、偏差値という一つのものさしだけでは測れません。お子さんの性格や興味、ご家庭の教育方針、そして学校ごとの個性豊かな校風。これらを丁寧に見つめ直し、最適なマッチングを見つける作業です。
この記事を最後まで読めば、志望校選びの具体的な手順から、学校を比較する際の重要ポイント、お子さんのタイプに合った校風の見つけ方まで、すべてが分かります。漠然とした不安を解消し、自信を持って志望校選びを進めるための一歩を、ここから踏み出しましょう。
【中学受験】志望校選びはいつから?学年別タスク

「志望校選びって、具体的にいつから始めればいいの?」という疑問は、多くのご家庭が抱く最初の壁です。結論から言うと、本格的に動き出すのは小学5年生からが一般的ですが、小学4年生から意識し始めるのが理想です。
学年ごとにやるべきことを整理して、計画的に進めていきましょう。
小学4年生:興味の方向性を探る時期
この時期は、まだ焦る必要はありません。親子で「どんな中学校生活を送りたいか」を話し合い、興味の方向性を探る大切な準備期間です。
- ・いろいろな学校があることを知る: 男子校、女子校、共学、大学附属、進学校、宗教のある学校など、世の中には様々なタイプの私立・国公立中学校があることを親子で話してみましょう。
- ・子どもの「好き」や「得意」を観察する: どんなことに夢中になるか、どんな環境だと楽しそうかなど、お子さんの個性や特性を改めて見つめ直す良い機会です。
- ・漠然としたイメージを共有する: 「制服が可愛い学校がいいな」「広いグラウンドでサッカーがしたい」「実験がたくさんできる学校は楽しそう」といった、お子さんの素直な希望を聞き出してみましょう。
まだ早いと思われがちですが、4年生から少しずつ準備を始めることで、その後の学習がスムーズになります。詳しくは以下の記事で解説しています。
小学5年生:候補校を絞り込む時期
小学5年生は、志望校選びを本格化させ、候補となる学校を具体的に絞り込んでいく時期です。塾での学習も本格化し、お子さんの学力や得意・不得意も見えてきます。
- ・情報収集を本格的にスタート: 塾から提供される資料や学校の公式サイト、オンラインの学校選びサイトなどを活用し、気になる学校の情報を集め始めます。
- ・学校説明会やオープンスクールに参加する: まずはオンライン説明会でも構いません。気になる学校の雰囲気を実際に感じてみましょう。この段階では、偏差値にとらわれず幅広く見て回るのがポイントです。
- ・候補校をリストアップする: 収集した情報をもとに、興味を持った学校を10〜20校ほどリストアップしてみましょう。
小学6年生:志望校を最終決定する時期
いよいよ受験学年。小学6年生の夏休み前までには、併願校を含めた受験プランを固めるのが目標です。
- ・候補校の優先順位をつける: 学校訪問や過去問との相性などを踏まえ、第1志望から併願校までの優先順位を明確にします。
- ・過去問との相性を確認する: 学校によって出題傾向は大きく異なります。お子さんが「解きやすい」と感じるかどうかも、重要な判断材料になります。
- ・受験スケジュールを確定する: 入試日や手続きの締め切りなどを確認し、無理のない受験スケジュールを組み立てます。一般的に、チャレンジ校、実力相応校、安全校をバランス良く組み合わせます。
【中学受験】志望校の決め方4ステップロードマップ

情報収集から学校決定まで、具体的に何をすれば良いのか。ここでは、誰でも実践できる志望校の決め方を4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:家庭の教育方針と子どもの希望を整理
志望校選びの最も重要な土台は、偏差値や大学進学実績の前に「ご家庭の教育方針」と「お子さんの希望」を明確にすることです。
「どんな大人になってほしいか」「どんな6年間を過ごしてほしいか」を親子でじっくり話し合い、譲れない軸を決めましょう。以下の点を紙に書き出してみるのがおすすめです。
- ・学習面: 大学進学を重視するのか、探究心や個性を伸ばしてほしいのか。
- ・生活面: 規律ある環境が良いか、自由な校風でのびのび過ごしてほしいか。
- ・将来について: お子さんが将来やりたいこと、興味のあることは何か。
- ・通学時間や学費: 家庭として許容できる範囲はどこまでか。
この軸がブレなければ、膨大な情報に惑わされることなく、学校選びを進めることができます。
ステップ2:学校情報を広く収集・リストアップ
家庭の方針が固まったら、次はその方針に合いそうな学校の情報を広く集めます。最初は条件を絞りすぎず、少しでも気になった学校はリストアップしていきましょう。
- ・塾からの情報: 進学実績や各学校の最新情報に精通しているため、最も信頼できる情報源の一つです。
- ・学校の公式サイト・パンフレット: 教育理念やカリキュラム、学校生活の様子が詳しく紹介されています。
- ・オンラインの学校比較サイト: 複数の学校の基本情報を一覧で比較でき、効率的な情報収集に役立ちます。(例:みんちゅう、JS日本の学校など)
- ・在校生や卒業生の保護者の口コミ: リアルな声は参考になりますが、あくまで個人の感想として捉えましょう。
ステップ3:比較検討し、候補校を3〜5校に絞る
リストアップした学校を、ステップ1で決めた「家庭の軸」と、後述する「学校選びで比較すべき10の重要ポイント」に沿って比較検討します。
エクセルなどで一覧表を作成し、各項目を点数化したり、〇△×で評価したりすると、客観的に比較しやすくなります。この作業を通して、候補校を現実的な3〜5校程度に絞り込みましょう。
ステップ4:学校訪問で雰囲気を確認し最終決定
書類上のデータだけでは分からないのが、学校の「空気感」です。最終決定の前には、必ず親子で学校を訪問しましょう。
学校説明会やオープンスクールはもちろんですが、文化祭や体育祭といった行事は、生徒たちの素顔が見える絶好の機会です。先生方の表情や生徒同士の会話、校内の掲示物、施設の清潔さなど、五感を使って学校の雰囲気を感じ取ってください。
「この学校、なんだかいいね」「ここに毎日通いたいな」とお子さんが心から思えるかどうかが、最後の決め手になります。
【中学受験】学校選びで比較すべき10の重要ポイント

候補校を比較検討する際に、どのような観点で見ればよいのでしょうか。ここでは、後悔しない学校選びのために必ずチェックしたい10のポイントを解説します。
偏差値・大学進学実績
偏差値とは、自分の学力が全体の中でどの位置にあるかを示す指標です。志望校を選ぶ上での重要な目安ですが、あくまで現時点での学力に基づくものです。お子さんの今後の伸びしろも考慮し、少し上のレベルの学校も視野に入れましょう。
大学進学実績は、学校の教育レベルや進路指導の手厚さを測る指標になります。国公立大学や難関私立大学への合格者数だけでなく、GMARCHや日東駒専など、中堅大学への進学実績も確認すると、学校全体の学力層が見えてきます。
志望校を検討する上では、偏差値や大学進学実績と並んで、学費の把握も重要です。6年間のトータル費用については下記の記事をご参照ください。
教育方針・理念
「建学の精神」や「教育理念」は、その学校の教育の根幹をなすものです。公式サイトやパンフレットを読み込み、「グローバル人材の育成」「自主自律の精神」「探究心の醸成」など、ご家庭の方針と合致するかをしっかり確認しましょう。この理念が、日々の授業や学校行事、生徒指導のすべてに反映されます。
校風・生徒の雰囲気
校風は、お子さんが6年間を快適に過ごせるかを左右する非常に重要な要素です。
- ・自由でのびのび
- ・規律を重んじ、面倒見が良い
- ・穏やかで落ち着いている
- ・活発でエネルギッシュ
など、学校によって様々です。説明会での先生や生徒の様子、服装、言葉遣いなどから、その学校ならではの雰囲気を感じ取りましょう。
校風は塾選びとも密接に関わります。お子さんの性格に合った塾を選ぶことも、志望校選びを成功させるカギです。
通学時間・アクセス
毎日のことなので、通学時間は軽視できません。ドアツードアで60分以内、長くても90分以内が現実的なラインです。体力的な負担はもちろん、通学時間が長すぎると、睡眠時間や勉強時間、部活動に参加する時間が削られてしまいます。朝のラッシュ時の混雑具合や乗り換えの回数も、実際に一度乗車して確認することをおすすめします。
学費・諸費用
私立中学の学費は、学校によって大きく異なります。授業料や入学金だけでなく、施設維持費、修学旅行の積立金、寄付金(任意の場合が多い)、制服代、教材費など、6年間でかかるトータルコストを把握しておくことが大切です。多くの学校が公式サイトで初年度納入金の目安を公開しています。
カリキュラム・授業内容
中学校の学習指導要領にとらわれない、特色あるカリキュラムも私立中学の魅力です。
- ・英語教育: ネイティブ教員の比率、オンライン英会話、海外研修の有無など。
- ・ICT教育: 生徒1人1台のタブレット端末の導入状況や活用方法。
- ・探究学習・STEAM教育: 課題解決型学習や理数系教育にどれだけ力を入れているか。
お子さんの興味や得意分野を伸ばせるカリキュラムがあるか、チェックしましょう。
部活動・学校行事
部活動や学校行事は、勉強だけでは得られない貴重な経験や仲間との絆を育む場です。お子さんが打ち込める部活動があるか、活動の頻度や実績はどうかを確認しましょう。文化祭や体育祭、合唱コンクール、修学旅行先なども、学校生活の楽しさを測る上で重要なポイントです。
施設・設備の充実度
学習環境や学校生活の質は、施設・設備の充実度に大きく影響されます。
- ・図書館: 蔵書数や自習スペースの広さ。
- ・グラウンド、体育館、プール: 運動部の活動に十分な広さや設備があるか。
- ・特別教室: 理科の実験室や音楽室、PCルームなどの設備。
- ・食堂(カフェテリア): メニューの豊富さや価格。
実際に学校を訪れた際に、隅々までチェックしてみてください。
学習・進路サポート体制
「面倒見の良さ」を判断する上で重要なのが、学習・進路サポート体制です。
- ・補習・講習: 授業についていけない生徒へのフォローや、長期休暇中の講習はあるか。
- ・進路指導: 低学年からのキャリア教育や、大学受験に向けた個別指導、卒業生による講演会など。
- :チューター制度: 質問に対応してくれる大学生チューターや教員が常駐しているか。
手厚いサポートを期待するご家庭は、特に重視したいポイントです。
ぎりぎりの学力で合格しても、入学後の学習についていけず苦労するケースもあります。志望校選びでは、合格可能性だけでなく『入学後に無理なく通えるか』という視点も大切です。詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
宗教の有無
ミッションスクール(キリスト教系)や仏教系の学校など、宗教教育を取り入れている学校も多くあります。礼拝や宗教に関する授業が日々の学校生活にどの程度関わってくるのか、ご家庭の考え方と合うかを確認しておく必要があります。宗教行事への参加が必須の場合もあるため、事前に調べておきましょう。
【中学受験】子どもの性格に合う校風の見つけ方

「うちの子には、どんな校風の学校が合うんだろう?」これは、多くの保護者の方が悩む点です。ここでは、お子さんの性格タイプ別に、合いやすい校風の傾向をご紹介します。
自由でのびのびした校風の学校
校則が比較的緩やかで、制服がない学校も多く、生徒の自主性を尊重する校風です。行事なども生徒主体で運営される傾向があります。
- ・向いている子のタイプ: 好奇心旺盛で、自分で考えて行動するのが好きな子。自己管理能力が高い子。
- ・見極めポイント: 説明会で「自主自律」という言葉がよく使われる。文化祭が非常に盛り上がり、生徒が企画・運営の中心になっている。
面倒見が良く手厚いサポートの学校
学習面での補習や個別指導が充実しており、日々の宿題や小テストが多い傾向にあります。先生方が生徒一人ひとりに目を配り、きめ細かく指導してくれます。
- ・向いている子のタイプ: コツコツ真面目に取り組む子。先生に質問したり、手厚く見てもらったりする方が安心できる子。
- ・見極めポイント: 「面倒見の良さ」を学校の強みとしてアピールしている。補習や講習制度、チューター制度が充実している。
穏やかで落ち着いた雰囲気の学校
都心から少し離れた緑豊かな環境にあったり、1学年の生徒数が少なかったりする学校に多い傾向です。生徒たちも穏やかで、落ち着いた学校生活を送りたい子に合っています。
- ・向いている子のタイプ: マイペースで、自分の時間を大切にしたい子。大人数や騒がしい環境が少し苦手な子。
- ・見極めポイント: 学校訪問をした際に、キャンパス全体に静かで落ち着いた空気が流れている。生徒数が比較的少ない。
個性を尊重し探究心を伸ばす学校
ユニークな探究学習プログラムや、プレゼンテーションの機会が多いなど、生徒一人ひとりの「好き」や「なぜ?」を深掘りする教育に力を入れています。
- ・向いている子のタイプ: 探究心が強く、好きなことをとことん追求したい子。自分の意見を発表したり、議論したりするのが好きな子。
- ・見極めポイント: 「探究」「リベラルアーツ」「STEAM教育」といったキーワードを掲げている。生徒の成果発表会などを見学できる機会がある。
学校ごとの特色や教育方針を比較しても、なかなか決めきれないこともあるでしょう。
学研の家庭教師なら、学力面のサポートに加えて“志望校選びの相談”にも対応。最新の受験情報を踏まえ、親子で納得できる学校選びを伴走します。
【中学受験】男子校・女子校・共学のメリットとデメリット
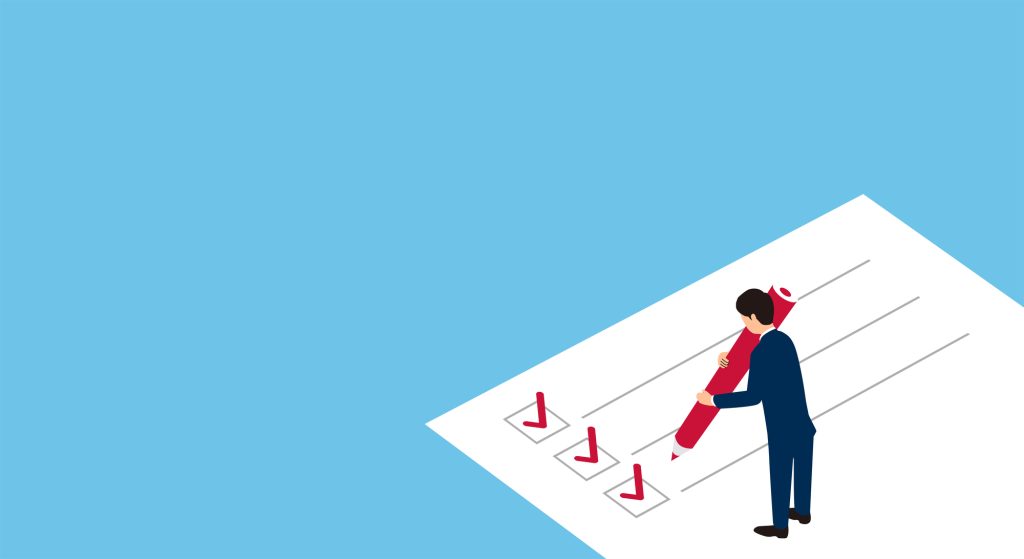
学校の種別も、校風や6年間の過ごし方に大きく影響します。それぞれの特徴を理解し、お子さんの性格に合う環境を選びましょう。
男子校の特徴と向いている子
異性の目を気にすることなく、何事にも全力で打ち込める環境が魅力です。
- ・メリット
- →リーダーシップを発揮する機会が多い。
- →趣味や部活動に没頭しやすい。
- →男の子の成長段階に合わせた指導が行われる。
- ・デメリット
- →6年間、同性だけの環境で過ごすことになる。
- →良くも悪くも、のびのびしすぎて羽目を外しがちになることも。
- ・向いている子: やんちゃでエネルギッシュな子。何かに熱中したい子。
女子校の特徴と向いている子
女性リーダーの育成に力を入れている学校が多く、理系分野への進学サポートが手厚い学校も増えています。
- ・メリット
- →性別による役割分担がなく、何事にも主体的に挑戦できる。
- →女性のロールモデルとなる先生や先輩に出会いやすい。
- →礼儀作法や言葉遣いなど、女性としての品性を育む教育が受けられる。
- ・デメリット
- →人間関係が密になりやすく、グループ化しやすい傾向も。
- →異性との自然なコミュニケーションの機会が少ない。
- ・向いている子: 落ち着いた環境でじっくり学びたい子。リーダーシップを発揮したい子。
共学校の特徴と向いている子
男女が共に学ぶ環境は、社会の縮図とも言えます。多様な価値観に触れながら成長できるのが最大の魅力です。
- ・メリット
- →多様な考え方や価値観に触れることができる。
- →異性との自然なコミュニケーション能力が身につく。
- →男女共同で協力し合う経験ができる。
- ・デメリット
- →思春期に異性の目を意識しすぎて、自分らしさを出しにくい場合がある。
- →リーダー役などが性別で固定化されやすい傾向が見られることも。
- ・向いている子: 協調性があり、様々なタイプの人と関わるのが好きな子。
【中学受験】志望校選びでよくある質問と解決策

志望校選びを進める中で出てくる具体的な悩みについて、Q&A形式でお答えします。
志望校がどうしても決まらない場合は?
まずは立ち止まり、最初に決めた「家庭の軸」に立ち返ってみましょう。情報が多すぎて混乱しているのかもしれません。優先順位をもう一度整理し、「これだけは譲れない」という条件を2〜3個に絞ってみてください。
また、塾の先生など、多くの生徒と学校を見てきた第三者に相談するのも非常に有効です。客観的な視点から、ご家庭に合う学校を提案してくれるでしょう。
子どもの偏差値と志望校のレベルが合わない場合は?
中学受験では、「チャレンジ校(合格可能性20〜40%)」「実力相応校(同50〜70%)」「安全校(同80%以上)」の3つのレベルの学校を組み合わせて受験するのが一般的です。
今の偏差値が届いていなくても、お子さんが「この学校に行きたい!」と強く願うなら、それをチャレンジ校として目標に据えるのは素晴らしいことです。その強い気持ちが、今後の成績を大きく伸ばす原動力になります。偏差値はあくまで現時点の目安と捉え、前向きに挑戦しましょう。
親と子どもの意見が対立したら?
まずは、お子さんの意見を頭ごなしに否定せず、なぜその学校が良い(または嫌だ)と思うのか、理由をじっくり聞く姿勢が大切です。お子さんなりに感じたこと、考えたことを尊重してあげましょう。
その上で、保護者としてなぜその学校を勧めたいのか(または反対なのか)を、感情的にならずに伝えます。お互いの考えを言語化することで、妥協点や新たな選択肢が見つかることもあります。
公立中高一貫校との併願は?
公立中高一貫校は学費の安さが魅力ですが、私立中学の入試が「教科試験」であるのに対し、公立は「適性検査」という思考力や表現力を問う独自の問題が出題されます。そのため、併願する場合は、適性検査に特化した対策が別途必要になることを理解しておく必要があります。
両方の対策をするのはお子さんにとって大きな負担になる可能性もあるため、塾の先生とよく相談して決めましょう。
説明会や文化祭で見るべきポイントは?
学校訪問は、貴重な情報収集の機会です。以下の点を意識して見てみましょう。
- ・先生と生徒の関係: 先生は生徒にどんな表情で話しかけているか。生徒は先生に気軽に質問しているか。
- ・生徒の様子: 挨拶は元気か。服装は乱れていないか。休み時間にどんな表情で過ごしているか。
- ・校内の環境: 掲示物はきれいに整理されているか。トイレや廊下は清潔に保たれているか。
- ・案内役の生徒: 自分の学校について、楽しそうに、誇りを持って話しているか。
こうした細かな点にこそ、その学校の本当の姿が表れます。
まとめ
中学受験の志望校選びは、決して簡単な道のりではありません。しかし、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、必ず「この学校で良かった」と思える選択ができます。
この記事でご紹介した志望校選びのポイントを、もう一度おさらいしましょう。
- ・始める時期: 小4から意識し始め、小5で本格化、小6の夏休み前までに決定するのが理想。
- 決め方のステップ: ①家庭の方針整理 → ②情報収集 → ③比較検討 → ④学校訪問で最終決定。
- ・比較のポイント: 偏差値だけでなく、教育方針、校風、通学時間、サポート体制など10のポイントで多角的に見る。
- ・最も大切なこと: 偏差値というものさし以上に、「お子さんの個性」と「学校の教育方針・校風」がマッチするかどうかを重視すること。
志望校選びの主役は、あくまでお子さん自身です。保護者の役割は、お子さんが自分に合った学校を見つけ、納得して受験に臨めるよう、伴走し、サポートすることです。
この記事が、皆さまの「後悔しない志望校選び」の一助となれば幸いです。親子で力を合わせ、素晴らしい未来への扉を開いてください。応援しています。




-61.jpg)
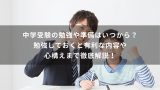


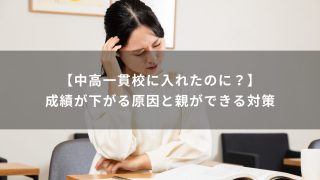
-38.jpg)
-40.jpg)