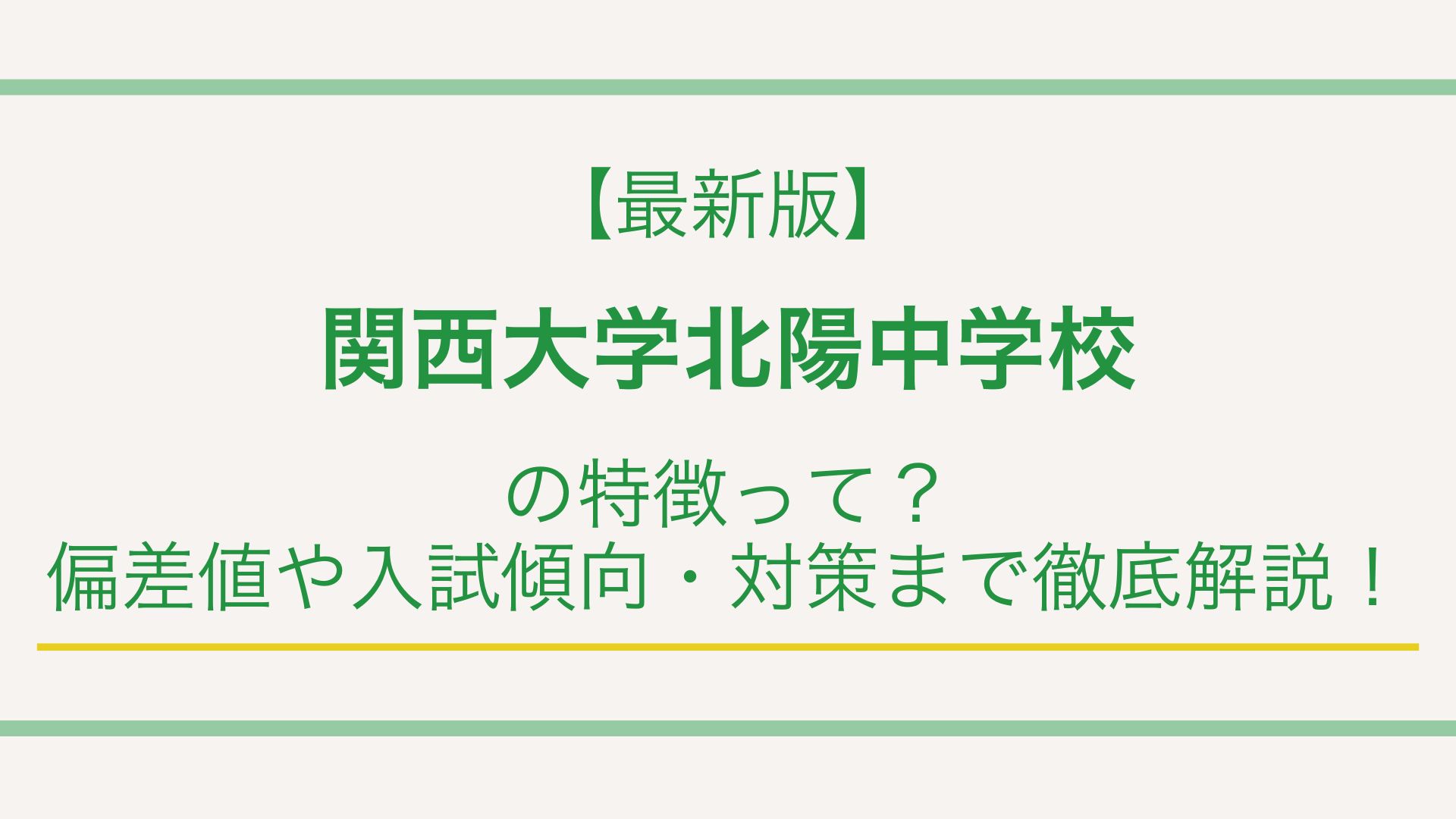「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)で『公共』という新しい科目が始まるらしいけど、一体どんな科目なの?」 「現代社会とは何が違うの?どうやって対策すればいい?」
2025年度の大学入試から本格的に導入される新科目「公共」について、多くの受験生や保護者の方がこのような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
この記事では、大学受験の専門家として、共通テストにおける「公共」の基本情報から、具体的な科目内容、効果的な勉強法、そして公民科目の選び方のポイントまで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、「公共」がどのような科目かが明確になり、自信を持って受験準備をスタートできます。
共通テストの「公共」とは?

まず、「公共」がどのような位置づけの科目なのか、基本から押さえていきましょう。旧センター試験の「現代社会」や、他の公民科目である「倫理」「政治・経済」との関係性を理解することが重要です。
新必修科目について
「公共」とは、2022年度から実施された高校の新学習指導要領で新設された公民科の必修科目です。これに伴い、2025年1月に実施される共通テストから、従来の「現代社会」に代わって「公共」が出題されることになりました。
これまでの「現代社会」が発展的にリニューアルされた科目と考えるとイメージしやすいでしょう。現代社会の様々な課題について、単に知識を暗記するだけでなく、多角的な視点から考察し、解決策を探究する力が問われます。
旧センター試験「現代社会」との違い
「公共」と「現代社会」の最も大きな違いは、知識の活用や思考力をより重視する点にあります。
倫理、政治・経済との関係性
「公共」は、倫理分野と政治・経済分野の基礎的な内容を統合した科目です。そのため、それぞれの専門科目である「倫理」「政治・経済」への橋渡し的な役割も担っています。
共通テストの公民科目は、この「公共」をベースとして、以下の3つの選択科目から1つを選ぶことになります。
つまり、「公共」の内容に加えて、より専門的な「倫理」または「政治・経済」を学習した成果が問われる仕組みです。
大学入学共通テストの仕組み

「公共」について理解を深めるために、まずは大学入学共通テストそのものの仕組みを再確認しておきましょう。旧センター試験との違いや科目選択のルールを知ることが、戦略的な受験計画の第一歩です。
旧センター試験からの主な変更点
共通テストは、旧センター試験と比べて以下の点が大きく変わりました。
教科・科目一覧と満点・配点
共通テストで実施される主な教科・科目と、その配点(満点)は以下の通りです。
| 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 200点 |
| 地理歴史・公民 | 「地理総合、地理探究」「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」「公共、倫理」「公共、政治・経済」などから最大2科目選択 | 各100点 |
| 数学 | 数学①:「数学Ⅰ, 数学A」または「数学Ⅰ」 数学②:「数学Ⅱ, 数学B, 数学C」 | 各100点 |
| 理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 「物理」「化学」「生物」「地学」 | 基礎2科目で100点 専門1科目で100点 |
| 外国語 | 英語(リーディング・リスニング)、ドイツ語、フランス語など | 200点(英語の場合) |
| 情報 | 情報Ⅰ | 100点 |
(参考:大学入試センター)
文系・理系別の科目選択モデル
志望する大学や学部によって必要な科目は異なりますが、一般的な選択モデルは以下の通りです。
必ず自分の志望校の募集要項で必要な科目を確認してください。
公民科目の選び方と注意点

共通テストでは、公民科目の選択が少し複雑です。特に「公共」の扱いには注意が必要です。
「公共」単独での受験は不可
最も重要な注意点は、共通テストにおいて「公共」1科目だけで受験することはできないということです。「公共」を受験する場合は、必ず「倫理」または「政治・経済」と組み合わせた科目を選択する必要があります。
このどちらかを選ぶことになります。
「公共、倫理」の組み合わせ
「公共」で扱う社会のルールや仕組みの基礎に加え、「倫理」で扱う古今東西の思想や哲学、人間の生き方について深く学びます。
「公共、政治・経済」の組み合わせ
「公共」の基礎の上に、「政治・経済」で扱う国内外の政治システムや経済活動の仕組みについて、より専門的に学びます。
第一解答科目のルールと選択時のポイント
地歴公民で2科目を受験する場合、「第一解答科目」と「第二解答科目」を選択する必要があります。ここで注意したいのが、大学によっては評価対象とする科目を「第一解答科目のみ」と指定している場合があることです。
例えば、地歴公民から1科目のみを必要とする大学を志望する場合、その大学が指定する科目を必ず「第一解答科目」として受験しなければ、得点が無効になってしまいます。
科目選択で失敗しないためにも、志望校の入試要項を早い段階で確認し、どの科目を第一解答科目にすべきか把握しておくことが極めて重要です。
公共の出題範囲と問題傾向

次に、「公共」で具体的にどのような内容が問われるのか、出題範囲と問題の傾向を見ていきましょう。
学習指導要領に基づく出題内容
「公共」の出題範囲は、文部科学省の学習指導要領で定められた以下の3つの大項目が中心となります。
(参考:文部科学省 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 公民編)
サンプル問題から見る難易度と特徴
大学入試センターが公開しているサンプル問題を見ると、難易度自体は「現代社会」と大きく変わらないものの、問題の形式がより思考力重視になっていることが分かります。
特徴的なのは、単に用語を答えさせる問題は少なく、架空の高校生による対話文や、新聞記事、統計データなどを読み解かせ、そこから何が言えるかを考えさせる問題が多い点です。
資料読解力と思考力を問う問題形式
「公共」の対策で最も重要なのは、初見の資料を素早く正確に読み解く力と、複数の情報を関連付けて考察する思考力を養うことです。
例えば、以下のような形式の問題が予想されます。
日頃から「なぜこうなるのだろう?」「別の見方はないだろうか?」と考える癖をつけることが、高得点への鍵となります。
公共の効果的な勉強法と対策

思考力が問われる「公共」ですが、やみくもに問題演習をしても力はつきません。効果的な勉強法と対策のポイントを3つ紹介します。
教科書を中心に基礎知識を固める
思考力問題の土台となるのは、正確な基礎知識です。まずは学校で使っている「公共」の教科書を徹底的に読み込み、太字の用語や基本的な概念を自分の言葉で説明できるようにしましょう。教科書の内容を疎かにして、応用問題ばかり解こうとするのは非効率です。
日頃から時事問題に関心を持つ
「公共」は、私たちが生きる現代社会と密接に結びついた科目です。新聞や信頼できるニュースサイトに目を通し、社会で起きている出来事に関心を持つ習慣をつけましょう。
ただニュースを見るだけでなく、「この問題の背景には何があるのか」「異なる立場の人々は、この問題をどう見ているのか」といった視点で考えることが、そのまま「公共」の学習につながります。
おすすめの参考書と問題集
教科書とニュースに加えて、市販の参考書や問題集を活用することで、より効率的に学習を進められます。
大学入学共通テスト 公共 集中講義(旺文社)
新科目「公共」の全体像を掴むのに最適な一冊。要点がコンパクトにまとまっており、短期間で基礎を固めたい人におすすめです。
共通テスト問題研究 公共、倫理/公共、政治・経済(教学社)
通称「赤本」シリーズ。大学入試センターのサンプル問題や試作問題、大手予備校の予想問題などが収録されており、実践的な演習に役立ちます。
きめる!共通テスト 公共(学研プラス)
講義形式で分かりやすく解説されており、初学者でもスムーズに学習を進められます。イラストや図解が豊富で、視覚的に理解しやすいのが特徴です。
共通テスト「公共」のよくある質問

最後に、受験生からよく寄せられる「公共」に関する質問にお答えします。
「倫理、政治・経済」とどちらが有利?
結論から言うと、一概にどちらが有利・不利ということはありません。 自分の興味や得意分野に合わせて選ぶのが最善です。
を選ぶと良いでしょう。また、二次試験で「倫理」や「政治・経済」が必要な場合は、それに合わせて選択する必要があります。
浪人生の経過措置はどうなる?
2025年度の共通テストでは、旧課程で学習した浪人生などのために経過措置が設けられます。公民科では、旧課程の「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」が選択可能です。
ただし、この経過措置は2025年度入試限定の可能性が高いため、注意が必要です。 (参考:大学入試センター 令和7年度大学入学共通テストからの出題教科・科目等について)
公共だけで受験できる大学はある?
共通テストを利用する入試においては、「公共」単独で受験できる大学は基本的にありません。 前述の通り、「公共、倫理」または「公共、政治・経済」のいずれかを選択する必要があります。
ただし、一部の私立大学が独自に行う一般選抜(個別学力検査)において、「公共」を単独の試験科目として課す可能性はあります。こちらも、必ず志望校の募集要項で確認してください。
まとめ
今回は、2025年度の共通テストから始まる新科目「公共」について、その内容から対策法、科目選択の注意点まで詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
新しい科目に不安を感じるかもしれませんが、問われる力の本質は「社会をより良くするために、主体的に考える力」です。これは大学での学びや、その後の人生でも必ず役立つ力です。
この記事を参考に、ぜひ前向きな気持ちで「公共」の学習に取り組んでみてください。応援しています!




-2-1.jpg)