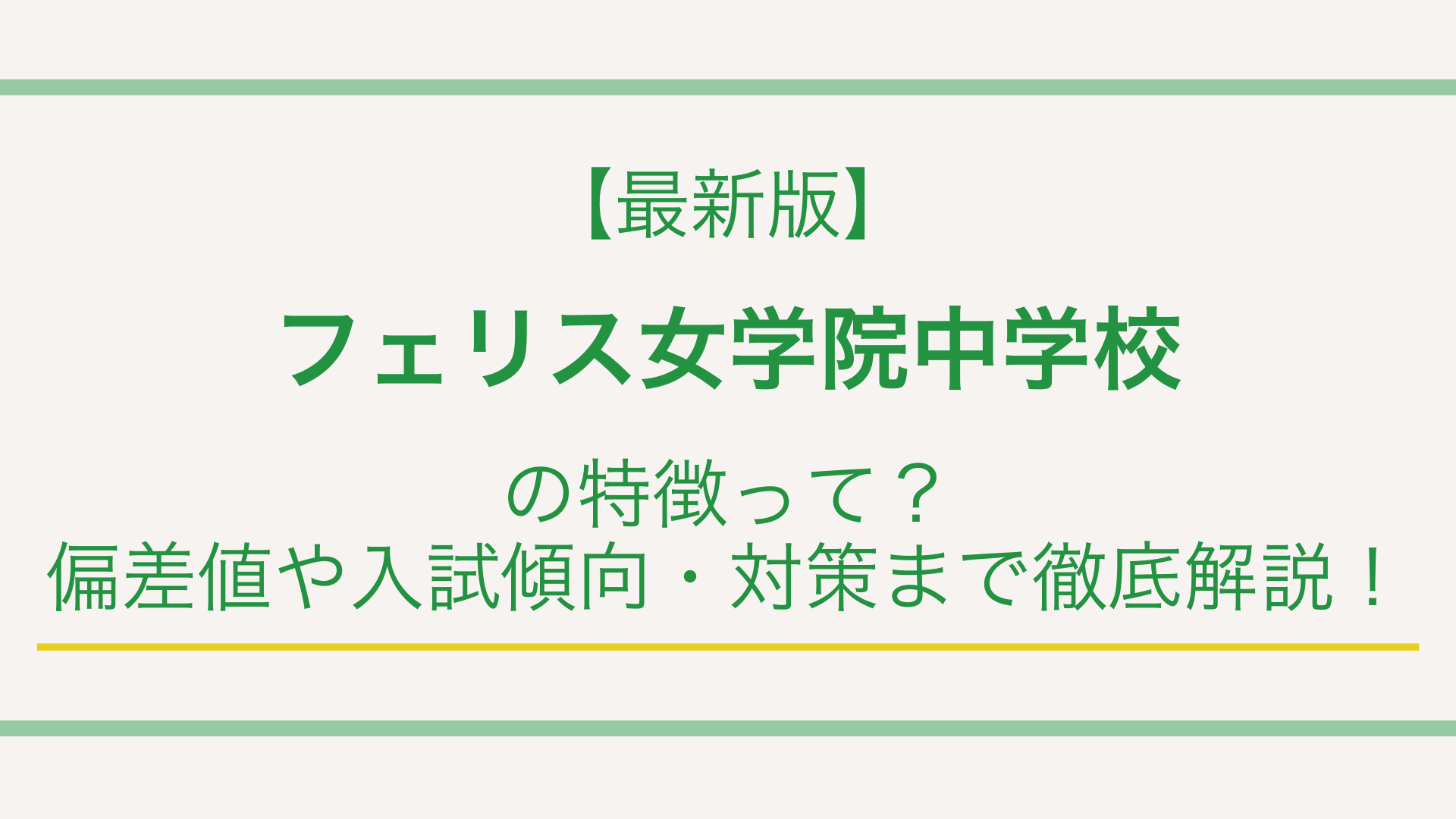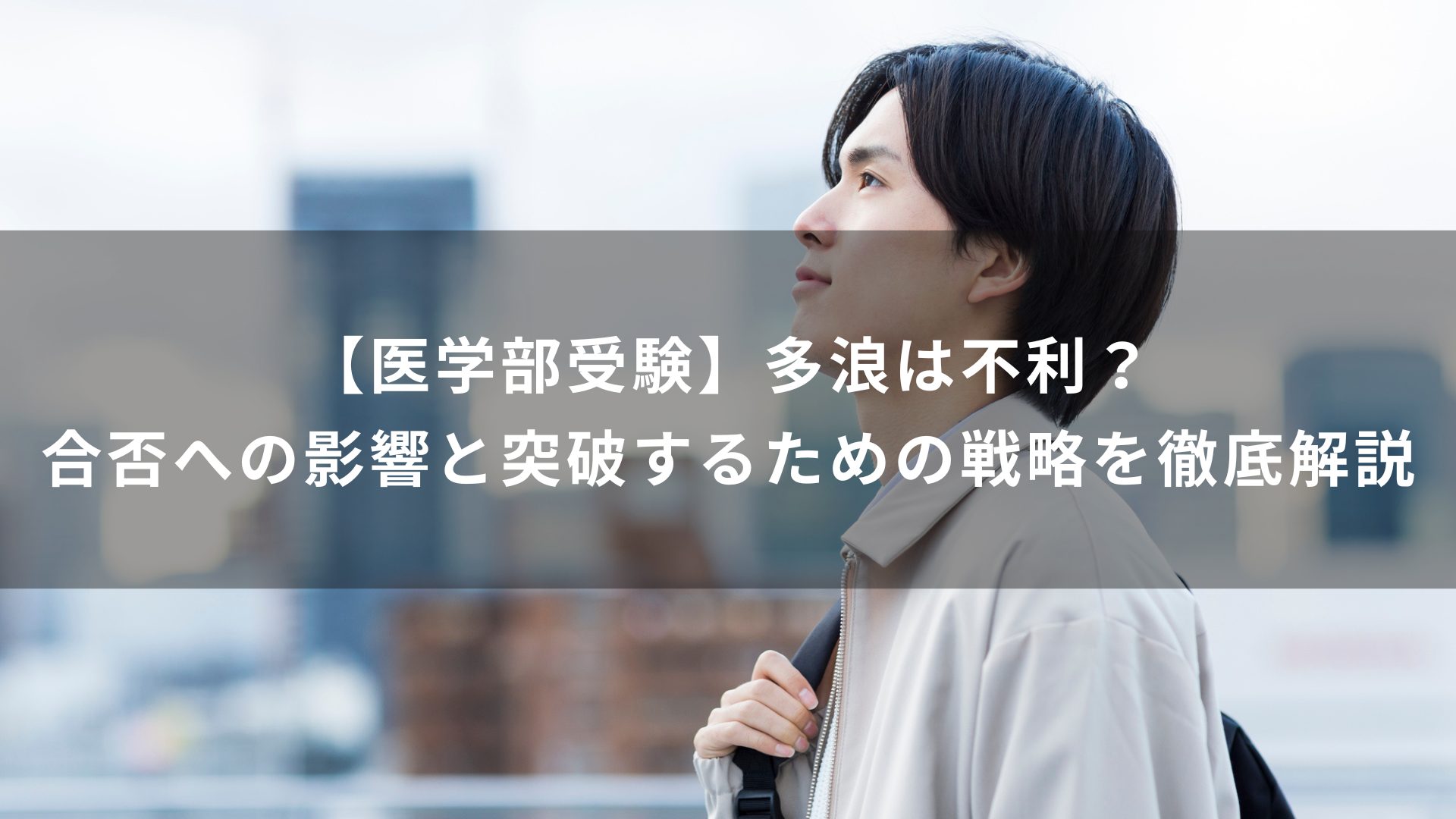不登校のお子さんを持つ保護者の皆さんにとって、「出席日数ゼロ」という現実は、進路への大きな不安材料となることでしょう。しかし、ご存知でしょうか? 文部科学省が定める「出席扱い(出席認定)」という制度を利用すれば、学校外での学習が学校の出席として認められるケースがあるのです。
本記事では、この出席扱い制度の概要から、ICT教材「すらら」と家庭教師を組み合わせることで、どのように出席認定を目指せるのかを具体的に解説します。お子さんの学習をサポートしながら、未来への選択肢を広げるための一助となれば幸いです。
出席扱い(出席認定)とは?制度の概要と対象

お子様の不登校で悩む保護者の方々にとって、学校の「出席日数」は大きな懸念事項ではないでしょうか。まずは、なぜ出席日数が重要なのか、そしてその問題を解決し得る「出席扱い」制度について見ていきましょう。
なぜ「出席日数ゼロ」だと困るのか(内申点や進路選択への影響)
学校生活において、出席日数は内申点に大きく影響します。多くの都道府県では国立・公立の高校進学時に内申点を重視する傾向があります。出席日数が不足していると、たとえ学力が高くても、受験資格が得られなかったり、総合点での判断を受ける時に不利に働いたりする可能性があります。結果として、出席日数はお子様の進路選択の幅を狭めてしまう要因となりかねません。お子様の将来を考えれば、この「出席日数ゼロ」の状態を解消することは、保護者の方にとって喫緊の課題と言えるでしょう。
文部科学省が示す「出席扱い(出席認定)」の制度とは
このような不登校児童生徒の進路への影響を緩和するため、文部科学省は「不登校児童生徒への支援について(通知)」の中で、学校外での学習活動を「出席扱い」と認めるケースがあることを示しています。これは、不登校であっても学びを継続し、社会参加への道筋を確保するための重要な制度です。自宅での学習やフリースクールへの登校・通所など、学校以外の場所での学習活動が一定の条件を満たせば、学校の出席として認められる可能性があるのです。
対象となるのはどんなケース?
出席扱いが認められるのは、主に以下のようなケースです。
- ・病気や発達特性等により学校への通学が困難な場合
- ・不登校の状態にあるが、自宅などで継続的な学習に取り組んでいる場合
- ・フリースクールやICT教材を活用した学習など、学校が適切と判断した学習活動
重要なのは、単に学校を休んでいるだけではなく、「自宅などでの学習を継続していること」が前提となる点です。そして、その学習が学校の教育課程に照らして適切であると学校側が判断することが必要となります。
ICT教材「すらら」とは?特徴と学習の仕組み

ここからは、出席扱いを目指す上で強力なツールとなるICT教材「すらら」について、その特徴と学習の仕組みを詳しくご紹介します。
すららの基本機能と特徴(AI教材、自宅学習、個別最適化)
「すらら」は、株式会社すららネットが開発・提供する対話型アニメーション教材です。小学校から高校までの主要5教科(国語、数学、理科、社会、英語/※高校は情報も加えた6教科)に対応しており、お子様の自宅学習を強力にサポートします。
主な特徴は以下の通りです。
- 【AI教材による個別最適化】
お子様の学習履歴や理解度に応じて、AIが最適な問題や解説を提示します。苦手な分野は基礎から丁寧に、得意な分野は応用へと、一人ひとりのレベルに合わせた学習が可能です。 - 【対話型アニメーション】
一方的な講義形式ではなく、キャラクターとの対話を通じて楽しく学べるアニメーション形式を採用しています。これにより、飽きることなく学習を続けやすいのが特徴です。 - 【自宅でいつでも学習可能】
インターネット環境があれば、PCやタブレットを使っていつでもどこでも学習できます。通学の負担がないため、不登校のお子様でも安心して取り組めます。 - 【無学年方式】
学年の枠にとらわれず、お子様のペースで過去学年の内容にさかのぼって学習したり、次学年の内容に進んだりすることができます。これにより、つまずきを解消し、得意分野を伸ばすことが可能です。
すららを使った学習で出席扱い(出席認定)される理由

すららを使った学習が出席扱いとして認められやすい理由は、その「学習の仕組み」にあります。
学習履歴の記録
すららは、お子様の学習時間、進捗状況、正答率などを詳細に記録します。これにより、学校側は「どれくらい学習に取り組んでいるか」を客観的なデータで確認できます。
個別指導の要素
家庭教師の指導と組み合わせることで、すららでの学習内容についての疑問点を解消したり、より深く理解するための補足指導を受けたりすることができます。この個別指導も、学校外の学習が「教育課程に照らして適切」と判断される重要な要素となります。
体系的な学習内容
すららの教材は、文部科学省の学習指導要領に準拠しており、学校で学ぶ内容を網羅しています。これにより、学校側はすららでの学習が学校のカリキュラムと乖離していないと判断しやすくなります。
学研の家庭教師での利用メリット
「すらら」は単体でも学習が可能ですが、学研の家庭教師と組み合わせることで、その効果はさらに高まります。
すらら利用料込みの料金プラン
すららは個人利用も可能なICT教材で個人利用の場合の料金は以下の通りとなります。
| 学研の家庭教師 ※2025年4月15日以降にご入会された生徒様対象 | ||||
| 小・中・高 3科目(国語・算数・英語) | 無料で利用可能! | |||
| すらら個人利用 ※プランは一例です。 | |
| 小・中 3科目(国語・算数・英語) 中・高 3科目(国語・算数・英語) | 入会金11,000円+月額8,800円 |
| 小・中・高 3科目(国語・数学・英語) | 入会金11,000円+月額11,000円 |
学研の家庭教師の不登校専門コースは、全てのコースにすららの利用権利が付与されており、追加料金を支払うことなくご利用いただけます。これにより、別途教材費を気にすることなく、質の高い家庭教師の指導とすららを併用できます。
すららに精通した家庭教師
学研の家庭教師の不登校専門コースは、すららの特性を理解してお子様のすららでの学習状況を把握した上で、適切な指導やアドバイスを提供します。すららだけでは解決しづらい疑問や、学習計画の立案などもサポートします。
進路相談・学校との連携サポート
学研の家庭教師の不登校専門コースは、これまでもお子様の学習面だけでなく、進路に関する相談や、学校との連携に関するアドバイス、生活面のご相談も行ってまいりました。出席扱いを目指す上で、学校との円滑なコミュニケーションは不可欠であり、このサポートは大きなメリットとなります。
すららで出席扱い(出席認定)を受けるための条件と準備

出席扱いを勝ち取るためには、文部科学省が示す要件を理解し、準備を整えることが不可欠です。「すらら」がどのようにこれらの要件を満たすのか、そして家庭と学校との連携の重要性を見ていきましょう。
文科省が示す「出席扱い(出席認定)」の7つの要件とは
文部科学省が示す「不登校児童生徒への支援について(通知)」には、学校外での学習を「出席扱い」と認めるための7つの要件が示されています。
- 1.保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- 2.学校外の機関における学習活動であることが、学校が把握していること
- 3.学校外の機関における学習活動の内容が、学校の教育課程に照らして適切と判断されること
- 4.学校外の機関における学習活動の評価が、学校として適切と判断されること
- 5.学校外の機関における学習活動が、生徒の社会的自立に向けた学びであると判断されること
- 6.学習活動の成果が、学校に報告されていること
- 7.学校が児童生徒の学習成果を評価し、指導に活かしていること
これらの要件をすべて満たすことが、出席扱いを受けるための重要なステップとなります。
すららが要件をどのように満たしているか
ICT教材「すらら」と学研の家庭教師の組み合わせは、上記の7つの要件を強力にサポートします。
- 保護者と学校との連携
担任となる講師および教務スタッフが間に入り、保護者様と学校との連携をサポートします。すららの学習履歴を学校に共有するお手伝いもしています。 - 学校が把握
家庭教師を通じて、すららでの学習計画や進捗を学校に共有し、学校側が学習状況を把握しやすい環境を整えます。 - 教育課程との整合性
すららの教材は、学習指導要領に準拠しており、学校で学ぶ内容と高い整合性を持っています。 - 適切な評価
すららは学習履歴を詳細に記録し、家庭教師が学習の定着度を確認します。これらの客観的なデータと家庭教師による評価を学校に提示できます。 - 社会的自立への学び
学研の家庭教師の不登校専門コースは学習指導だけでなく、コミュニケーション支援、外出のサポートもしているため、自律学習の習慣づけや学習意欲の向上を促すことで、お子様の社会的自立に向けた学びをサポートします。 - 学習成果の報告
すららの学習履歴データや講師からの報告を通じて、定期的に学習成果を学校に報告できます。 - 学校での評価と指導への活用
学校側は、報告されたすららでの学習成果をもとに、お子様の評価や今後の指導に活かすことができます。
出席扱い(出席認定)に必要な家庭・学校との連携内容
出席扱いを受けるためには、家庭と学校、そして家庭教師の三者間での密な連携が不可欠です。
保護者から学校への相談
まずは保護者様から学校の担任や学年主任または教頭に、出席扱いを検討している旨を相談することが出発点です。
学習計画の共有
すららでの学習計画を具体的に作成し、学校と共有します。どのような教材を使い、どれくらいの時間を学習に充てるのかなどを明確に示しましょう。
定期的な学習状況の報告
すららの学習履歴データや講師からの報告書などを活用し、定期的に学校へ学習状況を報告します。
面談の実施
必要に応じて、保護者様、学研の家庭教師、学校の先生との三者面談を実施し、お子様の状況や学習の進捗について情報共有を行います。
学校からのフィードバックの受領
学校からの意見やアドバイスを真摯に受け止め、必要に応じて学習計画を調整することも重要です。
実際に出席扱い(出席認定)を申請する流れ【4ステップ】
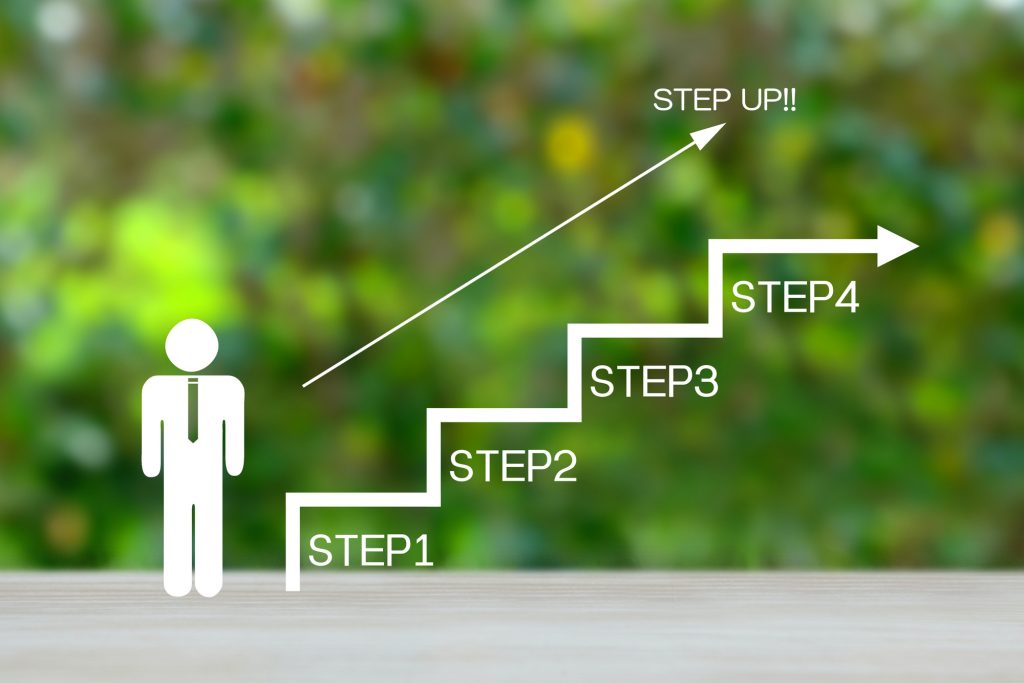
出席扱いを申請する具体的な流れは、以下の4つのステップで進みます。焦らず、1つずつ着実に進めていきましょう。
STEP1|担任に相談する
まず最初に、お子様の担任の先生に相談しましょう。不登校の状況や、自宅での学習を考えていること、そして出席扱いを希望している旨を伝えます。この時、感情的にならず、お子様の状況を具体的に説明し、協力を求める姿勢が重要です。先生も、お子様の学びを止めないために、何ができるかを一緒に考えてくれるはずです。可能であれば、家庭教師をつけることを検討していることや、ICT教材「すらら」の活用を考えていることも伝えておくと、話がスムーズに進みやすくなります。
STEP2|学校側での検討と可否判断
担任の先生に相談した後、学校内で出席認定の可否について検討が始まります。文部科学省は「学校長裁量」と定めていますが、地域によっては教育委員会との相談が必要な場合もあります。校長先生や教頭先生、学年主任、担任の先生、養護教諭や不登校担当教諭などが集まり、お子様の状況や学習内容が文部科学省の定める要件を満たしているか、学校の教育課程に照らして適切かなどを総合的に判断します。この際、保護者様から提出された情報(すららでの学習計画など)が重要な判断材料となります。
STEP3|学習計画と出席扱い(出席認定)ルールの確認
学校側が出席認定に前向きな姿勢を示してくれたら、次は具体的な学習計画と出席認定のルールを学校と確認します。
- 【学習計画】
週に何時間、どの科目を、すららを使って学習するのかを具体的に決めます。学研の家庭教師が、お子様の学習状況に合わせて最適な計画立案をサポートします。 - 【出席認定のルール】
例えば、「すららで週〇時間学習し、家庭教師の指導を週△時間受けることで、出席として認められる」といった具体的なルールが学校から提示されます。学習成果の報告頻度(月1回など)や、報告方法(すららの学習履歴を印刷して提出or確認用の学校アカウントの付与など)についても確認しておきましょう。これらのルールは学校によって異なるため、書面で確認することをおすすめします。
STEP4|出席扱い(出席認定)スタートと実施時の注意点
学校との合意が得られれば、いよいよ出席認定がスタートします。すららでの学習と家庭教師の指導を計画通りに進めていきましょう。 実施時の注意点としては、以下の点が挙げられます。
- 【計画通りの学習継続】
決められた学習時間を守り、継続して学習に取り組むことが重要です。すららは学習履歴が記録されるため、サボるとすぐにわかってしまいます。 - 【定期的な学習報告】
学校から求められた頻度で、すららの学習履歴や講師からの報告書などを提出し、学習状況を共有しましょう。 - 【学校との連携維持】
疑問点や困ったことがあれば、遠慮なく学校や家庭教師に相談し、連携を継続しましょう。
保護者がよく抱える不安とサポート事例

出席扱いを目指す中で、保護者の方々が抱えがちな不安と、学研の家庭教師が提供する具体的なサポートを過去事例も交えてご紹介します。
よくある質問Q&A
Q. 学校から出席扱いを拒否されたらどうすればいいですか?
A. まずは、拒否された理由を具体的に学校に確認しましょう。「学習内容が不足している」「連携が不十分」など、具体的な課題がわかれば、それに対応する対策を講じることができます。学研の家庭教師は、学校との交渉や、より説得力のある学習計画の再提案をサポートします。場合によっては、教育委員会に相談することも1つの選択肢です。
Q. ICT教材に不慣れで、使いこなせるか不安です。
A. ご安心ください。すららは直感的に操作できる設計ですが、もし操作に不安があれば、学研の家庭教師が初期設定から学習の進め方まで丁寧にサポートします。お子様だけでなく、保護者様の疑問にもお答えしますので、安心してご活用いただけます。
Q. 子供がすららの学習を嫌がったらどうすればいいですか?
A. 不登校のお子様の場合、学習に対して抵抗感があるのは自然なことです。家庭教師の指導も直前になってキャンセルをされることもしばしば。学研の家庭教師は、お子様の興味や特性に合わせ、気持ちに寄り添ったうえで、すららの効果的な使い方を提案したり、学習内容を工夫したりします。無理強いせず、まずは短時間から始めて、少しずつ学習に慣れていくようなサポートを心がけます。お子様が学習を楽しめるよう、一緒に試行錯誤していきましょう。
出席扱い(出席認定)された実例紹介
Aさんのケース(中学2年生・不登校)
Aさんは中学2年生の夏休み明けから、人間関係が原因で学校に行けなくなってしまいました。自宅でゲームばかりしているAさんを見て、お母様はこのままでは高校進学が難しいのではないかと大きな不安を抱えていました。そんな時、学研の家庭教師で「すらら」を使った出席扱いができることを知り、藁にもすがる思いで相談しました。
担当の教務スタッフは、まずAさんと面談し、彼の興味や学習状況を丁寧にヒアリング。最初は渋っていたAさんも、すららのアニメーション教材がゲーム感覚で取り組めることに興味を持ち、少しずつ学習をスタートさせました。講師は週に2回訪問し、すららで学習した内容の解説や、Aさんの学習計画の進捗を確認。お母様とも毎回10分ほどの指導報告の機会を設けて密に連携を取り、Aさんの学習状況や心の状態を共有しました。
そして、教務スタッフがお母様と一緒に学校に出向き、すららでの学習計画と学研の家庭教師のサポート体制を説明。すららの学習履歴データも提示し、Aさんが着実に学習に取り組んでいることを伝えました。学校側もAさんの学習意欲を評価し、週に10時間、すららでの学習と家庭教師の指導を組み合わせることで出席扱いを認めてくれることになりました。
出席扱いが始まったことで、Aさんもお母様も大きな安心感を得ることができました。Aさんは「出席がついている」という自信から、徐々に学習意欲を高め、今では高校受験に向けて前向きに取り組んでいます。
学研の家庭教師によるフォロー体制
学研の家庭教師は、お子様の出席扱いをトータルでサポートします。
- 【学習計画の立案】
お子様の状況に合わせた最適な学習計画を立案します。 - 【学習の進捗管理とモチベーション維持】
定期的な指導を通じて、学習の進捗を確認し、お子様のモチベーションを維持するサポートを行います。 - 【学校との連携サポート】
保護者様に代わって、学校への学習状況の報告や、出席認定に関する相談することもあります。 - 【保護者へのカウンセリング】
不安や悩みを抱える保護者様に対し、経験豊富な教務スタッフが親身に寄り添い、アドバイスを提供します。お電話のほか、LINE@(公式アカウント)も設置していますので忙しい保護者様でも時間を気にせずご相談いただけます。 - 【進路相談】
出席扱い後の進路指導についても、お子様の適性や希望に合わせてさまざまなアドバイスを行います。
まとめ
不登校のお子様を持つ保護者の皆さんにとって、出席日数の問題は大きな壁となりがちです。しかし、文部科学省が定める「出席扱い(出席認定)」制度と、ICT教材「すらら」そして学研の家庭教師を組み合わせることで、その壁を乗り越え、お子様の未来への選択肢を大きく広げることができます。
出席扱いを目指す上でのポイントは以下の通りです。
お子様の「学びたい」という気持ちを大切にし、未来への道筋を一緒に切り開きましょう。
学研の家庭教師では、すららを使った出席認定に関する無料相談を受け付けています。 お子様の状況に合わせて、最適な学習プランや出席認定に向けた具体的なステップをご提案させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。




-2-1.jpg)