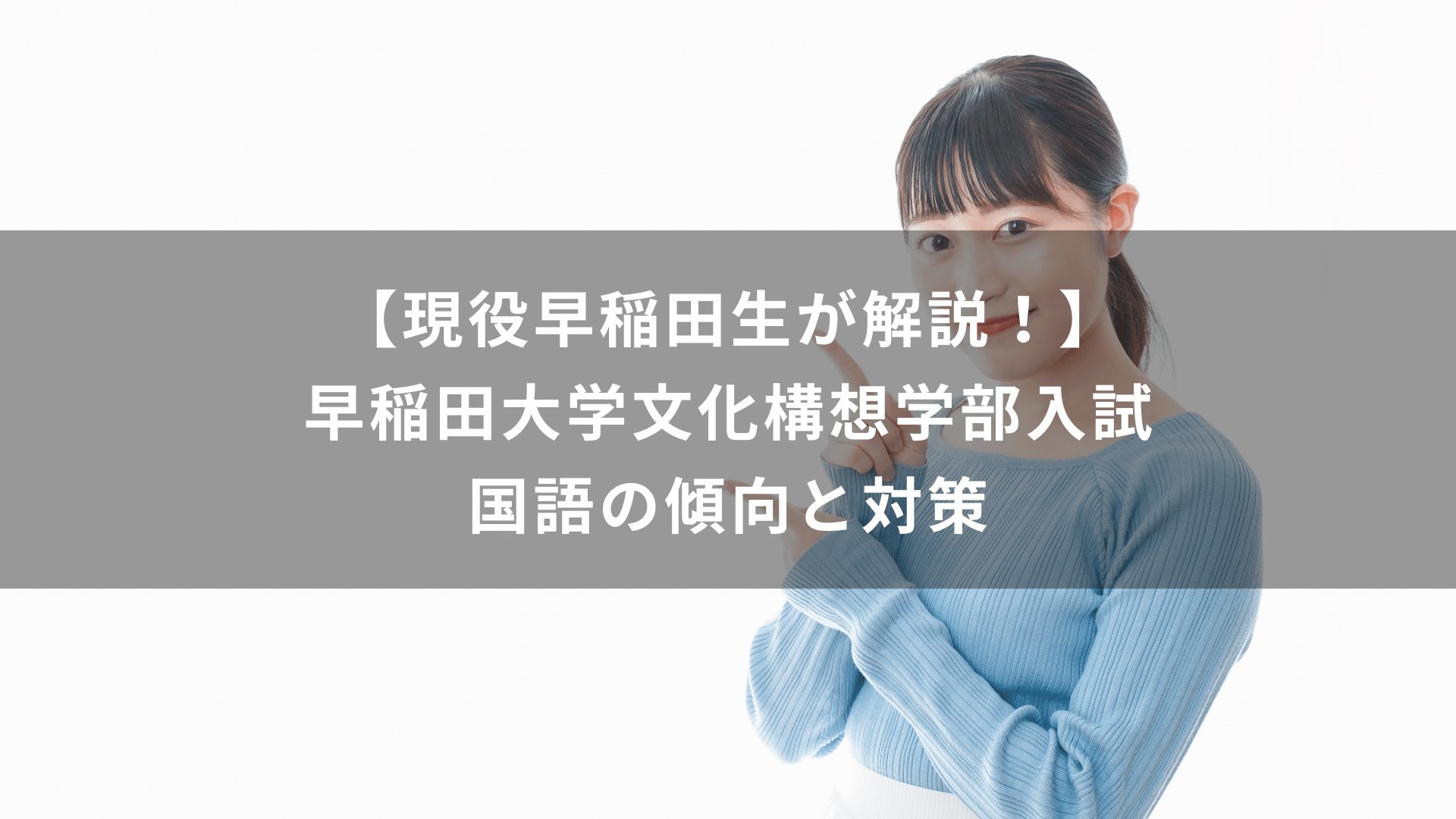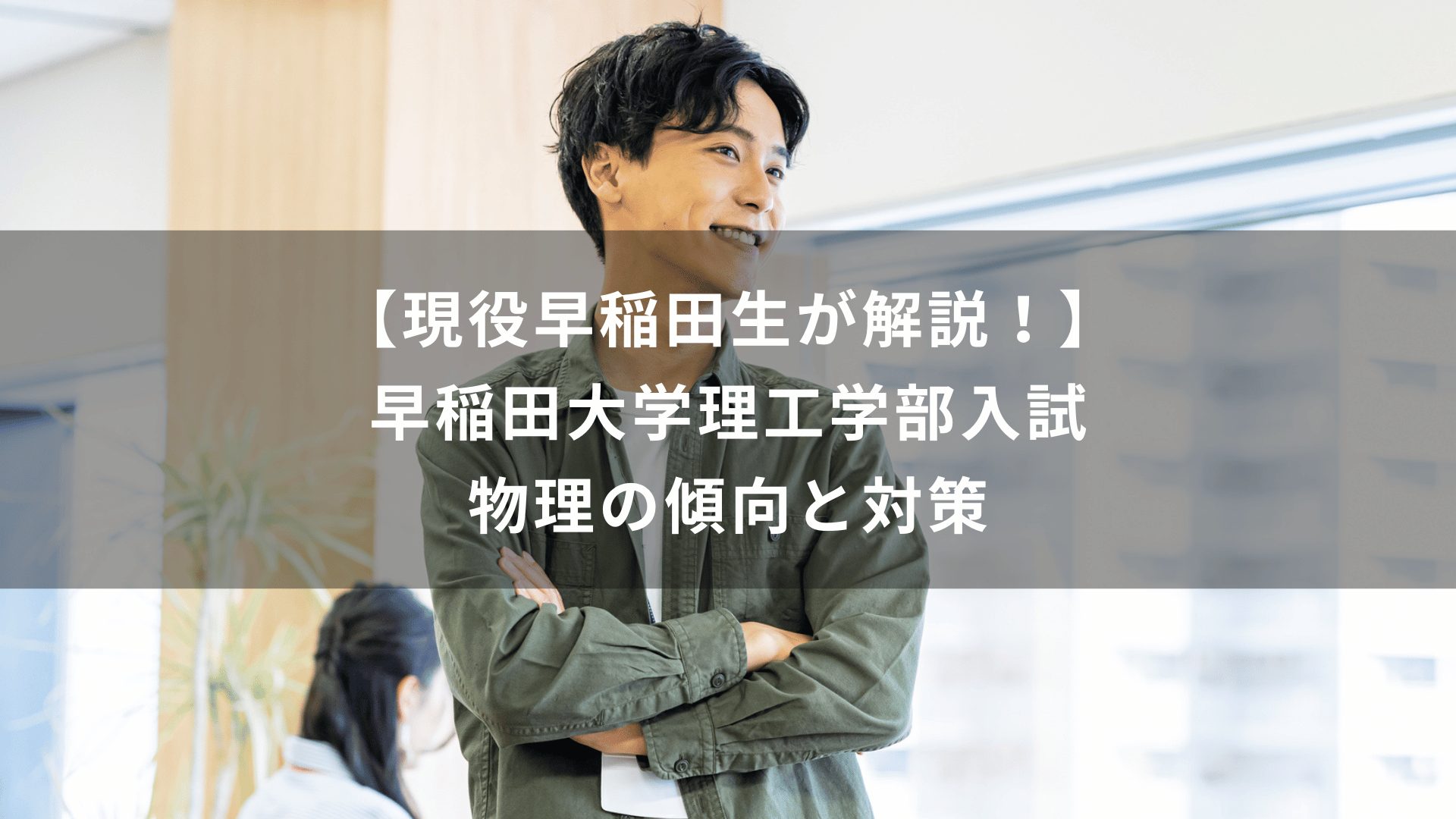子どもが「学校に行きたくない」と言い出す、いわゆる「行き渋り」に直面すると、親としてどう対応すべきか悩むものです。行き渋りに適切に対応することは非常に重要で、対応次第では不登校に繋がることもあります。
この記事では、子どもの行き渋りの原因と兆候を解説し、保護者が子どもに対してどのような対応をとるべきかをお伝えします。また、家庭だけでは解決が難しい場合に頼れる相談先についても紹介します。ぜひ参考にしてください。
子どもの行き渋りの原因と見逃してはいけない兆候

行き渋りの兆候は、子どもの微妙な行動や態度に現れることが多く、それを見逃さないことが重要です。例えば、朝の準備が遅くなったり、体調不良を訴えるといった変化は、行き渋りの前兆である可能性があります。以下に、具体的な兆候とその原因について紹介します。
・学校関係:友人とのトラブルや勉強への不安
・兆候:朝の準備が遅くなる、学校に行く途中で体調不良を訴える、友人や勉強の話をしたがらないなど
・環境の変化:学年が変わる、クラス替え、長期休暇明けなど
・兆候:登校前に体調不良を訴える、特に理由がなく学校に行くことを嫌がる
・心身の不調:自己肯定感の低下、無気力感、慢性的な疲労感など
・兆候:普段楽しんでいた活動に興味を示さなくなる、朝起きられなくなる
・発達障害や特性:学校の環境や集団生活に適応できない
・兆候:特定の授業や活動を嫌がる、学校のルールや他の子どもたちとのコミュニケーションに苦しんでいる様子がみられる
どのような原因であっても、行き渋りの兆候が現れる段階で、子どもは学校に対して不安やプレッシャーを感じている可能性が高く、保護者や教師のサポートを必要としています。
行き渋りへの適切な対応と避けるべき対応の具体例
子どもの行き渋りに対して、どのような対応を取るべきか悩む保護者は多いでしょう。ここでは、保護者が取るべき「適切な対応」と、「避けるべき対応」について詳しく解説します。
保護者の適切な対応とは
子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、まずは焦らずに子どもの気持ちに寄り添うことが大切です。行き渋りの際、子どもは不安やストレスを抱えていることが多く、保護者がその気持ちを認めて共感することで、子どもに安心感を与えます。
時には、学校を少し休ませることで、子どもの不安が軽減し、気持ちが落ち着くこともあります。保護者は無理に学校へ行かせるのではなく、子どもに選択肢を与えながら、安心できる環境を整えていきましょう。
避けた方がいい対応とは
逆に、行き渋りに対して「避けるべき対応」は、子どもの感情を無視したり、否定するような言動です。また、プレッシャーをかけて無理に学校へ通わせることは、短期的には問題が解決するように見えても、根本的な解決にはなりません。
行き渋りで頼れる相談先とは
行き渋りが続く場合は、保護者だけで対処せず、専門家や支援機関の助けを借りることが重要です。以下は、行き渋りに対する相談先として頼れる場所です。
スクールカウンセラーや教育相談窓口
学校内にいるスクールカウンセラーは、すぐに相談できる頼れる存在です。また、教育支援センター(適応指導教室)やフリースクールも不登校や行き渋りへの対応を専門としています。
精神科や心療内科
精神科や心療内科では、子どもの心身の状態を専門的に診断し、適切な治療やサポートを提供します。子どもの様子が深刻な場合(眠れていない、自傷行為があるなど)はすぐにカウンセラーに相談しましょう。
どこに相談していいかわからない場合は下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
行き渋りは、子どもが学校生活に不安やストレスを感じている兆候です。保護者の方は、その兆候を見逃さず、早期に適切な対応を取ることが重要です。無理に学校へ行かせるのではなく、子どもに寄り添い安心できる環境を提供することで、子どもの心の負担を軽減しましょう。また、家庭内で抱え込まず、学校や専門機関と連携し、サポートを受けることが大切です。
弊社が運営する学研の家庭教師 不登校専門コースでは、不登校支援に豊富な実績を持つ講師が対応します。お子さまの気持ちに寄り添いながら、安心できる関係性づくりを大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。