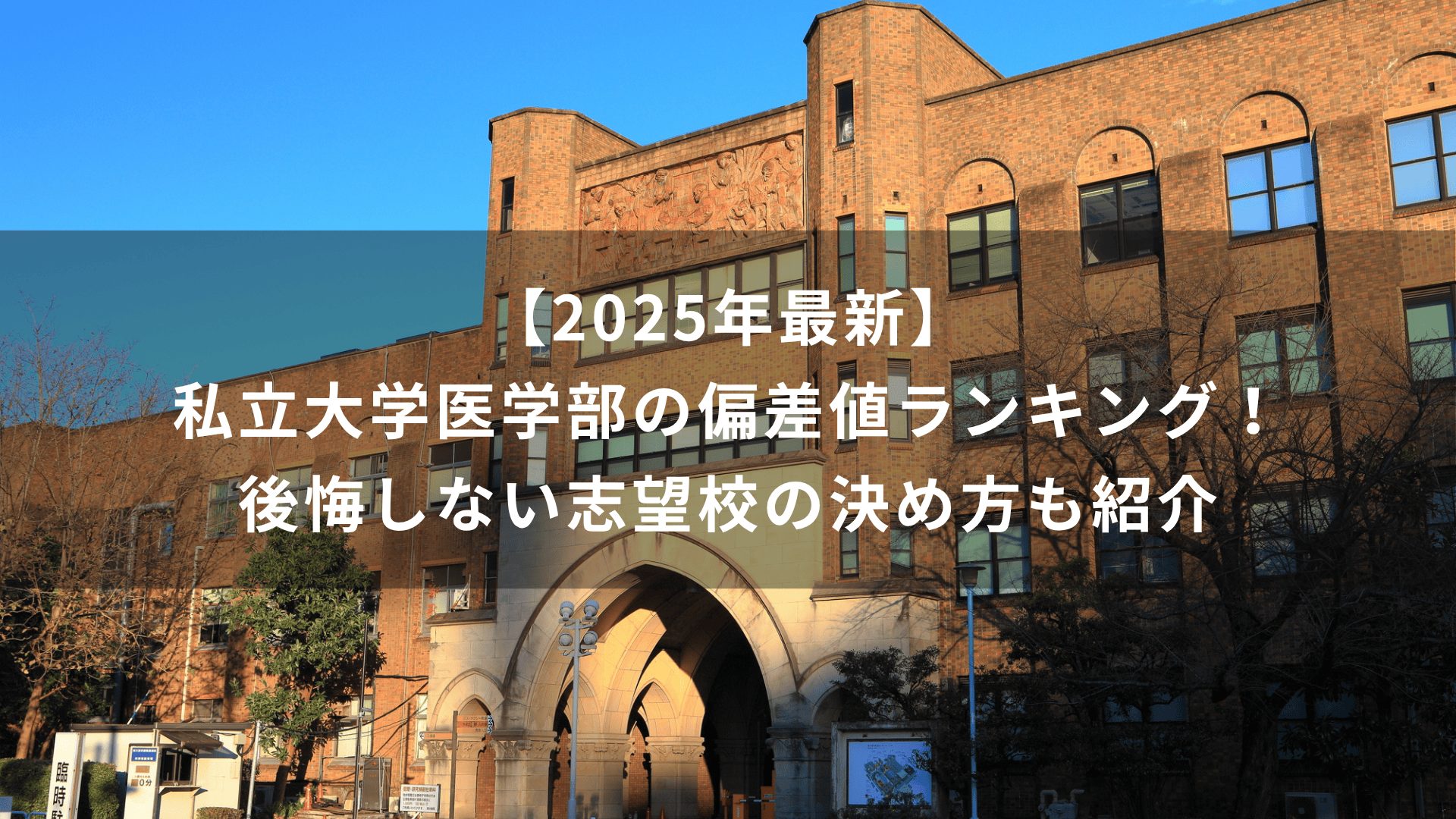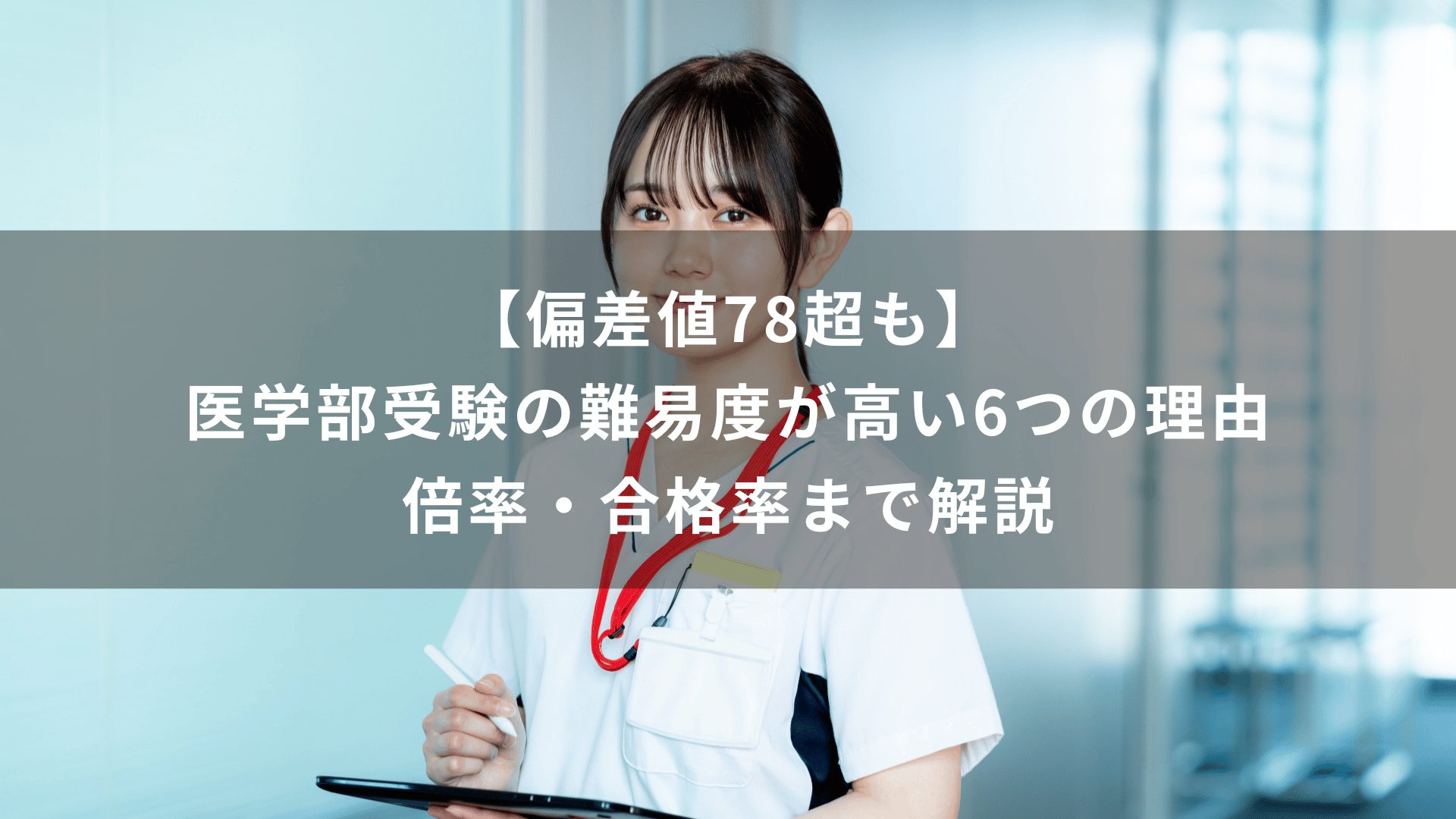「医学部に行きたいけど、どの大学を選べばいいかわからない…」 「自分の偏差値で合格できる私立医学部はどこだろう?」
医学部受験を控えたあなたや、お子様の進路を考える保護者の方にとって、志望校選びは最も重要で、そして悩ましい問題ではないでしょうか。特に私立大学医学部は、大学ごとに偏差値や学費、入試傾向が大きく異なり、情報収集だけでも一苦労です。
この記事では、医学部志望校選びの専門家として、2025年最新の私立大学医学部偏差値ランキングを分かりやすく解説します。さらに、偏差値だけでなく学費や国家試験合格率といった多角的な視点から、後悔しない志望校の選び方を具体的なステップでご紹介します。
この記事を読めば、膨大な情報の中からあなたに最適な志望校候補を絞り込み、自信を持って出願に臨むことができるようになります。
私立大学医学部の最新偏差値ランキング【2025年】

まずは、志望校選びの最も重要な指標となる最新の偏差値ランキングを見ていきましょう。ここでは、大手予備校の公開データを基に、偏差値帯別に大学をまとめました。
ご自身の模試の成績と照らし合わせながら、どのレベルの大学が視野に入るかを確認してみてください。
【偏差値70.0以上】最難関レベルの大学一覧
このレベルの大学は、私立医学部のトップに君臨し、国公立大学医学部と併願する受験生も多い最難関グループです。
- 慶應義塾大学(東京都):72.5
- 東京慈恵会医科大学(東京都):70.0
【偏差値67.5〜69.9】上位〜中堅レベルの大学一覧
上位〜中堅レベルには、歴史と実績のある大学や、特定分野に強みを持つ人気の大学が数多く含まれます。
- 順天堂大学(東京都):69.0
- 日本医科大学(東京都):69.0
- 自治医科大学(栃木県):68.5 ※地域医療への貢献が前提
- 大阪医科薬科大学(大阪府):68.5
- 関西医科大学(大阪府):68.0
- 産業医科大学(福岡県):67.5 ※産業医の養成が目的
- 昭和大学(東京都):67.5
- 東邦大学(東京都):67.5
- 国際医療福祉大学(千葉県):67.5
【偏差値65.0〜67.4】中堅〜下位レベルの大学一覧
この偏差値帯は、多くの私立医学部がひしめく激戦区です。大学ごとの特色をしっかり比較検討することが合格の鍵となります。
- 東京医科大学(東京都):67.0
- 近畿大学(大阪府):66.5
- 日本大学(東京都):66.5
- 藤田医科大学(愛知県):66.0
- 兵庫医科大学(兵庫県):66.0
- 愛知医科大学(愛知県):65.5
- 杏林大学(東京都):65.5
- 久留米大学(福岡県):65.5
- 福岡大学(福岡県):65.5
- 岩手医科大学(岩手県):65.0
- 金沢医科大学(石川県):65.0
- 埼玉医科大学(埼玉県):65.0
- 聖マリアンナ医科大学(神奈川県):65.0
- 帝京大学(東京都):65.0
- 東海大学(神奈川県):65.0
- 東京女子医科大学(東京都):65.0
- 獨協医科大学(栃木県):65.0
- 川崎医科大学(岡山県):65.0
※上記の偏差値は、複数の大手予備校が公表している2025年度入試向けの予想偏差値を参考に作成した目安です。模試によって判定基準は異なるため、あくまで参考としてご活用ください。
駿台・河合塾の最新偏差値データに基づく評価
「駿台と河合塾で偏差値が違うけど、どっちを信じればいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
これは、模試を受ける受験者層が異なるためです。一般的に、駿台の模試は医学部や難関大学を目指す上位層が多く受けるため、偏差値が低めに出る傾向があります。一方、河合塾の模試は受験者層が幅広いため、偏差値は高めに出る傾向があります。
重要なのは、自分が継続的に受けている模試の偏差値を基準に考えることです。A判定やB判定が出ている大学であれば、合格の可能性は十分にあると判断できます。複数の予備校のランキングを参考にしつつ、自分の模試成績を基に総合的に評価しましょう。
偏差値以外の志望校選びの重要比較ポイント

偏差値は重要な指標ですが、それだけで志望校を決めると入学後に後悔する可能性があります。あなたにとって本当に良い大学を選ぶためには、以下の4つのポイントも必ず比較検討しましょう。
6年間の総額学費ランキング
私立医学部の学費は大学によって大きく異なり、6年間で2,000万円台から5,000万円近くまで幅があります。家計への負担を考慮し、無理なく通える大学を選ぶことは非常に重要です。
- 学費が比較的安い大学
- 学費が比較的高額な大学
(参考:各大学公式サイト 2024年度情報)
医師国家試験合格率の比較
医師になるためには、大学卒業後に医師国家試験に合格する必要があります。この合格率の高さは、大学の教育の質やサポート体制を測る一つの指標となります。
注目すべきは以下の2つの数値です。
- 【新卒合格率】
その年に卒業した学生の合格率。大学の教育がストレートに反映されやすい指標です。 - 【全体合格率】
新卒者と既卒者(浪人)を合わせた合格率。既卒者へのサポート体制も垣間見えます。
一般的に新卒合格率は95%前後、全体でも90%前後が高い水準とされています。各大学の公式サイトや医学部専門予備校のサイトで最新の合格率を確認しましょう。(参考:厚生労働省 第118回医師国家試験の学校別合格者状況)
キャンパスの立地とアクセス
6年間という長い時間を過ごすキャンパスの環境も、学生生活の質を大きく左右します。
都心か地方か
都心部はアクセスが良く、アルバイトや情報収集に便利ですが、家賃などの生活費は高くなります。地方は落ち着いた環境で勉強に集中でき、地域医療に触れる機会も多いでしょう。
キャンパスの移動
低学年と高学年でキャンパスが異なる大学もあります。6年間同じキャンパスで学べるか、途中で引っ越しが必要になるかは事前に確認しておきましょう。
附属病院の場所
臨床実習で通うことになる附属病院がキャンパスから離れている場合もあります。通学の負担も考慮に入れておくと安心です。
留年率の低さと進級のしやすさ
意外と見落としがちですが、「留年率の低さ」も重要なチェックポイントです。留年は1年分の学費が余計にかかるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。
大学によっては進級判定が厳しく、留年率が高いところもあります。公にデータが発表されることは少ないですが、医学部専門予備校が開催する説明会や、在学生・卒業生の口コミサイトなどで情報を集めるのがおすすめです。進級サポートや再試験制度が整っている大学は、学生にとって心強いと言えるでしょう。
後悔しない医学部志望校の決め方4ステップ
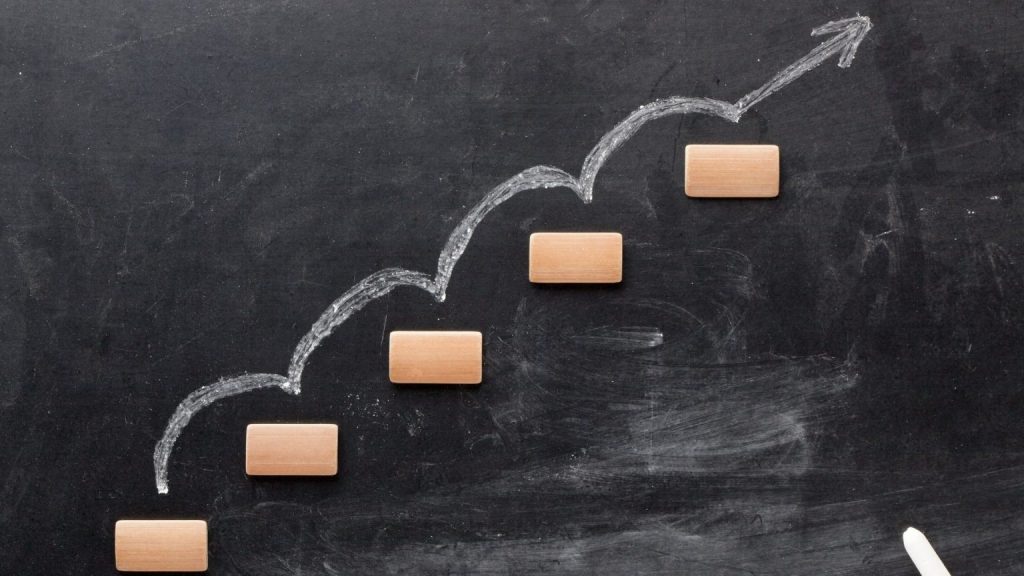
ここまでの情報を踏まえ、具体的に志望校を決定していくための4つのステップをご紹介します。この手順に沿って考えれば、冷静かつ戦略的に志望校を絞り込めます。
STEP1. 模試の成績から自分の学力を客観視する
まずは最新の模試の結果を冷静に分析し、自分の現在の学力レベルを正確に把握しましょう。
- 【ドッキング判定を確認する】
共通テスト模試と大学別模試の結果を総合した「ドッキング判定」は、より本番に近い合格可能性を示します。 - 【偏差値の推移を見る】
一時的な結果に一喜一憂せず、複数回の模試結果から平均的な偏差値や成績の推移を把握します。 - 【科目別の得意・不得意を分析する】
どの科目で点が取れていて、どこが課題なのかを明確にすることで、相性の良い大学が見えてきます。
STEP2. 偏差値と学費から志望校候補を絞り込む
次に、STEP1で把握した学力と、家庭の経済状況を基に、受験する可能性のある大学をリストアップします。
- 【偏差値の範囲を設定する】
自分の偏差値±2.5〜5.0程度の範囲で、ランキング表から候補となる大学を複数選び出します。 - 【学費の上限を決める】
保護者の方と相談し、支払いが可能な学費の上限を決めます。その範囲を超える大学は、奨学金制度の利用を検討するか、候補から外します。
この段階で、現実的に受験可能な大学が10〜15校程度に絞られるのが理想です。
STEP3. 入試科目と出題傾向の相性を確認する
リストアップした大学の入試科目、配点、出題傾向を調べ、自分との相性を確認します。
- 【入試科目の確認】
英語、数学(数Ⅲまで)、理科2科目が基本ですが、大学によっては理科1科目で受験できる場合や、小論文・面接の配点が高い場合があります。 - 【配点の確認】
得意科目の配点が高い大学は、他の受験生より有利になる可能性があります。 - 【過去問の分析】
実際に過去問を数年分解いてみましょう。「基礎的な問題が多い」「思考力を問う難問が多い」「時間的に厳しい」など、大学ごとの個性が分かります。自分が高得点を狙いやすいと感じる大学は、相性が良いと言えます。
STEP4. 挑戦校・実力相応校・安全校を組み合わせる
最後に、絞り込んだ候補の中から、出願する大学をバランス良く組み合わせていきます。これが「併願戦略」です。
挑戦校
合格可能性は低い(C判定以下)が、どうしても行きたい憧れの大学。合格すれば大成功です。1〜2校に絞りましょう。
実力相応校
自分の学力に最も合っている(A〜B判定)大学。ここが合格のメインとなる本命校です。2〜3校選ぶのが一般的です。
安全校
合格可能性が非常に高い(A判定以上)大学。いわゆる「滑り止め」ですが、必ず進学する可能性を考えて選ぶことが重要です。1〜2校確保しておくと精神的に安定します。
この組み合わせで合計5〜7校程度に出願する受験生が多いです。入試日程が重ならないように注意して、最終的な出願プランを完成させましょう。
「入りやすい」「狙い目」の私立医学部

「少しでも合格可能性が高い大学を知りたい」と考えるのは当然のことです。ここでは「入りやすい」「狙い目」と言われる大学のパターンを3つご紹介します。
偏差値が比較的低い大学の特徴
偏差値ランキングで下位に位置する大学は、相対的に見て合格ラインが低いと言えます。具体的には、偏差値65.0前後の大学群がこれに該当します。
ただし、注意点として、医学部である以上、どの大学も最難関であることに変わりはありません。「入りやすい」という言葉に惑わされず、十分な対策が必要です。また、新設の医学部や地方の大学は、都市部の伝統校に比べて偏差値が低めに出る傾向があります。
入試科目数が少ない大学
特定の科目が非常に得意な受験生にとっては、入試科目数が少ない大学は大きなチャンスになります。
例えば、帝京大学の医学部は、英語、数学、国語、物理、化学、生物の中から3科目を選択して受験できます。理科が1科目で済むため、理科2科目の対策が間に合わない受験生や、国語が得意な受験生にとっては狙い目と言えるでしょう。
地域枠や推薦入試の活用
一般選抜だけでなく、多様な入試方式に目を向けることも重要です。
地域枠
「地域枠」とは、卒業後に特定の地域(都道府県)で一定期間勤務することを条件に、奨学金が貸与されたり、一般枠より低い偏差値で合格できたりする制度です。その地域の医療に貢献したいという強い意志があるなら、非常に魅力的な選択肢です。
推薦入試・AO入試
評定平均や課外活動の実績に自信がある場合は、推薦入試やAO入試(総合型選抜)も検討しましょう。一般選抜とは異なる評価軸で選考されるため、思わぬチャンスが生まれることがあります。
国公立大学医学部との比較
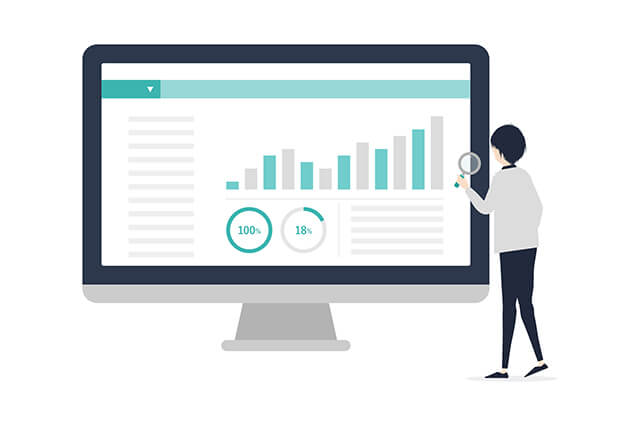
私立医学部を第一志望に考えている方も、国公立大学との違いを理解しておくことで、より納得感のある志望校選びができます。
国公立大学医学部の偏差値一覧
国公立大学医学部は、私立大学よりもさらに狭き門です。参考までに、トップレベルの大学の偏差値を見てみましょう。
- 東京大学(理科三類): 72.5以上
- 京都大学: 72.5
- 大阪大学: 70.0
- 東京医科歯科大学: 70.0
- 九州大学: 67.5
- 千葉大学: 67.5
- 神戸大学: 67.5
地方の国公立大学でも、偏差値65.0を下回ることはほとんどありません。
学費と入試難易度の違い
国公立と私立の最も大きな違いは、学費と入試科目です。
学費
国公立大学の学費は、どの大学でも6年間の総額が約350万円と、私立大学に比べて圧倒的に安価です。
入試難易度・科目
国公立大学は、大学入学共通テストで5教科7科目(またはそれ以上)が課されるのが一般的です。科目数が多く、総合的な学力が求められるため、私立大学専願の受験生とは対策が大きく異なります。
医学部の志望校選びに関するQ&A

最後に、医学部の志望校選びでよく寄せられる質問にお答えします。
学費が安い私立医学部はどこですか?
A. 国際医療福祉大学(約1,910万円)、順天堂大学(約2,080万円)、慶應義塾大学(約2,200万円)などが代表的です。 これらの大学は学費の安さから人気が高く、偏差値も最難関レベルとなっています。
再受験に寛容・有利な大学はありますか?
A. 「この大学なら再受験生が有利」と断言できる大学はありません。 しかし、大学によっては入学者の年齢構成などを公表しており、多浪生や社会人経験者が比較的多く在籍している大学もあります。年齢や経歴で不利になることは少なくなってきていますが、面接では**「なぜ再び医師を目指すのか」**を明確に説明できる準備が不可欠です。
面接・小論文の重要度はどのくらいですか?
A. 非常に重要です。大学によっては学科試験と同じくらい配点が高い場合もあります。 医師としての適性やコミュニケーション能力、倫理観などを評価するために実施されます。学科試験の点数がボーダーライン上にいる場合、面接や小論文の結果が合否を分けることも少なくありません。専門予備校などで十分な対策をしておきましょう。
志望校は「どこでもいい」は通用しますか?
A. 「どこでもいいから医学部に入りたい」という考えはおすすめできません。 医師になれればどこでも同じ、と考えるかもしれませんが、大学の校風、カリキュラム、研究分野、関連病院などは、あなたの将来のキャリアパスに大きな影響を与えます。6年間通うのはあなた自身です。 大変な受験勉強のモチベーションを保つためにも、「この大学で学びたい」という主体的な目標を持つことが、合格への一番の近道です。
まとめ
後悔しない医学部志望校選びのためには、偏差値という一つの軸だけでなく、多角的な視点から大学を比較検討することが不可欠です。
この記事で解説したポイントを、最後にもう一度確認しましょう。
医学部受験は長く険しい道のりですが、明確な目標があれば必ず乗り越えられます。この記事が、あなたの志望校選びの一助となり、夢への第一歩を力強く踏み出すきっかけになれば幸いです。頑張ってください!