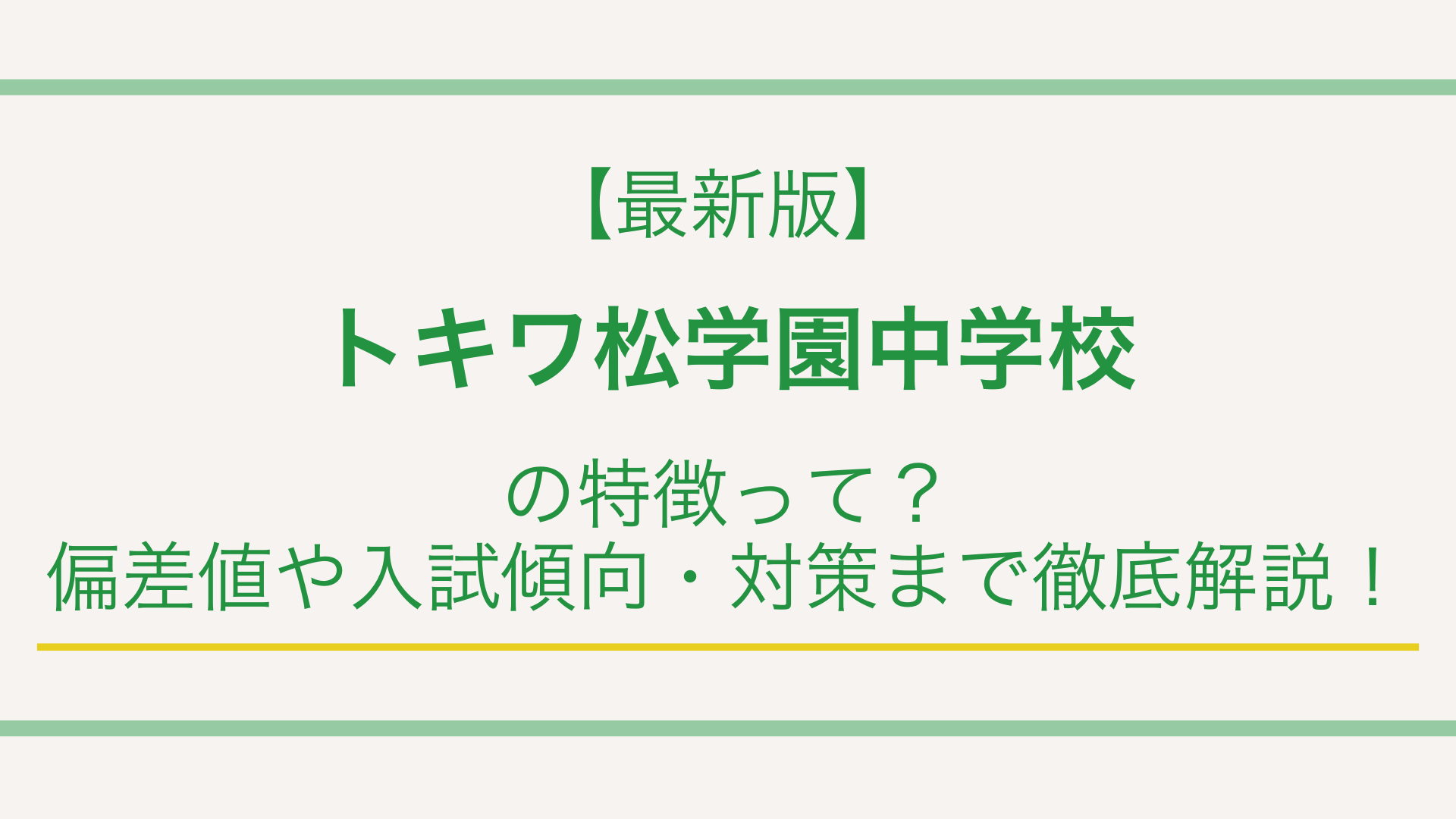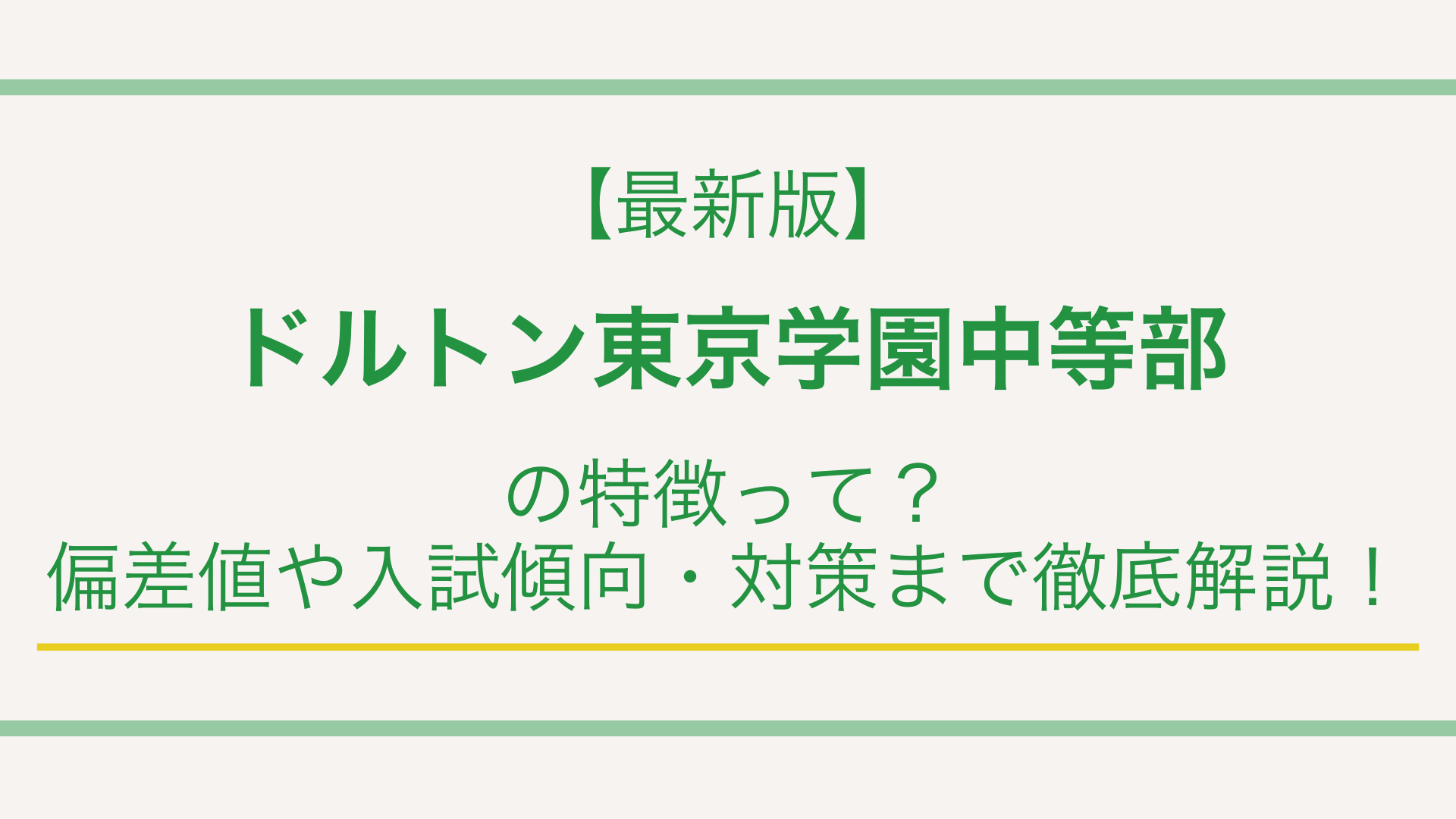医学部受験は他の学部に比べ、長期間にわたる計画的な学習が求められます。「どれくらい勉強すればよいのか」「いつから何を始めるべきか」といった疑問を抱く受験生や保護者は少なくありません。
合格に必要な勉強時間は一概には言えませんが、多くの予備校では目安として約5000時間を提示しています。本記事では、この時間配分の考え方と、学年別の1日のスケジュール例を示しながら、戦略的に学習を進める方法を解説します。
医学部受験に必要な勉強時間|合格に必要な5000時間とは?
医学部受験では「合計5000時間の勉強が必要」とよく言われます。これは、医学部が他学部と比べて圧倒的に難易度が高く、英語・数学・理科2科目・国語・社会など多くの科目で高得点が求められるためです。実際に合格者の多くが高校3年間で日々長時間の勉強を積み重ねており、週20~40時間、年間1000~2000時間を継続しています。他学部では2000~3000時間程度で合格するケースもありますが、医学部は受験科目数の多さ、問題の難度、競争率の高さから、より多くの勉強時間が必要となります。
例えば高1から3年間で5000時間を確保するには、年間約1666時間、週32時間、平日4時間+休日6時間程度が目安です。まずは「このくらい必要なのか」と現実的に受け止め、日々の積み重ねを意識しましょう。ただし、大切なのは時間の長さだけでなく、いかに集中して質の高い学習を積み重ねるかです。
次章からは、高校1年生から浪人生まで各段階の具体的な勉強戦略とスケジュールの立て方を紹介します。
医学部合格に必要な勉強時間の根拠や、国公立と私立の違いによる学習戦略を詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
高校1年生の勉強戦略とスケジュール例

高校1年生では、学習習慣づくりと生活リズムの安定が最優先です。このセクションでは、部活や学校と両立しながら、無理なく医学部受験の勉強を継続できるスケジュールの立て方を具体的に紹介していきます。
スケジュールの立て方のコツ(高校1年生)
高校1年生は、まず「学習習慣をつけること」が最優先です。学校や部活動と両立するため、平日は1~2時間、休日は3~4時間の勉強を目標に、無理のない計画を立てましょう。週単位でリズムを作ることが継続のカギです。例えば平日は宿題や予習・復習、週末は苦手分野の克服など、曜日ごとに目的を持たせるとメリハリがつきます。Studyplusなどのアプリや手帳で学習記録をつけると、進捗が「見える化」され、モチベーション維持にも役立ちます。
1日の勉強スケジュール例(高校1年生)
高校1年生の最優先事項は、部活動や新しい学校生活と両立しながら「学習習慣」を確立することです。ここでは、無理なく勉強を継続できる現実的なモデルとして、平日は帰宅後に2時間、休日は4.5時間の学習時間を確保するスケジュールを紹介します。通学などのスキマ時間も有効活用し、まずは「毎日机に向かう」リズムを作りましょう。
高校1年生の勉強スケジュール例
■ 平日(勉強時間:約2時間)
| 時間 | 内容 |
| 7:00-7:30 | 起床・朝食 |
| 7:30-8:00 | 通学(英単語など) |
| 8:30-16:00 | 学校の授業 |
| 16:00-18:30 | 部活動 |
| 18:30-19:30 | 帰宅・休憩 |
| 19:30-20:30 | 夕食・休憩 |
| 20:30-21:30 | 勉強①(数学の予習・復習) |
| 21:30-22:30 | 勉強②(英語の予習・復習) |
| 22:30-23:00 | 自由時間・就寝準備 |
| 23:00- | 就寝 |
■ 休日(勉強時間:合計4.5時間)
| 時間 | 内容 |
| 8:00-9:00 | 起床・朝食 |
| 9:00-11:00 | 勉強①(数学の演習・苦手分野) |
| 11:00-13:00 | 自由時間・昼食 |
| 13:00-15:00 | 勉強②(英語長文など) |
| 15:00-19:30 | 自由時間(部活、趣味、外出など) |
| 19:30-20:30 | 夕食・休憩 |
| 20:30-21:00 | 勉強③(理科・社会の復習など) |
| 21:00-22:30 | 自由時間(趣味、リラックス、入浴など) |
| 22:30-23:00 | 就寝準備 |
| 23:00- | 就寝 |
※本記事で紹介するスケジュールはすべてモデルケースです。体力・部活動・通学時間など個人の事情に合わせ、学習時間や順序を調整してください。
年間スケジュールの立て方と学習目標(高校1年生)
高校1年生の1年間では、「英語・数学の基礎力定着」「模試の受験経験」「苦手分野の把握」を大きな目標にしましょう。春・夏・冬の長期休みごと、定期テストごとに中期的な目標を立て、進捗を確認します。模試は結果に一喜一憂するのではなく、弱点発見や学習計画の見直しのための貴重な機会と捉えましょう。こうした一つ一つの積み重ねが、高2以降の学習基盤を築きます。
高1から医学部受験を始める意義や具体的な勉強法をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
高校2年生の勉強戦略とスケジュール例
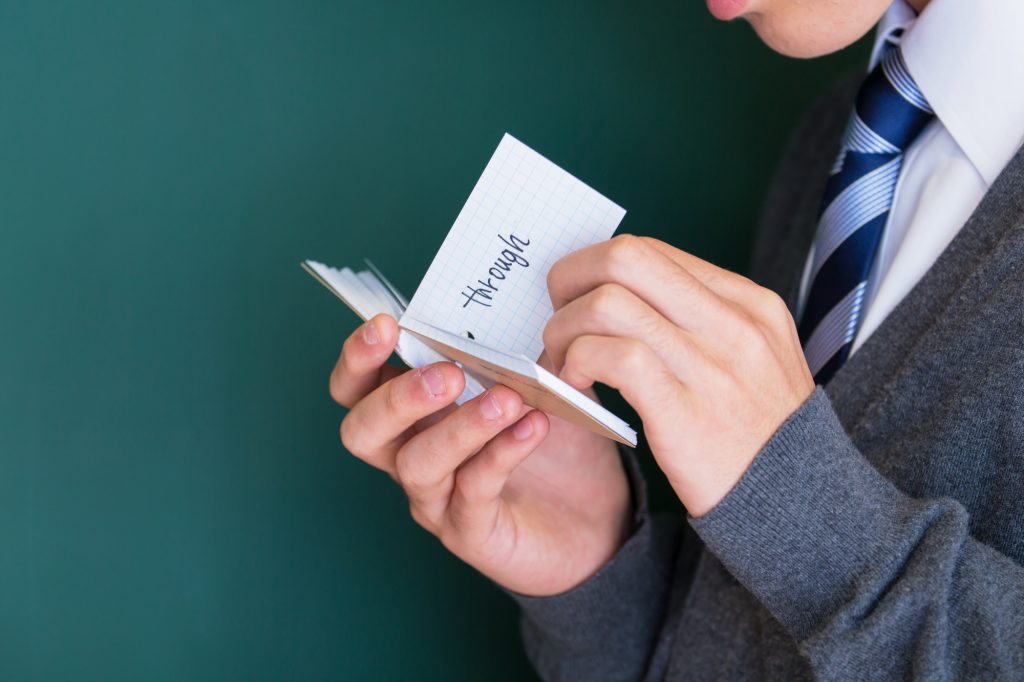
高校2年生は、基礎から応用へとステップアップする受験準備期です。このパートでは、医学部受験における理社の本格対策や模試結果を活かした戦略的なスケジュール設計の方法を解説していきます。
スケジュールの立て方のコツ(高校2年生)
高校2年生は受験準備の本格スタート期です。平日は3~4時間、休日は6~7時間を目安に勉強時間を確保し、学習の絶対量を増やしていきましょう。理科や社会の選択科目は早めに決めて基礎学習を始めると、高3での負担が大きく減ります。模試の結果や志望校の出題傾向をもとに計画を見直す習慣をつけ、受験本番に向けた土台をしっかり作りましょう。
1日の勉強スケジュール例(高校2年生)
高校2年生は、いよいよ受験勉強が本格化する大切な時期です。基礎固めに加え、応用問題や理科・社会にも着手し、学習の絶対量を増やしていきましょう。ここでは、平日は「朝学習」と「夜のまとまった学習」を組み合わせて3.5時間、休日は集中力を維持しながら合計7時間の学習時間を確保するスケジュールを提案します。
高校2年生の勉強スケジュール例
■ 平日(勉強時間:合計3.5時間)
| 時間 | 内容 |
| 6:30-7:00 | 起床・朝学習(英単語・計算など) |
| 7:00-8:00 | 朝食・準備・通学 |
| 8:30-16:00 | 学校の授業 |
| 16:00-18:30 | 部活動 |
| 18:30-19:30 | 帰宅 |
| 19:30-20:30 | 夕食・休憩 |
| 20:30-22:00 | 勉強①(数学・物理など集中力が必要な科目) |
| 22:00-22:30 | 入浴・休憩 |
| 22:30-23:30 | 勉強②(英語・理科暗記など) |
| 23:30- | 就寝(睡眠7時間確保) |
■ 休日(勉強時間:合計7時間)
| 時間 | 内容 |
| 8:00-9:00 | 起床・朝食 |
| 9:00-12:00 | 勉強①(英語・数学の演習) (※1時間ごとに休憩) |
| 12:00-13:30 | 昼食・休憩 |
| 13:30-16:30 | 勉強②(理科・社会の基礎固め) (※1時間ごとに休憩) |
| 16:30-19:00 | 自由時間・休憩(運動、趣味など) |
| 19:00-20:00 | 夕食 |
| 20:00-21:00 | 勉強③(その日の復習、課題など) |
| 21:00-22:30 | 自由時間(趣味、リラックス、入浴など) |
| 22:30-23:00 | 就寝準備 |
| 23:00- | 就寝 |
年間スケジュールの立て方と学習目標(高校2年生)
年間を通した戦略が重要になります。春から夏は英語・数学の基礎を完成させ、理科や社会の基礎に着手します。秋から冬にかけては応用問題や模試に本格的に取り組み、実力を試す時期です。「夏までに理社スタート」「冬の模試でB判定」など具体的な目標を立てると、学習を進めやすくなります。志望校の情報収集も始め、高3に向けて計画の下地を整えましょう。
高2からでも間に合う戦略や、逆転合格を狙うための勉強法を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
高校3年生の勉強戦略とスケジュール例

高校3年生は、医学部受験本番に向けた最も重要な1年です。この章では、過去問演習・志望校別対策を含む、1日間・1週間・1年間それぞれの勉強スケジュールの立て方や管理の工夫を紹介していきます。
スケジュールの立て方のコツ(高校3年生)
高校3年生の学習計画は、過去問演習が中心となります。スケジュールは日ごと・週ごとに目的を明確にし、模試や出願日といったイベントから逆算して組み立てましょう。苦手科目には意識的に時間を多く割き、面接や小論文、共通テスト対策といった多様なタスクもバランスよく管理します。計画は状況に応じて柔軟に見直し、最後まで集中力を維持するためにも、体調やメンタル管理を最優先しましょう。
1日の勉強スケジュール例(高校3年生)
いよいよ受験本番を迎える高校3年生は、1分1秒が合否を左右します。部活動も引退し、可処分時間をいかに志望校対策に充てるかが鍵です。ここでは「平日(学校あり)」と「休日(学校なし)」の2つのシーンに分けて、学習スタイル(自宅中心か、塾を活用するか)に応じたスケジュール例を紹介します。自分の学習スタイルに合わせて、最適な計画を立てましょう。
■ 平日(学校あり)
| 時間帯 | 自宅学習型 | 塾中心型 |
| 16:00-17:00 | 帰宅・休憩 | 部活/移動 |
| 17:00-19:00 | 勉強①(理科・社会など) | 塾で学習 |
| 19:00-20:00 | 夕食・休憩 | 帰宅・夕食 |
| 20:00-22:30 | 勉強②(英数・過去問演習) | 勉強(塾の復習・課題) |
| 22:30-23:30 | 入浴・復習・就寝準備 | 入浴・復習・就寝準備 |
| 23:30- | 就寝 | 就寝 |
■ 休日(学校なし)
| 時間帯 | 内容 |
| 8:00-9:00 | 起床・朝食 |
| 9:00-12:00 | 午前の勉強(英語・数学など思考系科目) (※1時間ごとに休憩) |
| 12:00-13:00 | 昼食・休憩 |
| 13:00-16:00 | 午後の勉強(理科・社会・過去問演習) (※1時間ごとに休憩) |
| 16:00-18:00 | 自由時間・軽運動・休憩 |
| 18:00-19:00 | 夕食 |
| 19:00-21:30 | 夜の勉強(復習・弱点補強・暗記) |
| 21:30-22:30 | 自由時間(趣味、リラックス、入浴など) |
| 22:30-23:00 | 就寝準備 |
| 23:00- | 就寝 |
年間スケジュールの立て方と学習目標(高校3年生)
4~6月は基礎の総復習と完成、7~9月は応用力強化と過去問への着手、10~12月は志望校別の本格演習、1月以降は最終調整と、時期ごとに目標を区切るのが効果的です。模試や出願日などのイベントをマイルストーンとして設定し、進捗を記録・振り返る時間を必ずスケジュールに組み込みます。心身のコンディション維持も年間計画に含め、最後まで走り抜きましょう。
高3生に特化した年間スケジュールや一日の勉強モデルをさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
浪人生の勉強戦略とスケジュール例

浪人生にとっては、自由な時間をいかに有効活用できるかが合否を左右します。この章では、現役時代の反省を活かした計画づくりや、1日・1週間・1年単位でのスケジュールの立て方を具体的に紹介していきます。
スケジュールの立て方のコツ(浪人生)
浪人生は、まず現役時代の反省点を振り返り、得意・苦手を明確にすることから始めます。学校の拘束がないため、生活リズムを一定に保ち、起床・就寝時間を固定することが極めて重要です。午前は基礎や暗記、午後は演習、夜は復習など、時間帯ごとに学習内容を分けると効率が上がります。無理なく継続するために、こまめな休憩や軽い運動も計画的に取り入れましょう。
1日の勉強スケジュール例(浪人生)
浪人生にとって、合否を分ける最大の要因は「自己管理能力」と「確立された生活リズム」です。自由な時間を最大限に活用し、1年間コンスタントに走り抜くための計画が欠かせません。ここでは、典型的な2つのスタイルである「予備校通学型」と「自宅浪人型」のスケジュールを提案します。どちらも1日10時間前後の学習時間を確保しつつ、心身の健康を維持するためのモデルです。
浪人生の勉強スケジュール例
| 時間帯 | 予備校通学型 | 自宅浪人型 |
| 6:30-7:30 | 起床・朝食・準備 | 起床・朝食・準備 |
| 7:30-9:00 | 通学・移動(暗記など) | 勉強①(英語) |
| 9:00-12:00 | 予備校(講義・自習) | 勉強②(数学) |
| 12:00-13:00 | 昼食・休憩 | 昼食・休憩 |
| 13:00-17:00 | 予備校(講義・自習) | 勉強③(理科・社会) |
| 17:00-18:30 | 帰宅・休憩 | 休憩・軽い運動 |
| 18:30-19:30 | 夕食 | 夕食 |
| 19:30-22:00 | 自宅学習(復習・暗記) | 勉強④(復習・弱点補強) |
| 22:00-23:00 | 入浴・就寝準備 | 入浴・就寝準備 |
| 23:00- | 就寝 | 就寝 |
計画通りにいかないときの対処法と外部サポートの活用法
医学部受験は計画を立てることが大切ですが、思うように進まなかったり、途中で挫折しそうになったりすることも少なくありません。
この章では、計画の見直し方や、必要に応じた外部サポート(家庭教師や予備校など)の活用方法について紹介します。自分だけで抱え込まず、柔軟に対処していくことが成功への近道です。
計画倒れを防ぐ「逆算思考」と見直しの実践ポイント
スケジュール設計の基本は「逆算思考」です。まず入試本番というゴールを設定し、そこから逆算して月単位・週単位の目標を立てましょう。計画は「立てっぱなし」にせず、定期テストや模試を進捗確認の機会として活用し、ズレが生じた場合は優先順位を見直したり学習時間を再配分したりして調整します。アプリや手帳で進捗管理を行い、週1回の振り返りタイムを習慣にするのも効果的です。計画通りにいかない時も焦らず、状況に合わせて修正しながら前進しましょう。
必要に応じた家庭教師・医学部予備校の取り入れ方
医学部受験では、スケジュール管理や苦手克服のために外部サポートを活用するのが有効です。
特に高2秋から高3春にかけては、「対策の優先順位が分からない」「自学だけでは不安」などの悩みが増える時期であり、サポートを検討する目安となります。
医学部予備校は戦略的なカリキュラムや最新情報の豊富さが強みで、家庭教師は柔軟な個別対応や苦手分野の徹底指導に優れています。すべてを外部に任せるのではなく、「全体の管理は予備校、苦手科目は家庭教師」といったハイブリッド活用もおすすめです。費用面も考慮し、必要な時期や科目に絞って段階的に利用することで、無駄なく効果的に学習を進められます。自分の状況に合わせて外部サポートを戦略的に取り入れましょう。
まとめ
医学部受験は長期戦であり、学年ごとの学習戦略とスケジュール管理が合格のカギとなります。各学年で「何をすべきか」「どう過ごすか」を押さえ、全体の流れを意識して計画を立てましょう。スケジュールは「立てて終わり」ではなく、見直し・調整を繰り返すことで、より実践的で効果的な計画になります。必要に応じて予備校や家庭教師の活用も検討し、柔軟な姿勢で受験に臨むことが成功への近道です。




-1-1.jpg)

-320x180.jpg)
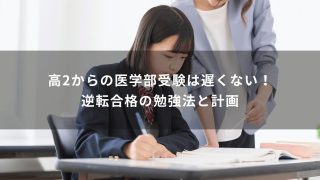
-320x180.jpg)