医学部受験は全国的に高倍率・高偏差値の狭き門とされていますが、実は“穴場”と呼ばれる大学も存在します。偏差値や倍率が比較的低かったり、地域枠や推薦枠が活用しやすかったり、条件次第では合格のチャンスを広げられるケースもあるのです。
本記事では、国公立・私立を問わず、受験生にとって狙いやすい“穴場”医学部を最新データをもとに一覧化し、選び方や注意点、戦略まで網羅的に解説します。
国公立医学部で“穴場”の大学一覧【最新】
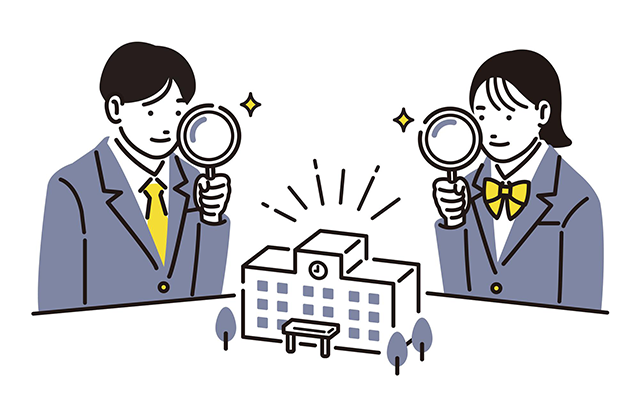
国公立医学部の中にも、偏差値や倍率が比較的低く、地域枠や教育体制などの理由で“穴場”とされる大学があります。ここでは、最新情報をもとに具体的な大学名とその特徴を紹介し、狙い目となる国公立医学部を明らかにしていきます。
偏差値・倍率ともに低めの国公立医学部
“穴場”と聞いて思い浮かぶのは、偏差値や入試倍率が全体的に低い大学でしょう。高偏差値の受験生からの人気が集中しにくい大学ともいえます。こうした国公立医学部は地方に立地し、各地域の医療人材育成に特化した大学が多く見られます。代表的な例としては、旭川医科大学や秋田大学、山形大学、島根大学、琉球大学などが挙げられます。これらの大学は首都圏や大都市圏に比べて受験者がやや分散しやすく、偏差値が全国平均より若干低めに設定されている傾向があります。また、北海道・東北地方や、中国・四国・九州・沖縄地方といったエリアの国公立医学部も、倍率が5〜7倍程度と都市部のトップ校に比べて落ち着いている場合が多いです。なお、年度による倍率の変動もあるため、近年の入試要項を必ず確認しましょう。
地域枠や推薦枠を活用しやすい国公立医学部
地域枠・推薦枠は、地域医療に貢献できる志願者を優先的に受け入れる制度であり、一般枠より競争率が低くなる傾向があります。
たとえば、信州大学は「長野県地元出身者枠(13名)」と「全国募集地域枠(7名)」を設けており、どちらも選抜方法は書類・共通テスト・面接です。また、旭川医科大学では総合型選抜(北海道特別選抜)や学校推薦型選抜(地域枠)などで合わせて25名以上の枠があり、島根大学や香川大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学などの地方国公立でも、地域枠や推薦枠の定員が10名以上と比較的手厚く用意されています。出願には指定県出身などの居住要件、成績評定平均、卒後の地域医療従事義務などが課されることが多いので、志望を検討する際には各大学の入試要項や、ホームページの発表を確認してください。
地方立地だが教育体制や就職支援が充実している国公立医学部
地方に位置している大学が必ずしも悪い大学とは勿論限りません。地域医療が学べる点はもちろん、大学独自の教育体制や就職支援が充実している医学部はあります。代表例には、信州大学、香川大学、長崎大学、鹿児島大学、熊本大学などがあります。これらの大学では、地域の医師を招いた専門的な実習体制を売りにしている、基礎医学と臨床医学を融合させたカリキュラムを敷いている、AIを用いた医療教育など、独自色をもった教育が学べることが特徴です。また、多くの地方医学部は附属病院を中心とした地域密着型の医療ネットワークを有しているため、卒業後も地域での就職先が確保されやすい特徴があります。さらに、自治体や大学による奨学金制度やキャリア支援部門の設置により、進路相談・専門研修・地域医療従事支援に関するサポートが手厚いです。就職率や医師国家試験合格率も高く、安心してキャリア形成ができる環境といえるでしょう。
私立医学部で“穴場”の大学一覧【最新】
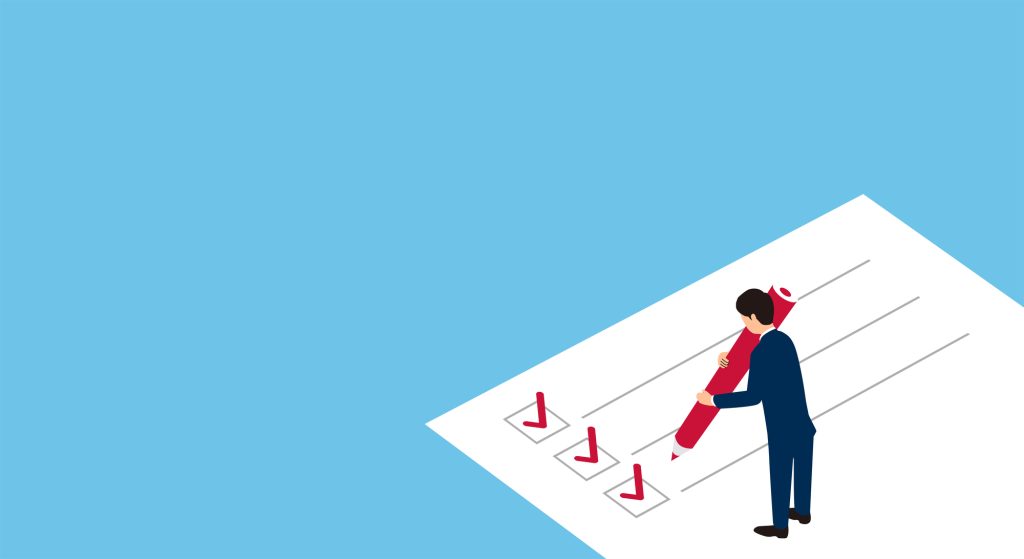
私立医学部は学費が高く難関という印象がありますが、大学によっては偏差値や倍率が抑えめで、特待制度や立地の影響から“穴場”とされることもあります。ここでは、私立医学部の中でも比較的受験しやすい大学を具体的に紹介します。
合格者の偏差値が比較的低めの私立医学部
私立医学部の中でも偏差値が比較的低めに設定されている大学は、全国的にみると地方に多く存在します。各種予備校が発表している2025年度入試向けの偏差値予測などによると、偏差値が60台前半から中盤に位置する医学部として、川崎医科大学(偏差値61〜62)、金沢医科大学(偏差値61〜62)、聖マリアンナ医科大学(偏差値62〜63)、獨協医科大学(偏差値62台)、埼玉医科大学(偏差値62〜63)、岩手医科大学(偏差値62〜64)などが挙げられます。これらの大学は、首都圏トップ校と比べると合格に必要な学力レベルがやや低めに設定されているため、「医学部に何としても進学したい」という受験生にとって現実的な選択肢です。偏差値が低めとはいえ、募集定員や立地、受験科目などでさらに入りやすさに差が出るため、最新の募集要項や入試結果も必ず確認することが重要です。
学費が比較的安い or 特待制度が充実している私立医学部
私立医学部は全般的に学費が高額ですが、そのなかで学費が抑えられている大学や特待制度が手厚い大学は“穴場”となりやすい傾向があります。代表的な例として、国際医療福祉大学は学費が約1,860万円と私立医学部の中では安価な設定です。また、順天堂大学や日本医科大学も私立の中で比較的学費が抑えられるでしょう。さらに、藤田医科大学や兵庫医科大学、近畿大学など、多くの私立医学部で成績優秀者向けの特待生制度を設けており、入試成績や学業維持によって最大で学費全額免除となるケースも見られます。これらの制度は経済的負担を大きく軽減し、同時に応募者層がある程度限られることで競争率が下がりやすいのが特徴です。受験対策とあわせて、応募条件・継続要件の詳細をよく調べることが重要です。
地方立地で受験者数が少なめの私立医学部
首都圏から遠い地方の私立医学部は、交通アクセスや生活環境の違いから首都圏受験生に敬遠されがちで、結果として競争率が比較的抑えられています。具体的には、川崎医科大学(岡山県)、金沢医科大学(石川県)、岩手医科大学(岩手県)、福岡大学医学部(福岡県)などが該当します。これらの大学は地元出身者や地域志向型の学生が多い一方、試験当日の移動や、その後の生活への不安などのハードルから、都市部と比べて受験者数が伸びにくい傾向が見られることが一般的です。また、医療需要の高い地方自治体との連携により、地域枠や奨学金制度を採用しているケースもあり、志願者層がさらに限定される要因となっています。都市部での激戦を避けたい場合、こうした地方私立医学部を志望校リストに加えることは合格への有効な戦略となります。
入りやすい医学部の特徴とは?“穴場”の判断基準を整理

偏差値や倍率だけでなく、入試科目・地域枠の有無・学費・立地など“穴場”とされる医学部には共通の特徴があります。ここでは、そうした判断基準を整理し、読者自身が自分に合った穴場大学を見つける参考になるよう、わかりやすく解説します。
偏差値が比較的低めである
他の学部と同じように、医学部でも模試等で出される偏差値が相対的に低い大学は、他校に比べて入学のハードルが下がるため、“穴場”とされます。これまで述べてきたような理由のとおり、こうした大学は多くの場合、地方立地や学費の高さといった理由で受験生の人気が集中しにくく、競争率が上がりづらい傾向があります。自身の学力レベルが首都圏の大学の受験に自信がない場合など、現実的に合格を狙いやすい条件となり、受験戦略の幅が広がるのが大きなメリットといえるでしょう。
倍率が安定して低い・下がってきている
医学部の中には、定員数の充実や志願者の分散化などを背景に、近年倍率が安定的に低く推移している大学も多いです。大学や入試方式にもよりますが、少子化などの影響で、一部の大学では以前より倍率が落ち着く傾向が見られます。 例えば大分大学や福島県立医科大学は、倍率2~3倍台と全国平均を下回る年度もあるほどです。こうした大学では、入学希望者が限定されやすく、毎年安定して受験者数が抑えられることで“穴場校”として注目されています。
地域枠・推薦枠が多く設けられている
地域枠や推薦枠は、地域医療人材の確保を目的として設置された特別枠であり、一般枠よりも倍率が低い場合が多いのが特徴です。定員の多さや地元出身者優遇など要件が明確なため、条件に該当すれば競争が限定的になり、合格チャンスが高まります。医療従事義務や違反した場合のペナルティなどのリスクはあるものの、推薦や地域貢献志向の受験生にとっては極めて有利な制度です。
試験科目や難易度が他大学と比べて易しい
金沢医科大学などの一部の医学部では試験科目数が少なく、あるいは問題の難易度自体が他大学より控えめな傾向があります。こうした大学は、特定科目の得意分野に絞って対策したい受験生や、学力全般に不安がある人に適しています。効率的な受験準備ができ、多浪・再受験組など幅広い層にとってチャンスが広がる点が強みです。
学費・立地など他の要因で敬遠されやすい
学費が高額な私立医学部や、地方などアクセスが不便な大学は、経済的・地理的要因から受験生が敬遠しやすく、結果的に競争率や偏差値が低めに推移します。たとえば川崎医科大学や福岡大学医学部は学費が高いことで有名です。地方私立や新設校の多くは、受験地域を問わず受験生にとって現実的な穴場になりやすいのが特徴です。
医学部の穴場を狙うための受験戦略

“穴場”医学部を確実に狙うには、志望校の特性に合わせた戦略的な受験プランが不可欠です。ここでは、国公立と私立の併願方法、地域枠や推薦枠の活用法、効果的な学習環境の整え方など、実践的な戦略を具体的に紹介します。
国公立と私立の併願戦略を立てる
国公立と私立医学部を併願する際は、試験日程や入試科目の重複、出願条件に十分注意する必要があります。私立医学部は入試日が分散しているため、複数校の併願が可能ですが、試験日が重なる大学同士は同年に受験できません。また、国公立と私立で求められる科目や配点、出題方式の違いにも留意が必要です。実際には、国際医療福祉大学や順天堂大学など、試験日が他と重なりにくく国公立との併願に適した大学が存在します。併願戦略を立てる際は、スケジュール表を作り、移動や試験準備の負担も総合的に考慮しましょう。
地域枠・推薦枠の要件やスケジュールを確認する
地域枠・推薦枠を活用する場合、出願には成績証明や志望理由書、場合によっては高校長の推薦状など事前に準備すべき書類が多いことに注意が必要です。これらの枠は定員数や応募資格(出身地、在籍高校、評定平均など)が明確に定められているため、各大学の募集要項を早めに確認・準備しましょう。スケジュール管理も重要で、推薦や地域枠の出願は一般入試より早く締切られることが一般的です。エントリーや面接日程の把握、結果発表日の確認も怠らないことが合格へつながります。
塾・家庭教師で情報収集や対策のサポートを受ける
受験対策の専門家である塾・家庭教師を活用すると、最新の入試情報や大学ごとの出題傾向、併願スケジュールの調整、受験戦略の立案まできめ細かいサポートが受けられます。過去問分析や小論文・面接対策、進路相談など個別指導が可能なため、特に併願戦略や推薦枠対策など、自力では手が回りにくい情報収集と準備に大きなメリットがあります。
また、模試の実施や模擬面接、最新の合格率データの提供を通じて、効率的かつ計画的な学習を実現できるのが大きな強みです。
学研の家庭教師では、医学部受験に精通したプロ家庭教師が、最新の入試情報と豊富な指導経験に基づき、お子様だけの合格戦略を立案します。志望校選定から学習計画、面接・小論文対策まで、マンツーマンで徹底的にサポート。まずは無料の学習相談で、お気軽にお悩みをお聞かせください。
穴場医学部を選ぶ際に注意すべきポイント

“入りやすいから”という理由だけで医学部を選ぶと、入学後に想定外の苦労をするケースもあります。ここでは、教育内容や卒後の勤務義務、国家試験対策の実態など、後悔を防ぐために知っておくべき注意点を紹介します。
偏差値・倍率に偏った志望校選びのリスク
医学部選びを偏差値や倍率のみで決めてしまうと、「合格しやすいから」と入学した後に、その大学の教育方針や校風、進級制度、実習環境が自分に合っていないことに気付いて後悔するケースが少なくありません。例えば、「偏差値が低めだから負担が軽いだろう」と思っていたら実は進級条件が非常に厳しく、入学後に想像以上のプレッシャーや留年リスクに直面した、という事例がよく見られます。特に入試の偏差値は低めでも、高い医師国家試験合格率を誇る大学は、学内での進級基準が厳しい傾向にあるため注意が必要です。 また、都市部志向の強い受験生が地方大学へ入学し、住環境や医療事情の違い、キャリア形成の選択肢の狭さに悩むこともあります。こうした誤算を防ぐためには、単なる数値だけでなく、自分の志望や将来展望にあった学びの場かどうか、全体像をしっかり確認することが重要です。
教育内容・進級制度・国家試験対策の実態
医学部は大学ごとに教育内容や進級制度、国家試験対策の充実度に大きな差があります。多くの大学で進級基準が厳しく、毎年必修単位の取得や多数の試験合格が求められ、不合格で即留年となることも珍しくありません。また、国家試験対策も大学によってサポート体制や合格実績に差があり、十分なフォローが得られない環境では、最後の関門で苦労する学生が多くなります。同じ偏差値帯でも、進級の厳しさが想像以上で「やっと入ったのに留年や退学の危機に直面した」という声は少なくありません。志望校選びの際には、進級率や国家試験合格率、対策講座やサポート内容の実態も必ずチェックしましょう。
地域枠の義務や将来の勤務地制限の影響
地域枠で医学部に入学すると、卒業後に指定された地域や医療機関で一定期間勤務する義務が課されます。この年限は大学によりますが、6~9年間に及ぶことが一般的で、地域によってはより長期となるケースも珍しくありません。勤務地や診療科もある程度限定され、キャリアの自由度が大きく制限されることから、「都市部や専門性の高い病院で働きたい」「将来的に他地域で活躍したい」という希望がある場合、悩みや後悔につながる可能性があります。また、義務期間中に県外や他分野への移動は原則認められず、やむを得ず離脱する場合には奨学金の返還やペナルティが課されることもあります。自分の将来設計やライフスタイルにどのような影響を与えるか、親子でもよく相談して事前に慎重に判断しましょう。
まとめ
この記事では、偏差値・倍率・地域枠・立地・学費など、さまざまな視点から“穴場”とされる医学部を紹介してきました。偏差値や倍率が比較的低く、地域枠や推薦制度をうまく活用できる大学、特待制度のある私立医学部など、合格しやすくなる要素は多岐にわたります。
一方で、進級の厳しさや卒業後の勤務制限など、選ぶ際に注意すべき点も存在します。“入りやすさ”だけにとらわれず、将来のビジョンや学びの質を含めて、自分に合った医学部選びを行いましょう




-65.jpg)

-3.jpg)
-3-1.jpg)