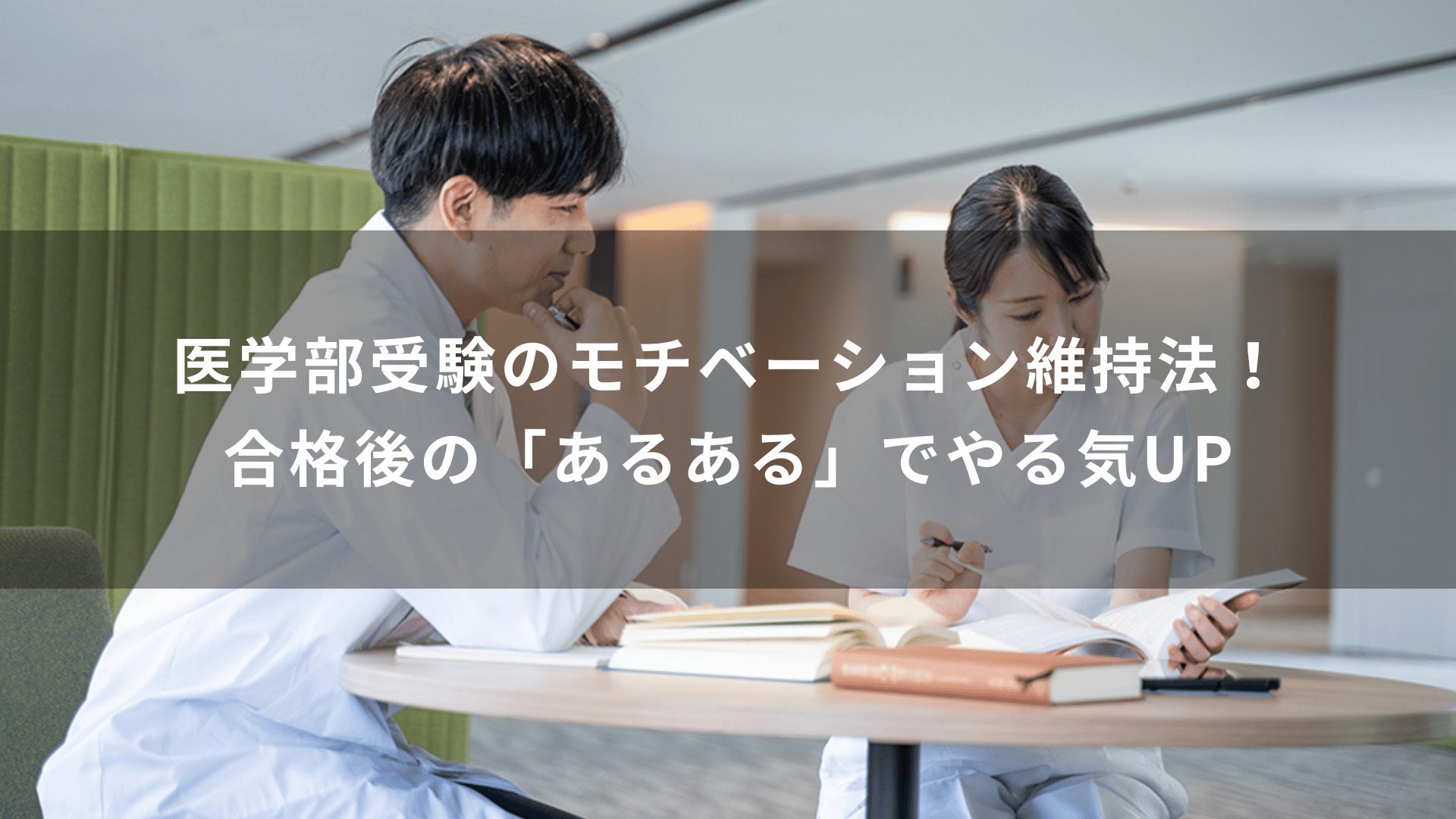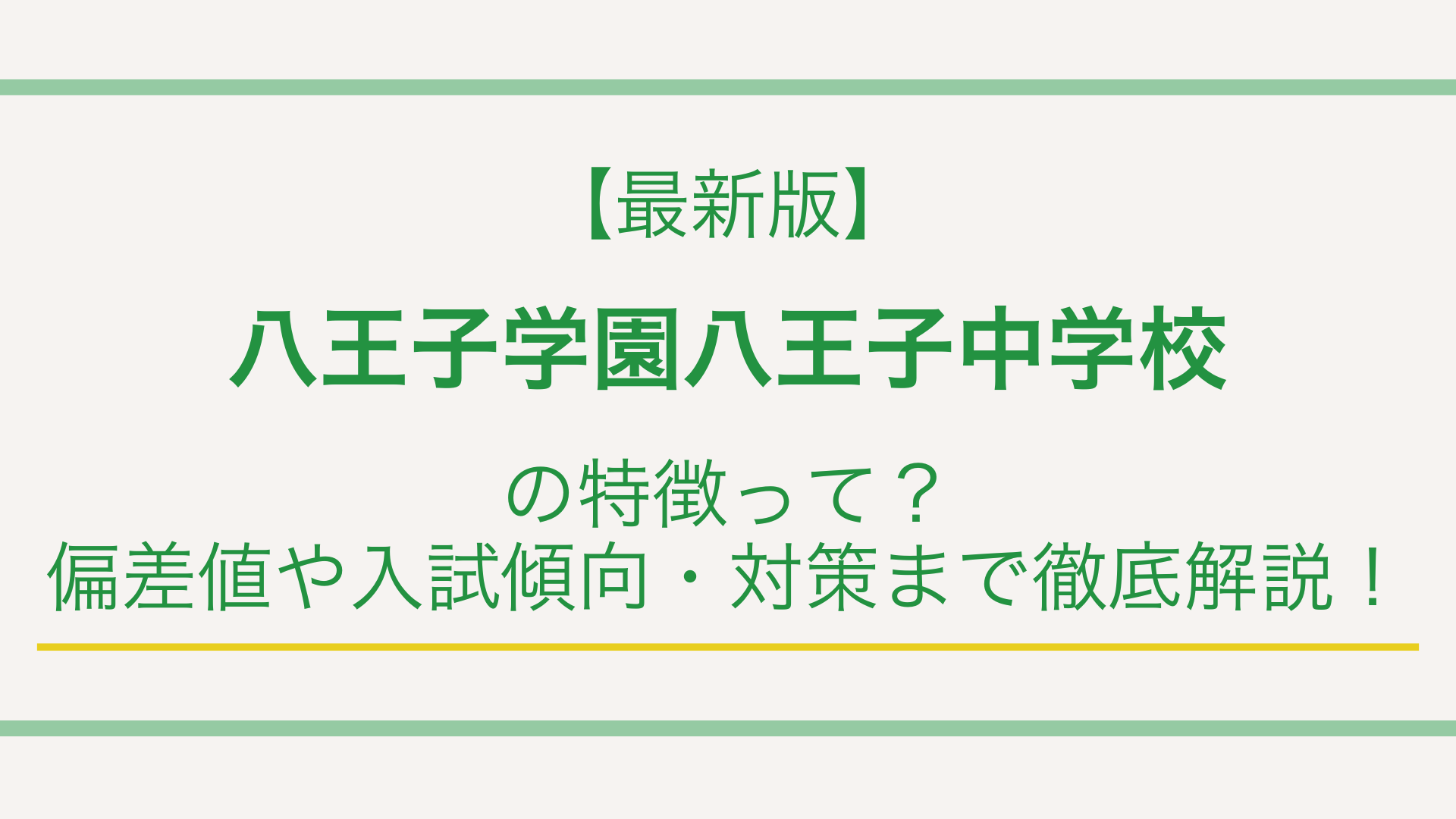医学部の総合型選抜や学校推薦型選抜において、合否を大きく左右するのが「自己推薦書」です。学力だけでは測れない個性や医師としての将来性をアピールする重要な書類ですが、「何から書けばいいかわからない」「どうすれば評価される文章になるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、医学部受験を専門とするプロの視点から、評価される自己推薦書の書き方を、構成や例文を交えながら徹底的に解説します。準備段階から具体的な執筆方法、避けるべきNG例、提出前の最終チェックリストまで、この記事を読めば自己推薦書作成のすべてがわかります。
あなたの熱意と個性が伝わる自己推薦書を完成させ、医学部合格への道を切り拓きましょう。
医学部自己推薦書とは?志望理由書との違い

まず、自己推薦書がどのような書類で、大学側が何を評価しているのかを正しく理解することが、効果的なアピールへの第一歩です。
自己推薦書で大学が見る評価ポイント
大学は自己推薦書を通して、ペーパーテストだけではわからないあなたの個性や潜在能力を見ています。特に医学部では、以下の点が重要視されます。
自己推薦書と志望理由書の目的の違い
自己推薦書と志望理由書は、提出を求められる目的が異なります。それぞれの違いを理解し、内容を書き分けましょう。
- ・自己推薦書 「自分がいかにその大学にふさわしい人材であるか」をアピールする書類です。自分の長所や経験、実績を根拠に、自分を大学に推薦する(売り込む)ことが目的です。
- ・志望理由書 「なぜその大学・学部で学びたいのか」を説明する書類です。大学の理念や特色への理解を示し、そこで学びたい理由を具体的に述べることが中心となります。
簡単に言えば、自己推薦書は「自分」が主役、志望理由書は「大学」が主役と考えると分かりやすいでしょう。ただし、医学部入試では両方の要素を1つの書類にまとめる形式も多いため、設問の意図を正確に読み取ることが大切です。
志望理由書は、自己推薦書と並んで提出を求められるケースが多く、評価の大きなポイントになります。書き方や例文をまとめた記事もあるので、自己推薦書とあわせてチェックしてみてください。
総合型・学校推薦型選抜での重要性
学力試験が重視される一般選抜と異なり、総合型選抜や学校推薦型選抜では、自己推薦書が合否に直結すると言っても過言ではありません。
出願書類の中でも、あなたの人物像を最も雄弁に語るのが自己推薦書です。面接試験も、多くの場合、自己推薦書に書かれた内容に基づいて行われます。つまり、質の高い自己推薦書は、書類選考を突破するだけでなく、面接を有利に進めるための「設計図」にもなるのです。
推薦入試そのものの仕組みや合格者像を理解しておくと、自己推薦書の書き方もより具体的になります。
自己推薦書を書く前の3つの準備

いきなり書き始めるのは非効率です。まずは以下の3つの準備を行い、文章の骨子を固めましょう。
医師を志す理由の深掘り(自己分析)
「なぜ医師になりたいのか?」この問いに対する答えが、自己推薦書の核となります。ありきたりな言葉で終わらせず、あなただけのオリジナルなストーリーに昇華させるために、以下の点を自問自答してみましょう。
これらの問いに答えることで、あなたの志望動機に深みと説得力が生まれます。
志望大学のアドミッション・ポリシーの確認
アドミッション・ポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を示す方針のことです。これは、大学から受験生へのメッセージであり、自己推薦書を作成する上で最も重要な指針となります。
必ず志望大学の公式サイトや募集要項でアドミッション・ポリシーを熟読し、大学が求める人物像と自分の強みや目標がどのように合致するかを考えましょう。大学の理念やカリキュラムの特色、研究内容などを理解し、それを自分の言葉で語れるようにしておくことが不可欠です。
アピールできる経験・実績の棚卸し
これまでの高校生活を振り返り、自己PRの材料となる経験や実績をすべて書き出してみましょう。どんな些細なことでも構いません。
書き出したエピソードの中から、「医師としての適性」や「大学のアドミッション・ポリシー」に結びつくものを選び出し、深掘りしていきましょう。
合格に近づく自己推薦書の基本構成

内容が良くても、構成が分かりにくければ魅力は半減してしまいます。読み手である評価者に意図を明確に伝えるため、論理的な構成を意識しましょう。
結論ファーストで伝えるPREP法
ビジネスシーンでも用いられるPREP法は、説得力のある文章を作成するための強力なフレームワークです。自己推薦書にも応用できます。
- Point(結論) 最初に最も伝えたいこと(例:「私は地域医療に貢献する医師になりたい」)を述べます。
- Reason(理由) その結論に至った理由を説明します(例:「なぜなら、祖父が過疎地で医療を受けられずに苦しんだ経験があるからです」)。
- Example(具体例) 理由を裏付ける具体的なエピソードや経験を挙げます(例:「この経験から地域医療の重要性を痛感し、高校では地域医療に関する探究活動に主体的に取り組みました」)。
- Point(結論の再提示) 最後に結論をもう一度述べ、熱意を伝えます(例:「以上の理由から、私は貴学の充実した地域医療実習を通して学び、将来は地域医療を支える医師になりたいと強く希望します」)。
この流れを意識することで、主張が明確で論理的な文章になります。
医師志望理由から将来性まで示す構成例
PREP法を基に、医学部自己推薦書に特化した構成例をご紹介します。この流れに沿って書くことで、バランスの取れた自己推薦書を作成できます。
- 【書き出し】医師を志す明確な動機と将来像 (結論:Point)
- 【中盤①】動機を裏付ける原体験やエピソード (理由・具体例:Reason, Example)
- 【中盤②】医師としての適性を示す自己PR(強みと具体例) (理由・具体例:Reason, Example)
- 【中盤③】その大学でなければならない理由 (理由・具体例:Reason, Example)
- 【結論・締め】入学後の抱負と将来の展望 (結論の再提示:Point)
構成別!自己推薦書の書き方とポイント

それでは、上記の構成に沿って、各パートの具体的な書き方とポイントを見ていきましょう。
①書き出し|冒頭で惹きつける書き方
書き出しは、評価者が最初に目にする部分です。ここで興味を引けるかどうかが、その後の印象を大きく左右します。
ポイントは、自分がどのような医師になりたいのかという「結論」を最初に示すことです。「私は、患者一人ひとりの心に寄り添い、対話を通じて最適な医療を提供する医師になりたいと考えています。」のように、あなたの目指す医師像を具体的に記述しましょう。これにより、文章全体の方向性が明確になり、評価者も読み進めやすくなります。
②医師の志望理由|原体験との結びつけ方
「人の役に立ちたい」「病気で苦しむ人を助けたい」といった動機は立派ですが、それだけでは他の受験生との差別化は困難です。なぜそう思うようになったのか、きっかけとなった「あなただけの原体験」を具体的に語りましょう。
例えば、「祖母が癌と診断された際、担当医の先生が不安な家族に何度も丁寧に説明してくださる姿を見て、技術だけでなく患者の心を支えることの重要性を学びました。」のように、個人的なエピソードを交えることで、志望動機にリアリティと深みが生まれます。
③自己PR|医師の適性と具体例の示し方
ここでは、あなたが医師として優れた資質を持っていることをアピールします。ただし、「私には協調性があります」と書くだけでは不十分です。その強みをどのように発揮したか、具体的なエピソードを添えて証明しましょう。
- ・アピールしたい強み (例:探究心、リーダーシップ、協調性、忍耐力など)
- ・それを裏付ける具体的なエピソード (例:文化祭で対立する意見をまとめ、企画を成功させた経験)
- ・その経験から得た学びと、それをどう医師の仕事に活かすか (例:多様な意見を尊重し、合意形成を図る力は、チーム医療において不可欠だと考えます)
このように「強み+具体例+将来への活用」をセットで語ることで、説得力が格段に増します。
④大学を選んだ理由|理念や特色との接続
「なぜ、数ある大学の中からこの大学を選んだのか?」を明確に伝えるパートです。ここで、事前に調べたアドミッション・ポリシーや大学の特色が活きてきます。
「貴学が掲げる『地域医療への貢献』という理念に深く共感しました。特に、1年次から始まる地域医療実習プログラムは、私が医師を目指すきっかけとなった地域医療の課題解決に貢献したいという目標と完全に合致しています。」のように、自分の目標と大学の特色を具体的に結びつけて述べましょう。「家から近いから」といった理由は避け、その大学で学びたいという熱意を伝えることが重要です。
⑤結論・締め|将来性と熱意の伝え方
最後は、これまでの内容をまとめ、入学後の意欲と将来のビジョンを力強く示して締めくくりましょう。
「これまでに培ってきた探究心と協調性を活かし、貴学の先進的な研究にも積極的に参加したいです。そして、卒業後は地域医療の最前線で、患者さんから信頼される医師として貢献することが私の目標です。」のように、入学後の学びへの期待と、その先の将来像を具体的に語ることで、あなたの将来性を評価者に印象付けましょう。
【文字数・強み別】医学部自己推薦書の例文集
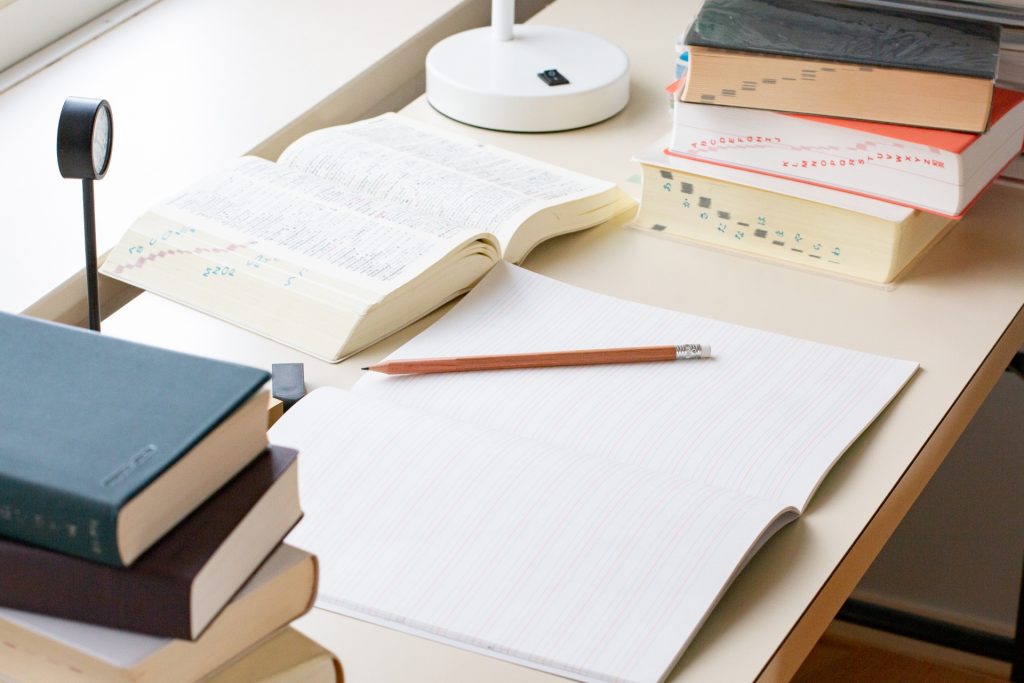
ここでは、具体的な例文をいくつか紹介します。構成や表現を参考に、あなた自身の言葉で書き換えてみてください。
800字の自己推薦書例文
私は、患者一人ひとりの背景にある物語に耳を傾け、心に寄り添う医療を実践する医師になりたい。
この想いの原点は、高校1年生の時に参加したへき地医療のドキュメンタリー上映会にある。そこでは、医師不足により十分な医療を受けられない高齢者の実情が映し出されていた。特に印象的だったのは、ある医師が「病気を診るだけでなく、その人の生活や孤独も診るのが私の仕事だ」と語っていたことだ。この言葉に衝撃を受け、私は技術や知識だけでなく、患者の人生全体を支える医師を目指そうと決意した。
この目標に向け、私は2つの力を意識して高校生活を送った。一つは「傾聴力」だ。所属していた討論部では、相手の意見を最後まで聞き、その意図を正確に理解することに努めた。当初は自分の主張をすることに必死だったが、相手の背景を理解しようとすることで、より建設的な議論ができるようになった。この経験は、患者やその家族との信頼関係を築く上で必ず役立つと確信している。
もう一つは「探究心」である。地域の医療課題について自主研究を行い、高齢者の通院負担を軽減するためのコミュニティバスの有効性について論文にまとめた。この研究を通して、課題を発見し、解決策を模索するプロセスに大きなやりがいを感じた。
貴学のアドミッション・ポリシーである「多様な視点から地域医療に貢献する人材の育成」に強く惹かれている。特に、多職種連携を重視した実践的なカリキュラムは、私が目指す全人的医療を学ぶ上で最高の環境だと考える。
入学後は、討論部で培った傾聴力と自主研究で得た探究心を最大限に発揮し、仲間と切磋琢磨しながら学びを深めたい。そして将来的には、地域に根ざし、住民から「あの先生がいてくれて良かった」と心から思われる医師として、貴学で得た学びを社会に還元していく所存だ。
1000字の自己推薦書例文
私は、科学的探究心と倫理観を両立させ、常に進化する医療技術を患者のために正しく用いることができる医師になることを強く志望する。
この志を抱いたきっかけは、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の課題研究で「ゲノム編集技術の倫理的課題」について探究した経験にある。当初は、難病治療の可能性を秘めた素晴らしい技術だと考えていた。しかし、研究を進める中で、デザイナーベビー問題や予期せぬ副作用のリスクなど、生命倫理に関わる深刻な課題が数多く存在することを知った。技術の進歩が必ずしも人類の幸福に直結するわけではないという現実に、大きな衝撃を受けた。この経験から、最先端の知識を追い求める探究心と、それを扱う医師に求められる高い倫理観の両方を兼ね備えることの重要性を痛感した。
この目標を達成するため、私は高校生活において主体的な学びを追求してきた。課題研究では、国内外の論文を数十本読み込み、大学教授にメールで質問するなどして、多角的な情報収集に努めた。その結果、研究成果を地域の高校生科学技術フェアで発表し、優秀賞をいただくことができた。このプロセスを通じて、未知の課題に対して粘り強くアプローチし、論理的に考察する力を養うことができたと自負している。
また、私は学業だけでなく、他者と協働する力も重視してきた。文化祭ではクラスの企画責任者を務め、意見が対立するメンバーの間に入り、双方の意見を尊重しながら議論を重ね、最終的に全員が納得できる形で企画を成功に導いた。この経験から、多様な価値観を持つ人々と目標を共有し、チームとして成果を出すことの難しさと重要性を学んだ。この協調性は、医師、看護師、技師など多職種が連携して患者を支える「チーム医療」の現場で不可欠な素養だと考えている。
貴学が、最先端の医学研究と倫 理教育の両方に力を入れている点に、私は強い魅力を感じている。特に、貴学の〇〇研究室が取り組んでいる△△の研究は、私が課題研究で抱いた問題意識と深く関連しており、ぜひその一端に触れたいと考えている。また、1年次から始まる医療倫理に関するカリキュラムは、私が目指す医師像の礎を築く上で、最高の環境であると確信している。
入学が許可された暁には、課題研究で培った探究心を活かして、学問に真摯に取り組むことはもちろん、サークル活動などを通して多様な仲間と交流し、人間性を磨きたい。そして将来的には、科学的根拠に基づいた的確な診断能力と、患者の尊厳を守る高い倫理観を兼ね備えた医師として、医療の発展と人々の幸福に貢献していく覚悟だ。
強み別(学業・課外活動)の例文
学業(探究心)をアピールする場合
私は、生物の授業で学んだ免疫システムに強い興味を持ち、「自然免疫におけるマクロファージの役割」というテーマで1年間探究活動を行いました。先行研究を調べる中で、教科書には載っていない未解明な部分が多くあることを知り、知的好奇心を刺激されました。実験では、仮説通りに進まない困難にも直面しましたが、粘り強く条件を変えて試行錯誤を重ね、最終的には考察を論文にまとめることができました。この経験を通じて培った、未知の課題に対して仮説を立て、検証を繰り返す科学的探究心は、将来、医師として診断や治療方針を決定する上で必ず役立つ力だと考えています。
課外活動(リーダーシップ)をアピールする場合
私はバスケットボール部の部長として、チームをまとめる役割を担いました。当初、チームは個々の能力は高いものの、連携がうまくいかず、試合に勝てない時期が続きました。私は、全部員と個別に面談する機会を設け、それぞれの悩みや目標を聞き出すことに努めました。その上で、全員が納得できる練習メニューを提案し、チームの目標を「県大会ベスト8」と明確に設定しました。異なる意見を調整し、一つの目標に向かってチームを導いたこの経験は、多様な専門家と連携して患者さんの治療にあたるチーム医療の現場において、リーダーシップを発揮する上で大きな強みになると信じています。
悪い例と改善例の比較
【悪い例】 私は人の役に立ちたいので、医師になりたいです。高校では部活動を頑張り、協調性を学びました。貴学は家から近く、歴史もあるので志望しました。入学したら一生懸命勉強して、立派な医師になりたいです。
【改善例】 私は、幼い頃に入院した際に担当してくださった医師の、丁寧な説明と温かい励ましに救われた経験から、患者さんの不安に寄り添える医師になりたいと考えるようになりました。この目標に向け、高校ではサッカー部の活動に注力し、ポジションの異なる仲間と連携して勝利を目指す中で、チームで目標を達成するために不可欠な協調性を学びました。貴学が掲げる「全人的医療」の理念と、充実したコミュニケーション教育のカリキュラムに強く惹かれており、私の目標を実現する上で最高の環境だと確信しています。入学後は、サッカーで培った体力と協調性を活かし、仲間と切磋琢磨しながら、患者さんの心まで診ることができる医師を目指して学び続けます。
【改善のポイント】
評価を下げる自己推薦書のNG例

せっかくの努力が無駄にならないよう、評価を下げてしまう可能性のある表現は避けましょう。
抽象的で具体性に欠ける表現
「コミュニケーション能力が高い」「リーダーシップがある」といった言葉だけでは、評価者はあなたの能力を判断できません。必ず具体的なエピソードをセットで記述し、主張に説得力を持たせましょう。
受け身な姿勢や他責的な記述
「〜という経験をさせてもらった」「先生に勧められて〜した」といった受け身な表現は、主体性の欠如と捉えられかねません。「〜に主体的に取り組んだ」「自ら〜と考え、行動した」のように、あなたの意志で行動したことが伝わる表現を心がけましょう。
根拠のない自信過剰なアピール
「私は誰よりも優れた医師になれます」「必ず貴学に貢献します」といった、根拠のない自信は傲慢な印象を与えます。自信を持つことは大切ですが、「〜という経験を活かし、〜という形で貢献したい」のように、謙虚な姿勢で、かつ具体的に記述することが重要です。
自己推薦書と同じように、文章力や論理性が問われるのが小論文です。特に推薦入試ではセットで課されることが多いため、自己推薦書と並行して準備しておきましょう。
提出前の最終チェックリスト
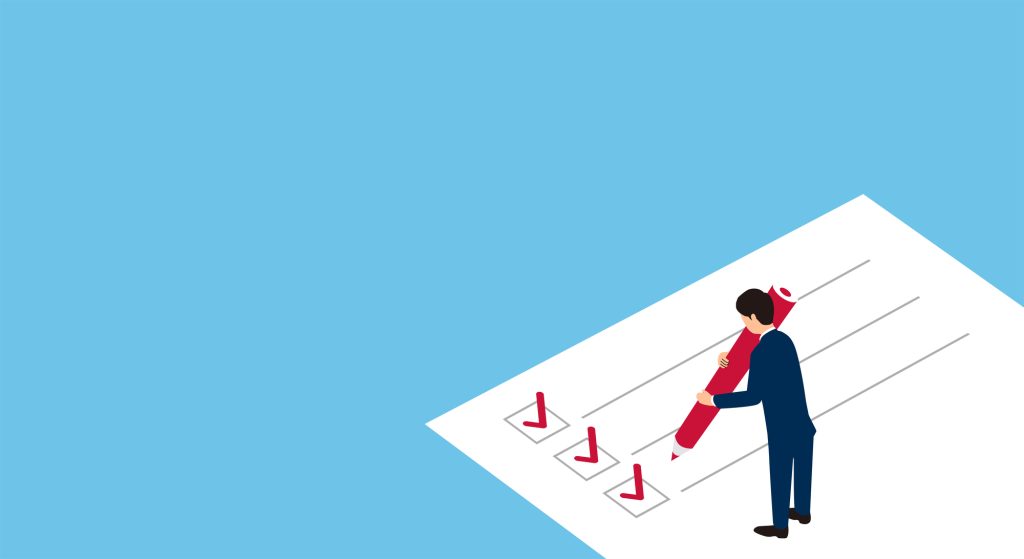
書き終えたら、必ず以下の項目をチェックして、完璧な状態で提出しましょう。
誤字脱字・文法エラーの確認
誤字脱字は、注意力が散漫であるという印象を与えかねません。声に出して読んでみる(音読する)と、文章のリズムや間違いに気づきやすくなるのでおすすめです。
指定文字数や形式の遵守
大学が指定する文字数(例:800字以内、1000字程度など)や、手書き・PC作成などの形式を必ず守りましょう。文字数オーバーや不足は、指示を理解していないと判断される可能性があります。
内容の一貫性と論理的なつながり
文章全体を読み返し、冒頭で述べた将来像と結論が一致しているか、エピソードとアピールしたい強みがきちんと結びついているかなど、論理的な矛盾がないかを確認しましょう。
第三者(先生・親)による添削依頼
自分では気づかない間違いや、分かりにくい表現があるかもしれません。完成したら、必ず学校の先生や予備校の講師、保護者など、信頼できる第三者に読んでもらい、客観的な意見をもらうことが非常に重要です。
「本当にこの内容で評価されるのかな…」と不安に思う方も多いはず。そんな時は、医学部受験を熟知した家庭教師に相談すれば安心です。学研の家庭教師では、文章だけでなく出願戦略まで含めた具体的なアドバイスをしています。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
医学部の自己推薦書は、単なる作文ではありません。それは、あなたがどのような人間で、将来どのような医師になりたいのかを、あなた自身の言葉で語る「未来へのプレゼンテーション」です。
この記事で紹介した準備、構成、書き方のポイントを参考に、あなたにしか書けない、熱意あふれる自己推薦書を完成させましょう。
自己推薦書を書くプロセスは、自分自身と深く向き合う貴重な機会です。なぜ医師になりたいのかを改めて見つめ直し、自分の強みを再発見することで、面接への自信にもつながるはずです。あなたの努力が実を結び、医学部合格の夢が叶うことを心から応援しています。





-1-320x180.jpg)
-3-320x180.jpg)
-4-320x180.jpg)