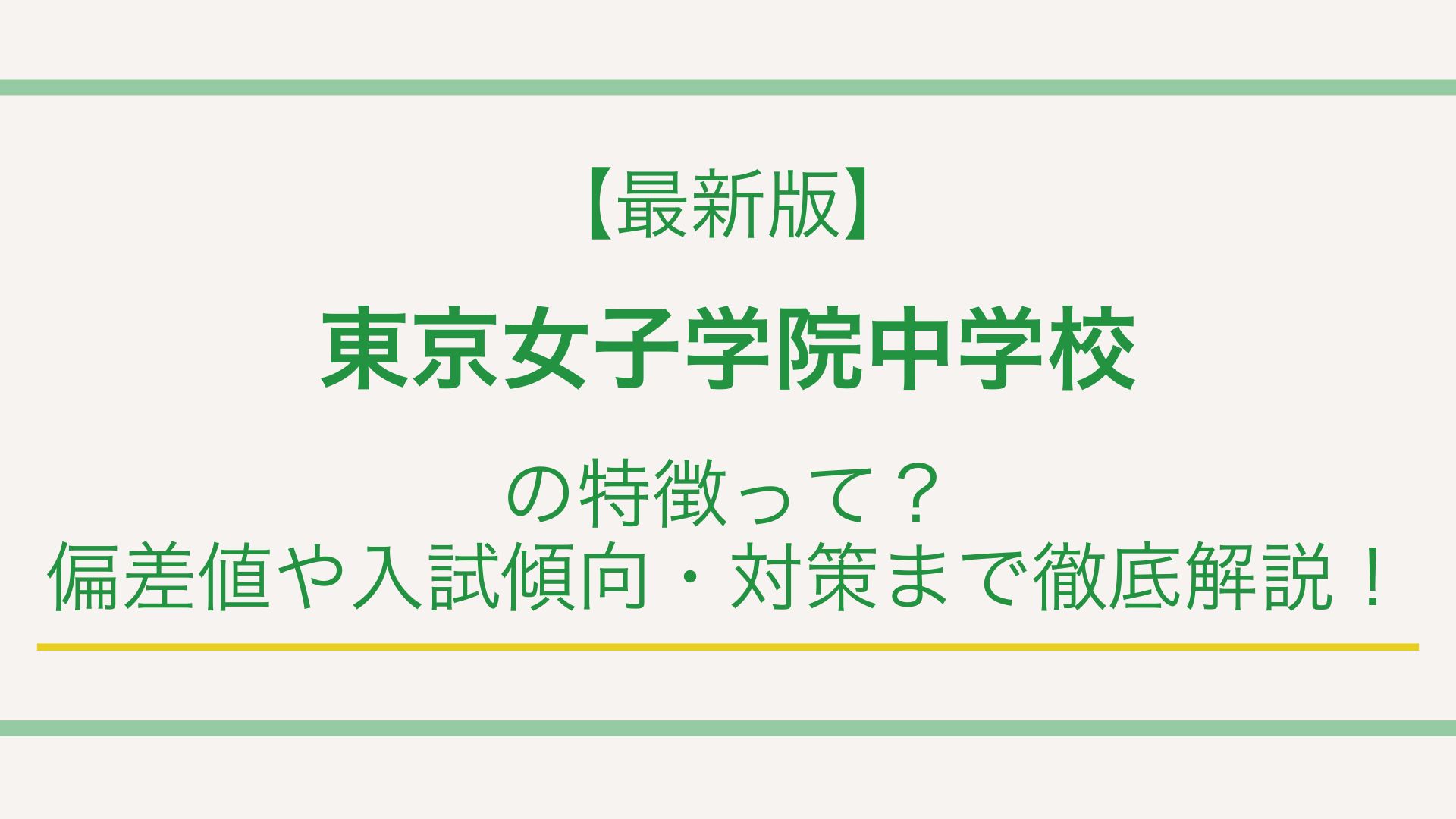「サピックスの算数の授業についていけない…」 「宿題が多くて、家庭学習がうまく回らない…」 「頑張っているのに、算数の成績が上がらない…」
中学受験の最高峰ともいわれるサピックス。その中でも特に「算数」は、カリキュラムの進度が速く、内容も高度なため、多くのご家庭で悩みの種になりがちです。
しかし、ご安心ください。サピックスの算数で成績を上げるためには、正しい勉強法と家庭学習のやり方があります。闇雲にすべての宿題をこなすのではなく、ポイントを押さえた学習サイクルを確立することが、偏差値アップへの一番の近道です。
この記事では、サピックスの算数に悩むお子様と保護者様のために、家庭学習で成果を出すための具体的な勉強法を、長年の指導経験を持つプロの視点から徹底解説します。ぜひ、明日からの学習にお役立てください。
サピックス算数:学習の基本戦略
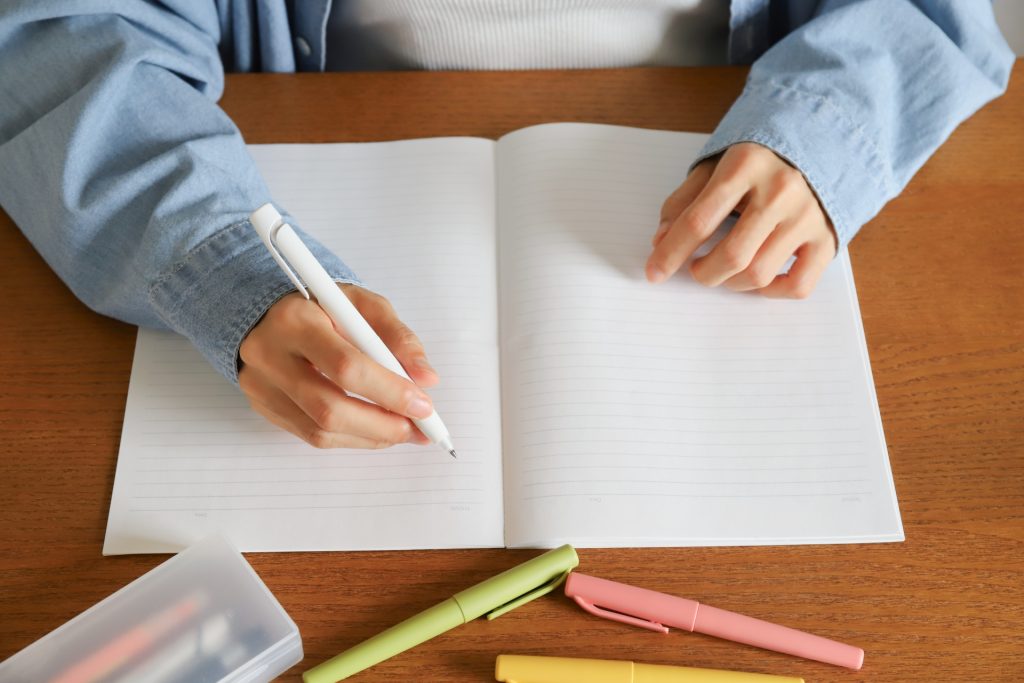
サピックスの算数を攻略するには、まず基本となる戦略を理解することが不可欠です。多くのご家庭が陥りがちな「全部やろうとする」学習から脱却し、効率的に成績を上げるための3つの柱を解説します。
最重要は「復習中心」の学習サイクル確立
サピックスの算数学習において、最も重要なのは「復習」です。サピックスのカリキュラムは、同じ単元を難易度を上げながら繰り返し学ぶ「スパイラル方式」を採用しています。
そのため、授業で習った内容をその週のうちに確実に定着させることが、次のステップに進むための絶対条件となります。復習こそが、成績を上げるための最短ルートであり、家庭学習の核と位置づけましょう。授業の理解度が不十分なまま先に進んでも、知識は積み上がっていきません。
特にマンスリーテストや組分けテストは、復習の成果を測る大切な指標になります。テスト対策を効果的に行うことが算数成績アップにつながります。サピックスのマンスリー・組分けテスト対策はこちら。
問題の取捨選択と優先順位の付け方
サピックスから出される課題は膨大です。すべてを完璧にこなそうとすると、時間がいくらあっても足りず、親子ともに疲弊してしまいます。
ここで重要になるのが、問題の「取捨選択」と「優先順位付け」です。お子様の現在の学力やクラスの位置に応じて、取り組むべき問題を見極める必要があります。
- ・最優先(A):授業で扱った問題と、その類題: デイリーサピックスの「デイリーステップ」や「デイリーサポート」のA~C問題(クラスレベルによる)など、授業の核となる問題です。これらは100%自力で解けるようにすることが目標です。
- ・優先(B):定着度を確認するための標準問題: デイリーサポートのD問題や、各種テストで正答率が高いにもかかわらず間違えた問題などが該当します。まずは8割程度の正解を目指しましょう。
- ・後回し(C):応用・発展問題: デイリーサポートのE問題や思考力系の問題、テストの最後のほうにある難問などです。基礎が固まっていない段階で手を出しても、時間ばかりかかってしまい非効率です。まずはA・Bが完璧になってから、余力があれば挑戦する、というスタンスで問題ありません。
「できない問題」を「できる問題」に変えることが成績アップの本質です。まずは、お子様が確実にマスターすべき問題に集中させましょう。
算数で成績を安定させるためには、基礎の徹底に加え、最上位を目指す戦略も必要です。サピックスでαクラスに入るための勉強法はこちら。
サピックス算数における予習の要不要
サピックスでは、算数の予習は原則として不要です。むしろ、予習をすることで「知っている」という安心感から授業への集中力が削がれたり、間違った解法が頭に入ってしまったりするデメリットのほうが大きいと考えられています。
サピックスの授業は、生徒の思考力を引き出すように構成されています。まっさらな状態で授業に臨み、先生の発問に集中し、「どうしてそうなるんだろう?」と考えること自体が重要な学習です。家庭学習では、授業で受けた新鮮な刺激を忘れないうちに復習することに全力を注ぎましょう。
サピックス算数:家庭学習のやり方と教材活用法

基本戦略を理解したところで、次に「デイリーサピックス」や「基礎力トレーニング」といった具体的な教材を、家庭学習でどう活用すればよいのかを解説します。
デイリーサピックスの効果的な復習方法
デイリーサピックスは、サピックスの家庭学習の中心となる教材です。以下の手順で復習を進めることで、学習内容を効率的に定着させることができます。
- ・授業の解き直し(授業当日~翌日): まずは授業で扱った問題を、解説を見ずに自力で解き直します。ここで解けなかった問題には「×」、解けたけれど自信がない問題には「△」など、印をつけておきましょう。
- ・宿題への取り組み: 「問題の取捨選択」の考え方に基づき、優先順位の高い問題から取り組みます。解けなかった問題には、正直に印をつけておくことが大切です。
- ・丸付けと解説の読み込み: 保護者の方が丸付けをし、間違えた問題はお子様自身に解説をじっくり読ませます。なぜ間違えたのか、正しい解法はどういうものかを理解させることが目的です。
- ・2回目の解き直し(2~3日後): 1回目で間違えた「×」印の問題だけを、もう一度解き直します。ここで解ければOKですが、まだ解けない場合は、再度解説を読み込み、理解を深めます。
- ・3回目の解き直し(週末): 2回目でも解けなかった問題を、週末にもう一度解き直します。最低3回は繰り返すことで、苦手な問題も記憶に定着しやすくなります。
このサイクルを1週間で回すことが理想です。
基礎力トレーニング(基礎トレ)の毎日継続
「基礎力トレーニング」、通称「基礎トレ」は、計算力と一行問題への対応力を養うための重要な教材です。
- ・毎日、時間を決めて取り組む: 朝食前や学校に行く前の10~15分など、時間を決めて毎日継続することが何よりも大切です。歯磨きと同じように、生活の一部として習慣化させましょう。
- ・満点を目指し、間違えたら必ず解き直す: 目標は常に満点です。時間を計って緊張感を持ち、もし間違えた問題があれば、その日のうちに必ず解き直して完璧にしておきましょう。
毎日のコツコツとした積み重ねが、テスト本番でのケアレスミスを防ぎ、得点力を安定させます。
毎日の基礎学習リズムを作ることは、中学受験全般に通じる重要ポイントです。中学受験の家庭学習習慣をつける方法はこちら。
復習テスト・組分けテストの効果的な見直し
マンスリーテストや組分けテストは、学習の成果を測る絶好の機会ですが、最も重要なのはテスト後の見直しです。
- ・テスト当日のうちに自己採点と解き直しを行う: 記憶が新しいうちに、間違えた問題を解き直しましょう。「なぜ間違えたのか(計算ミス、勘違い、時間が足りなかったなど)」を分析することが重要です。
- ・正答率を参考に見直しの優先順位を決める: 正答率が50%以上あるにもかかわらず間違えた問題は、多くの生徒が正解している、つまり「落としてはいけない問題」です。これらを最優先で復習し、確実に解けるようにしましょう。
- ・解き直しノートにまとめる: 間違えた問題をノートにまとめ、自分だけの「弱点問題集」を作成するのも非常に効果的です。
テストは受けっぱなしにせず、次へのステップアップのための貴重な教材として活用しましょう。
点数や偏差値の見方を正しく理解することが、クラス昇降に一喜一憂せず学習を前進させる鍵となります。サピックスのクラス分け基準とコース表の見方はこちら。
偏差値を上げるための復習ノートの作り方
ただ間違えた問題を貼り付けるだけでは、効果的な復習ノートとは言えません。偏差値を上げるためのノートには、以下の要素を盛り込みましょう。
- ・問題と自分の間違った解答: どのような間違いをしたのかを客観的に把握するために、自分の解答も残しておきます。
- ・正しい解法・ポイント: 解説を読んで理解した、正しい解き方や重要なポイントを自分の言葉でまとめます。図や式も丁寧に書き写しましょう。
- ・間違いの原因分析: 「なぜ間違えたのか?」を言語化します。「公式を忘れていた」「問題文を読み間違えた」など、具体的な原因を書くことで、同じミスを防ぐ意識が高まります。
- ・次に活かすこと: 「次は問題文の単位に線を引く」「計算は余白に大きく書く」など、具体的なアクションプランを書き込みます。
このノートをテスト前に見返すことで、自分の弱点を効率的に総復習できます。
サピックス算数:1週間の家庭学習スケジュールモデル

「具体的に、いつ何をすればいいの?」という疑問にお答えするため、5年生を例にした1週間の家庭学習スケジュールモデルをご紹介します。これをベースに、お子様の生活リズムや塾のスケジュールに合わせて調整してください。
授業当日と翌日のタスク
授業で得た知識が最も新鮮なこの時期の学習が、定着度を大きく左右します。
- 授業当日(例:火曜日)
- ・帰宅後、授業で習った内容を親子で軽く話す(5分程度)。
- ・授業で扱った問題の解き直し(30分~1時間)。まずはこれだけできれば十分です。
- 授業翌日(例:水曜日)
- ・基礎トレ(10分)。
- ・前日の授業の宿題(優先順位の高いもの)に着手(1時間~1.5時間)。
授業がない平日のタスク
計画的に宿題を進め、復習の時間を確保します。
- 木曜日
- ・基礎トレ(10分)。
- ・火曜日の算数の宿題の残り(1時間~1.5時間)。
- 金曜日
- ・基礎トレ(10分)。
- ・別の曜日の授業(例:木曜日の理科・社会)の宿題。
- ・算数の宿題で間違えた問題の1回目の解き直し(30分)。
週末のタスクと週次計画の見直し
週末は、平日にやりきれなかった部分の調整と、1週間の総仕上げを行います。
- 土曜日
- ・基礎トレ(10分)。
- ・1週間分の宿題で間違えた問題の総復習(解き直しノート作成など)(1.5時間~2時間)。
- ・余力があれば、応用問題に挑戦。
- 日曜日
- ・基礎トレ(10分)。
- ・テストが近い場合は、テスト範囲の総復習。
- ・1週間の学習状況を振り返り、翌週の計画を軽く立てる。
重要なのは、計画を詰め込みすぎないことです。予備日を設け、体調や学校行事に合わせて柔軟に調整できるようにしておきましょう。
サピックス算数:学年別の勉強法と注意点
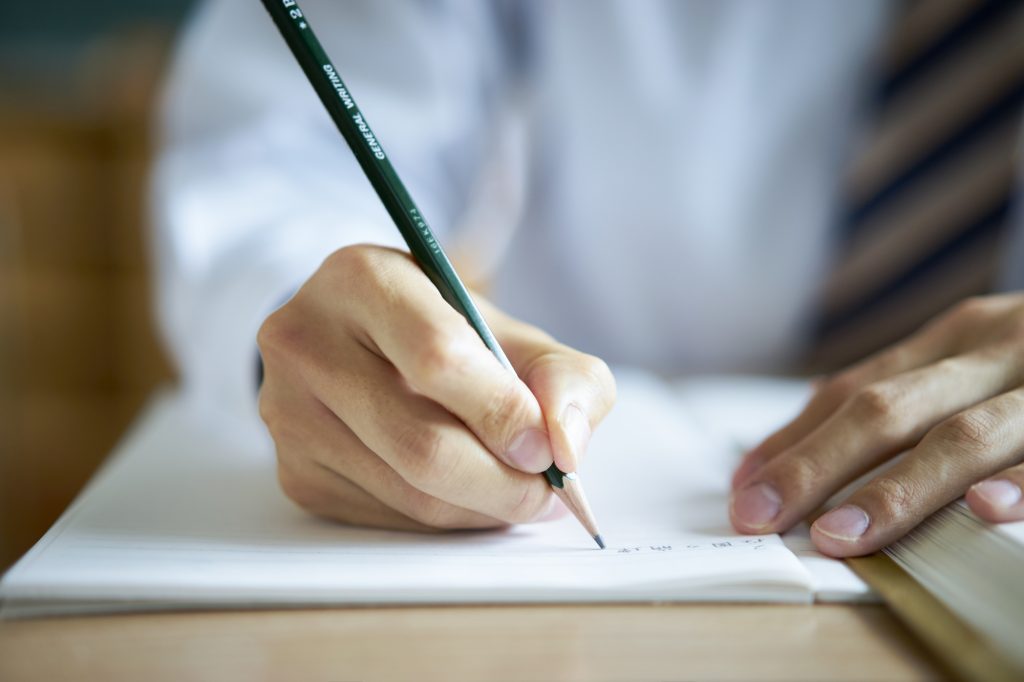
サピックスの算数は、学年ごとに求められることや学習のポイントが異なります。ここでは、特に重要な4年生から6年生までの勉強法と注意点を解説します。
4年生の勉強法|学習習慣の確立
4年生は、本格的な中学受験勉強のスタートラインです。この時期の最重要課題は「学習習慣の確立」です。
焦らず、まずは勉強を毎日の生活に組み込むことを目標にしてください。
5年生の勉強法|学習量の増加への対応
5年生は、サピックスのカリキュラムの中で最も学習量が増え、内容も一気に難しくなる学年です。多くのお子様が「中だるみ」や成績の伸び悩みを経験する、まさに正念場と言えます。
6年生の勉強法|志望校対策と過去問演習
6年生は、いよいよ受験本番を見据えた最終学年です。これまでの学習の総仕上げと、志望校に特化した対策が中心となります。
最後まで諦めずに、基礎の確認と志望校対策を両輪で進めていきましょう。
悩み別Q&A|成績が上がらない時の対策

ここでは、多くのご家庭から寄せられる具体的な悩みについて、Q&A形式でお答えします。
授業についていけない・算数が苦手な場合
A. 基礎に立ち返り、問題のレベルを絞ることが最優先です。
サピックスの授業についていけないと感じる場合、その単元の土台となる知識が抜けている可能性が高いです。
- ・前の学年のテキストに戻る勇気を持つ: 例えば、5年生で「割合」につまずいているなら、4年生のテキストの「割合」の回に戻って復習してみましょう。急がば回れです。
- ・デイリーサポートのA・B問題に集中する: 難しい問題は一旦すべて横に置き、クラスレベルに関わらず、最も基本的な問題だけを完璧にすることを目指してください。小さな「できた!」の成功体験を積むことが、苦手意識を克服する第一歩です。
- ・計算力を徹底的に強化する: 算数が苦手なお子様は、計算がおぼつかないケースが多く見られます。基礎トレに加え、市販の計算ドリルなども活用し、正確かつスピーディーに計算できる力を養いましょう。
宿題が終わらない・家庭学習が回らない場合
A. 「全部やらない」と決めることが解決策です。
宿題が終わらないのは、お子様の能力や努力が足りないからではありません。サピックスの課題は、そもそも全員が完璧にこなせる量ではないのです。
- ・「やることリスト」ではなく「やらないことリスト」を作る: お子様の学力に合わせて、「今週はデイリーサポートのE問題はやらない」「思考力問題は週末に1問だけ」など、やらないことを明確に決めましょう。
- ・優先順位を親子で共有する: 「今週は、このA問題とB問題だけは絶対にできるようにしようね」というように、目標を具体的に、かつ達成可能なレベルに設定し、親子で共有することが大切です。これにより、お子様も安心して学習に取り組めます。
上位クラス(αクラス)を目指す勉強法
A. 基礎の完璧な定着を前提に、思考力を鍛える学習を取り入れましょう。
αクラス(上位クラス)に定着するためには、標準問題をミスなく解き切る力に加え、応用問題に対応できる思考力が必要です。
- ・別解を考える習慣をつける: 一つの問題を解いた後、「もっと効率的な解き方はないか?」「別の考え方はできないか?」と、多角的にアプローチする習慣をつけましょう。解説に載っている別解を研究するのも有効です。
- ・思考力問題に粘り強く取り組む: デイリーサピックスの思考力問題や、市販のハイレベル問題集などに時間をかけて取り組む時間を設けましょう。すぐに答えを見ずに、10分、15分と粘り強く考える経験が、思考の体力と柔軟性を育てます。
- ・ミスの原因を徹底的に分析する: 上位層の戦いでは、一つのケアレスミスが命取りになります。間違えた問題について、「なぜミスしたのか」を徹底的に分析し、二度と同じ間違いをしないための対策をノートにまとめるなど、ミスの撲滅に全力を注ぎましょう。
親の関わり方とサポートのコツ

中学受験は「親子の受験」とも言われます。特に算数では、保護者の適切なサポートがお子様の成績を大きく左右します。
子供への質問対応と教え方のポイント
お子様から「分からない」と質問された時、どう対応すればよいのでしょうか。
- すぐに答えを教えない
最もやってはいけないのが、すぐに答えや解き方を教えてしまうことです。これではお子様の思考力は育ちません。 - ヒントを与えて考えさせる「伴走者」になる
「この問題、前にやったあの問題と似ていない?」「この図に補助線を引いてみたらどうかな?」など、お子様自身が答えにたどり着けるようなヒントを与えましょう。解説を一緒に読み解き、「どこが分からなかったの?」と問いかけるのも効果的です。 - 感情的にならない
「なんでこんな問題も分からないの!」といった言葉は百害あって一利なしです。親が感情的になると、お子様は質問すること自体をためらうようになってしまいます。難しい場合は、一度距離を置くことも大切です。
モチベーションを維持させる声かけ
成績が上がらない時や、難しい問題に直面した時、お子様のモチベーションは下がりがちです。そんな時こそ、保護者の声かけが重要になります。
- 結果ではなく「過程」を褒める
「テストの点数が良かったね」だけでなく、「毎日コツコツ基礎トレを頑張っているね」「難しい問題に諦めずに挑戦していて偉いね」など、努力している過程や姿勢を具体的に褒めてあげましょう。 - 他人と比較しない
「〇〇ちゃんはαクラスなのに…」といった比較は、お子様の自己肯定感を下げるだけです。比べるべきは、過去の自分自身です。「前は解けなかったこの問題が解けるようになったね!」と、お子様自身の成長を認め、伝えてあげてください。
個別指導や家庭教師を検討するタイミング
家庭学習だけではどうしても限界を感じる場合、外部の力を借りるのも有効な選択肢です。
以下のような状況が見られたら、個別指導や家庭教師の利用を検討するタイミングかもしれません。
- ・特定の単元がどうしても克服できない
- ・保護者が教えても、親子喧嘩になってしまう
- ・家庭学習のペースが全くつかめず、宿題が回らない
- ・質問できる相手がおらず、分からない問題が溜まっていく一方
プロの講師は、お子様の弱点を的確に分析し、サピックスのカリキュラムに合わせた最適な指導を行ってくれます。親子関係を良好に保つためにも、専門家のサポートを検討する価値は十分にあります。
ご家庭だけでは解決できない場合は、外部のプロを活用するのも有効な手段です。学研の家庭教師によるサピックス対策はこちらをご覧ください。
まとめ
今回は、サピックスの算数の成績を上げるための具体的な勉強法と家庭学習のやり方について解説しました。最後に、最も重要なポイントを振り返ります。
- ・最重要は「復習中心」の学習: サピックスはスパイラル方式。その週の学習内容を定着させることが最優先です。
- ・「問題の取捨選択」で無理なく学習: すべてを完璧にこなすのは不可能。お子様のレベルに合わせ、優先順位をつけて取り組みましょう。
- ・教材を正しく活用する: デイリーサピックスは「3回解き直し」、基礎トレは「毎日継続」が基本です。
- ・テストは「見直し」こそが本番: 間違えた問題を分析し、解き直しノートを作ることで、弱点を克服できます。
- ・親は「伴走者」に徹する: 答えを教えるのではなく、ヒントを与えて考えさせ、努力の過程を褒めてあげましょう。
サピックスの算数は確かに大変ですが、正しい方法で努力を続ければ、必ず道は開けます。この記事で紹介した方法を参考に、親子で力を合わせ、焦らず一歩ずつ学習を進めていってください。応援しています。




-59.jpg)
-34-320x180.jpg)

-63-320x180.jpg)
-55.jpg)