「うちの子、集中力がなくて宿題が全然進まない…」 「簡単なミスばかりで、勉強が嫌いになってしまわないか心配…」
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ小学生のお子さんを育てる中で、勉強に関する悩みは尽きないものですよね。何度言っても机に向かわなかったり、すぐに他のことに気を取られたりする姿を見ると、ついイライラしてしまったり、将来への不安を感じてしまったりすることもあるでしょう。
しかし、お子さんが勉強に集中できないのは、決してやる気がないからや、怠けているからではありません。 ADHDの特性による脳の働き方が、学習においてさまざまな困難さを引き起こしているのです。
この記事では、ADHDの小学生が勉強でつまずく理由から、家庭で今すぐ実践できる具体的な勉強法、親の関わり方のコツまで、網羅的に解説します。
お子さんの特性を正しく理解し、合ったアプローチを見つけることで、勉強への苦手意識を和らげ、持っている力を最大限に引き出すことができます。ぜひ最後まで読んで、お子さんに合ったサポート方法を見つけるヒントにしてください。
ADHD以外にも、ASDやLDなど発達障がいの特性によって学習のつまずき方は異なります。こちらの記事もあわせてご覧ください。
ADHDで勉強できない・集中が続かない理由

ADHDのお子さんが勉強で困難を抱えるのは、その特性に原因があります。主に「不注意」「多動性・衝動性」「実行機能の課題」という3つの側面から、なぜ勉強が難しく感じるのかを理解することが、サポートの第一歩です。
不注意特性|注意が散漫になりやすい
不注意特性とは、注意を持続させたり、必要なことに注意を向けたりすることが苦手な特性です。 この特性があると、勉強中に以下のような様子が見られることがあります。
本人に悪気はなくても、脳の機能として注意をコントロールすることが難しいため、「集中しなさい!」と叱るだけでは解決しにくいのです。
多動性・衝動性特性|じっとしているのが苦手
多動性・衝動性特性とは、静かに座っていたり、自分の行動や感情をコントロールしたりすることが苦手な特性です。 勉強においては、次のような困難につながります。
特に小学生にとっては、長時間椅子に座って静かに勉強すること自体が、非常に大きな苦痛を伴う場合があります。
実行機能の課題|計画や段取りが苦手
実行機能とは、目標を達成するために、計画を立てて段取り良く物事を進める脳の働きのことです。ADHDのお子さんは、この実行機能に課題を抱えていることが多くあります。
「何からやればいいか分からない」という状態なので、勉強を始めること自体のハードルが非常に高くなってしまうのです。
家庭でできるADHDの特性に合わせた勉強法

ADHDの特性を理解した上で、家庭でできる具体的な勉強の工夫を取り入れてみましょう。ここでは、すぐに試せる5つの方法をご紹介します。
時間管理の工夫|タイマーで短時間集中
ADHDのお子さんにとって、終わりの見えない長時間の勉強は苦痛です。タイマーを使って時間を区切り、「短い集中」と「こまめな休憩」を繰り返す方法が効果的です。
課題の工夫|宿題をスモールステップに分解
たくさんの宿題を前にすると、「こんなにできない…」と圧倒されてやる気を失ってしまいます。課題をできるだけ細かく分解(スモールステップ化)し、達成感を積み重ねさせてあげましょう。
暗記の工夫|体や五感を使いながら覚える
じっと机に向かって教科書を読むだけの暗記は、ADHDのお子さんには向きません。体や五感をフル活用して、楽しく覚える工夫を取り入れましょう。
やる気の工夫|勉強のゲーム化とご褒美
勉強を「やらなければいけないこと」から「やると良いことがある楽しいこと」に変える工夫も大切です。
ながら勉強の活用|許可するルールを決める
一般的には「集中できないからダメ」とされがちな「ながら勉強」ですが、ADHDのお子さんにとっては、適度な刺激がある方がかえって集中できる場合があります。 一律に禁止するのではなく、ルールを決めて許可することも検討しましょう。
大切なのは、「何がその子の集中を助けるのか」を見極め、親子で話し合ってルールを決めることです。
思春期が近づくと、反発や言葉のやり取りに悩む場面も増えます。反抗期の親の対応方法 もぜひ参考にしてください。
子どものやる気を引き出す親の教え方と関わり方

勉強法を工夫するのと同じくらい、親の関わり方は重要です。お子さんが安心して勉強に取り組めるよう、以下の4つのポイントを意識してみてください。
結果ではなく取り組んだ過程を褒める
テストの点数や正解数といった「結果」だけを評価していると、子どもは「間違えたらダメだ」「100点を取らないと認めてもらえない」と感じ、挑戦することに臆病になってしまいます。
「10分間、集中して座っていられたね」「難しい問題に諦めずに取り組んだのがすごい!」など、結果に至るまでの「過程」や「努力」を具体的に褒めましょう。小さな成功体験を積み重ねることが、自己肯定感と次へのやる気につながります。
指示は短く具体的に伝える
ADHDのお子さんは、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手です。「宿題をやって、部屋を片付けて、お風呂に入りなさい」といった複数の指示は、混乱の原因になります。
指示は「一つずつ」「短く」「具体的に」伝えるのがコツです。「まず、算数のドリルの5ページ目を開いて」と伝え、それが終わったら「次に、1番の問題を読んでみよう」というように、行動を分解して伝えてあげましょう。
子どもの気持ちに共感し肯定的に接する
勉強を嫌がるお子さんに対して、頭ごなしに「やりなさい!」と叱っても逆効果です。まずは、「そっか、やりたくないんだね」「この問題、難しいよね」と、お子さんの気持ちに寄り添い、共感する姿勢を見せることが大切です。
気持ちを受け止めてもらったという安心感が、「じゃあ、少しだけやってみようかな」という気持ちを引き出すきっかけになります。親が一番の理解者でいることが、お子さんの心の安定につながります。
失敗を責めず一緒に次の対策を考える
ケアレスミスをしたり、問題を間違えたりしたときに、「どうしてこんな簡単なミスをするの!」と責めるのはやめましょう。失敗は誰にでもあることであり、特にADHDの特性上、ミスは起こりやすいものです。
「惜しかったね!どこで間違えちゃったかな?」「次はどうしたら間違えないかな?一緒に作戦を考えよう!」と、失敗を学びの機会と捉え、前向きに次の対策を考えるパートナーになりましょう。
勉強の集中力を高める環境作りと便利グッズ

勉強に集中するためには、環境を整えることも非常に重要です。視覚や聴覚からの刺激を減らし、集中を助けるグッズを活用してみましょう。
机周りの視覚情報を減らす
視界に好きなキャラクターの文房具やおもちゃが入ると、すぐに注意がそれてしまいます。 机の上やその周りには、勉強に必要なもの以外は置かないようにしましょう。
学習時間を可視化するタイマー
「あとどれくらい?」が分からないと、子どもは不安になります。残り時間が視覚的に分かるタイマーは、見通しを立てるのに役立ちます。
外部の音を遮断するイヤーマフ
聴覚が過敏で、些細な物音にも反応してしまうお子さんには、外部の音を物理的に遮断するアイテムが有効です。
手遊びで集中を助けるフィジェット
じっとしているのが苦手で、手や指を動かしていないと落ち着かないお子さんには、手遊びができるフィジェットグッズが集中を助けることがあります。
ただし、かえって遊びに夢中になってしまう場合もあるため、勉強中に使って良いか、どんな時に使うかなどのルールを親子で決めることが大切です。
成長に伴い学習環境の整え方も変わっていきます。発達障がいの中学生向け勉強法 も合わせてチェックしてみましょう。
小学生の勉強に関するよくある悩みQ&A
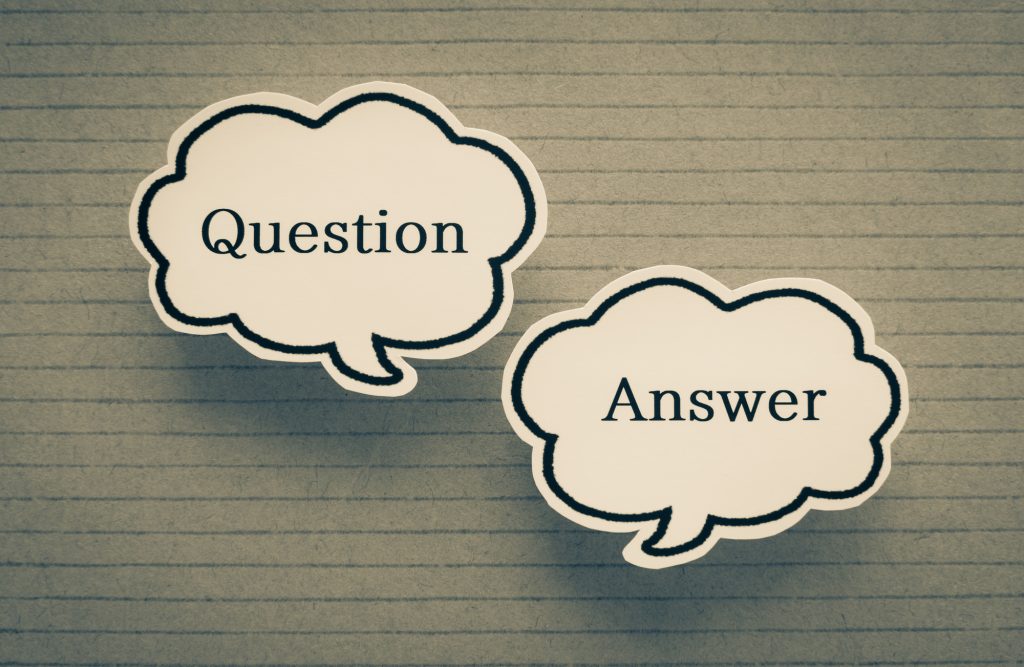
ここでは、保護者の方からよく寄せられる勉強に関する具体的な悩みについて、Q&A形式でお答えします。
宿題を全くやろうとしない時の対処法は?
まずは、始めるためのハードルを極限まで下げることが重要です。 「宿題を全部やる」というゴールが高すぎると、手をつけることすらできません。「まず椅子に5分だけ座ってみよう」「鉛筆を握るだけでOK」「漢字を1文字だけ書いたら終わり」など、絶対にクリアできる目標から始めてみましょう。少しでも行動できたら、大げさなくらい褒めてあげることがポイントです。「やればできる」という感覚を育てていきましょう。
テスト勉強はどう進めればいい?
テスト勉強は、計画性と見通しが鍵になります。 まず、テスト範囲の全体像を把握し、「どの日に何をやるか」をカレンダーやホワイトボードに書き出して「見える化」しましょう。その際も、「1日にドリル5ページ」ではなく、「月曜日は算数のドリルのP10〜11」「火曜日は漢字練習のP5」のように、タスクを細かく具体的にするのがコツです。どこから手をつけていいか分からない場合は、前回間違えた問題の復習から始めると、効率的に弱点を克服できます。
ゲームばかりで勉強しない時のルール作りは?
一方的にゲームを禁止したり取り上げたりするのは、反発を招くだけで逆効果です。 大切なのは、お子さんと一緒にルールを決めることです。「なぜゲームをしたいのか」「どれくらいやりたいのか」という気持ちをヒアリングした上で、「宿題が終わったら30分」「夜8時まで」など、お互いが納得できる明確なルールを作りましょう。タイマーを使って時間を区切る、ルールを守れたらカレンダーにシールを貼るなど、ルールを守ることが楽しくなるような工夫も有効です。
漢字や計算など反復練習を嫌がる時は?
同じことの繰り返しは、ADHDのお子さんにとって苦痛になりがちです。 単純な反復練習ではなく、楽しさや変化を取り入れましょう。
また、量を思い切って減らすことも大切です。「1日ドリル1ページ」ではなく「1日3問」でも、毎日続ければ大きな力になります。できたことをしっかり褒めて、達成感を味わわせてあげましょう。
勉強だけでなく、朝の準備や登校に気が進まない「行き渋り」の様子が見られることもあります。
行き渋りと発達障がいの関係・サポート方法 についても知っておくと安心です。
まとめ
今回は、ADHDの小学生のお子さんが抱える勉強の困難さと、家庭でできる具体的なサポート方法について解説しました。
最後に、最も大切なことをお伝えします。それは、焦らず、お子さんのペースを尊重し、一番の応援団でいてあげることです。
ADHDの特性は、決してマイナスなだけではありません。興味のあることへの驚異的な集中力、ユニークな発想力、エネルギッシュな行動力など、素晴らしい個性に満ちています。
勉強でつまずくことがあっても、それはお子さんの能力が低いからではありません。ただ、学び方のスタイルが少し違うだけです。
この記事で紹介した方法をヒントに、ぜひお子さんと一緒に「これならできそう!」と思えるやり方を探してみてください。試行錯誤の過程そのものが、親子の絆を深め、お子さんの「自分ならできる」という自信を育んでいくはずです。
親が笑顔でいることが、お子さんにとって何よりの安心材料になります。 一人で抱え込まず、時には学校の先生や専門機関にも相談しながら、お子さんの成長を温かく見守っていきましょう。
発達特性に合った学び方を一緒に考えたい方へ。
学研の家庭教師 では、一人ひとりの特性に合わせた個別カリキュラムを提供。不登校・発達障がい専門の「訪問支援室」で、学習・生活・メンタル面までサポートします。お困りごとがあれば一度ご相談ください。




-92.jpg)

-76-320x180.jpg)
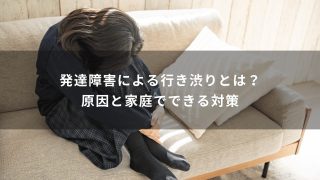
-76.jpg)
-91.jpg)