「最難関中学を目指すならサピックス」という評判を聞き、お子様の入塾を検討されている保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし同時に、「入室テストが難しい」「対策しないと落ちる」といった噂に、不安を感じていらっしゃるかもしれません。
この記事では、サピックスの入室テストに臨むお子様と保護者の方々のために、テストの基本情報から具体的な対策、万が一不合格だった場合の対処法まで、専門家の視点で徹底的に解説します。
この記事を読めば、サピックス入室テストへの漠然とした不安が解消され、合格に向けた具体的な一歩を踏み出せるはずです。
入室テストを理解するには、まずサピックスという塾の特徴を押さえておくことが大切です。
【サピックス】入室テストの基本情報

まずは、サピックスの入室テストがどのようなものか、基本的な情報を押さえておきましょう。
年間テストスケジュールと申込方法
サピックスの入室テストは、主に3月・7月・11月・1月など、年に数回実施されます。特に、新学年が始まる前の11月や1月のテストは、入塾希望者が集中する重要なタイミングです。
- ・主なテスト時期
- ・3月度入室テスト(新学年準備)
- ・7月度入室テスト(夏期講習前)
- ・11月度入室テスト(新学年準備)
- ・1月度入室テスト(新学年準備)
- ・申込方法
- ・テストの申し込みは、サピックス公式サイトのマイページから行います。事前に会員登録を済ませておくとスムーズです。テスト日程は校舎によって異なる場合があるため、必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。 (参考:https://www.sapientica.com/)
テスト科目・出題範囲・試験時間
テストは基本的に国語と算数の2科目で行われます。出題範囲は「学校の教科書レベル」とされていますが、実際にはそれだけでは解けない応用力や思考力が問われる問題が多く含まれます。
「知識の量」だけでなく、「考える力」そのものが試されるのがサピックスの入室テストの大きな特徴です。
学年別の試験時間は以下の通りです。
| 学年 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 新1年生 | 30分 | 30分 |
| 新2年生 | 30分 | 30分 |
| 新3年生 | 30分 | 30分 |
| 新4年生 | 40分 | 40分 |
| 新5年生 | 40分 | 40分 |
| 新6年生 | 40分 | 40分 |
合格基準点とクラス分けの仕組み
保護者の方が最も気になるのが合格基準点(ボーダーライン)ではないでしょうか。
- ・合格基準点は非公開で、毎回変動する
- ・サピックスの入室テストは、決まった点数を取れば合格という「絶対評価」ではありません。受験者全体の成績によって合格ラインが変動する「相対評価」です。そのため、「何点取れば合格」と一概には言えません。
- ・入室テストの成績で最初のクラスが決まる
- ・合格後、テストの成績順にクラスが編成されます。最上位の「α(アルファ)クラス」から、アルファベット順のクラス(A, B, C…)へと続きます。αクラスに入るには、合格基準点を大きく上回る高得点が必要です。
【サピックス】入室テストの難易度と合格率

「サピックスの入室テストは難しい」「落ちる子も多い」という話は本当なのでしょうか。ここでは、テストの難易度と合格率の実態に迫ります。
「落ちる」は本当?学年別の合格率
結論から言うと、入室テストに「落ちる」ことは実際にあります。
サピックスは公式な合格率を公表していませんが、一般的に以下のような傾向があると言われています。
- ・低学年(新1〜3年生)
- ・比較的合格しやすく、定員に空きがあれば多くの子供が入室できます。ただし、油断は禁物です。
- ・新4年生
- ・中学受験の本格的なスタート時期であり、入塾希望者が最も多くなります。そのため競争が激しくなり、合格率は他の学年より低くなる傾向にあります。
- ・高学年(新5〜6年生)
- ・サピックスの授業は進度が速いため、途中から入室するには非常に高い学力が求められます。合格のハードルはかなり高くなります。
テストが「難しい」と言われる理由
サピックスの入室テストが「難しい」と言われるのには、明確な理由があります。
- ・学校の授業範囲を超えた思考力問題
- ・単に計算ができる、漢字を知っているだけでは解けない、パズルのような思考力・発想力が問われる問題が出題されます。
- ・長い問題文と高い読解力
- ・特に算数では、問題文が長く、状況を正確に読み解く国語的な力も必要になります。
- ・スピードと正確性の両立
- ・限られた時間内に多くの問題を処理する必要があるため、素早く正確に解き進める力が求められます。
「対策なし」での合格可能性
「対策なしで合格できる?」という疑問を持つ方もいるでしょう。
地頭が良く、読書習慣やパズルなどで考える訓練が自然とできているお子様であれば、低学年(特に新1・2年生)で対策なしで合格することもあります。
しかし、入塾希望者が増える新3年生、特に新4年生以降は、対策なしでの合格は非常に困難です。ライバルとなる子供たちの多くは、何らかの準備をしてテストに臨みます。合格の可能性を少しでも高めるためには、計画的な対策が不可欠と言えるでしょう。
サピックス以外の塾との比較をしてみることも重要です。お子様に合った塾選びのポイントを理解しておくと、後悔しづらくなります。
【サピックス】学年別入室テスト対策

ここからは、合格を勝ち取るための具体的な対策を学年別に解説します。
新4年生(小3)の対策ポイント
中学受験のスタートラインであり、最も重要な学年です。準備を万全にして臨みましょう。
- ・算数
- ・四則計算の徹底はもちろん、和差算や植木算といった特殊算の基礎に触れておくと有利です。思考力を問う文章題に慣れることが合格への鍵となります。
- ・国語
- ・長文読解が中心です。日頃から少し長めの物語文や説明文を読む習慣をつけましょう。また、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明する記述問題の練習も大切です。
- ・学習習慣の確立
- ・毎日机に向かう習慣をつけることが、この時期の最も重要な対策です。短時間でも良いので、毎日コツコツと続けることが、サピックス入塾後の学習にも繋がります。
新3年生(小2)の対策ポイント
本格的な受験勉強の準備期間と位置づけ、基礎力を固めましょう。
- ・算数
- ・100マス計算などで計算の正確性とスピードを高めましょう。図形問題に苦手意識を持たないよう、パズルやタングラムなどで遊びながら親しむのがおすすめです。
- ・国語
- ・読書習慣を身につける絶好の機会です。子供が興味を持つ本をたくさん読み聞かせたり、一緒に読んだりして、語彙力と読解力の土台を作りましょう。
- ・楽しむ気持ちを育てる
- ・この時期は、勉強を「やらされるもの」ではなく「楽しいもの」と感じさせることが何よりも大切です。知的好奇心を刺激するような問題集や教材を選びましょう。
新1・2年生(幼児・小1)の対策
この学年でのテストは、学力測定というよりも「テスト慣れ」や「地頭の良さ」を見る意味合いが強いです。
- ・ひらがな・カタカナの読み書き、簡単な計算ができれば十分です。
- ・親子での会話や読み聞かせを通して、言葉の力や考える楽しさを育むことが、将来的な学力の伸びに繋がります。
- ・鉛筆を正しく持ち、椅子に座って話を聞くといった基本的な学習姿勢を身につけておくことも大切です。
新5・6年生の対策ポイント
この時期の入室は、サピックス内部生の進度に追いつく必要があるため、非常に高いハードルがあります。
- ・サピックスのカリキュラムは学校の数年先を進んでいるため、そのギャップを埋める学習が必須です。
- ・算数では特殊算のほとんどを、国語では高度な読解・記述力をマスターしていることが前提となります。
- ・入室を目指す場合は、サピックスのカリキュラムに詳しい個別指導塾や家庭教師のサポートを得ながら対策するのが現実的な選択肢となるでしょう。
中学受験に精通した学研の家庭教師なら、サピックス入室テスト特有の出題形式や頻出分野をふまえた指導が受けられます。限られた時間を最大限に活かすためのサポートを検討してみてはいかがでしょうか。
【サピックス】対策に使うべき市販問題集と過去問
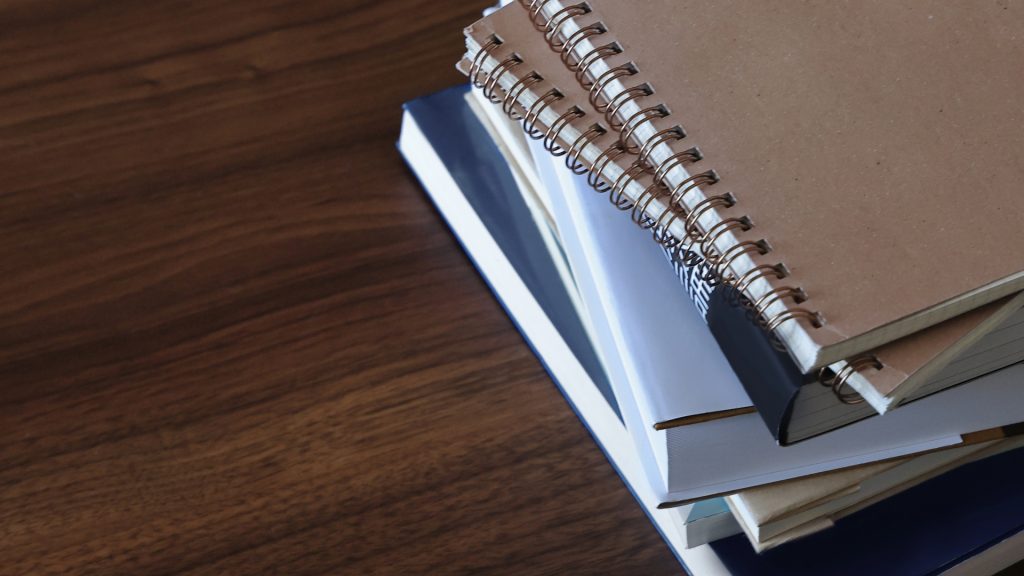
「家庭で対策するには、どんな教材を使えばいいの?」という声にお応えして、おすすめの問題集や過去問の扱いについて解説します。
おすすめの市販問題集・ドリル
サピックスの入室テスト対策として定評のある市販問題集をご紹介します。
- ・きらめき算数脳(サピックスブックス)
- ・サピックス自身が出版している思考力問題集。入室テストの傾向に最も近いとされ、多くの受験生が使用しています。まずはこの一冊から始めるのがおすすめです。
- ・ピグマキッズくらぶ(サピックス通信教育)
- ・サピックスの低学年向け通信教育。良質な問題で思考力を鍛えることができ、入室テスト対策としても非常に有効です。
- ・トップクラス問題集シリーズ(文理)
- ・標準レベルから最高レベルまで段階的に学力を引き上げられる問題集。基礎固めから応用まで幅広く対応できます。
- ・スーパーエリート問題集(文英堂)
- ・思考力を要する難易度の高い問題が多く収録されており、さらに上を目指すお子様向けです。
過去問の入手可否と代替問題
「過去問は手に入らないの?」という質問をよく受けますが、残念ながらサピックスの入室テストの過去問は一切市販されていません。
しかし、以下の方法でテストの傾向に近い問題に触れることは可能です。
- ・サピックス出版の問題集を解く
- ・前述の「きらめき算数脳」などが最も効果的な代替問題となります。
- ・サピックスの季節講習やイベントに参加する
- ・講習内で扱う問題や、一部のイベントで実施されるテストは、入室テストのレベル感を知る良い機会になります。
- ・思考力系の市販問題集に取り組む
- ・様々な出版社の思考力系ドリルを解くことで、初見の問題への対応力が養われます。
国語の対策ポイント
国語は一朝一夕には伸びにくい科目です。日々の積み重ねが大切になります。
- ・長文に慣れる
- ・毎日少しずつでも文章を読む習慣をつけましょう。物語文、説明文など、様々なジャンルの文章に触れることが重要です。
- ・語彙を増やす
- ・文章中に出てきた知らない言葉は、親子で一緒に辞書を引いて意味を確認しましょう。言葉のストックが読解の助けになります。
- ・記述の練習をする
- ・「主人公はなぜそう思ったの?」など、文章の内容について問いかけ、自分の言葉で説明する練習を繰り返しましょう。
算数の対策ポイント
算数は、思考のプロセスを重視して学習を進めましょう。
- ・計算の正確性とスピードを磨く
- ・計算はすべての基本です。ドリルなどを活用し、毎日時間を計って練習しましょう。
- ・思考力問題に楽しんで挑戦する
- ・「きらめき算数脳」などの問題集を使い、「どうすれば解けるかな?」と親子で一緒に考える時間も大切です。すぐに答えを教えず、じっくり考える経験を積ませましょう。
- ・図形問題に親しむ
- ・実際に紙を切ったり折ったり、図形をノートに書き写したりすることで、平面・立体の感覚が養われます。
【サピックス】入室テスト当日から結果発表までの流れ

対策を万全にしたら、あとは本番に臨むだけです。当日の流れと心構えを確認しておきましょう。
当日の持ち物と服装・心構え
- ・持ち物リスト
- ・受験票
- ・筆記用具(濃く書ける鉛筆を複数本、消しゴム)
- ・腕時計(教室に時計がない場合に備え、シンプルなアナログ時計がおすすめ)
- ・ハンカチ、ティッシュ
- ・(必要であれば)上着など体温調節できるもの
- ・服装
- ・温度調節しやすく、リラックスできる普段着が最適です。新しい服や着慣れない服は避けましょう。
- ・心構え
- ・お子様には「満点を取らなくていいんだよ」「わかる問題から丁寧に解こうね」と声をかけ、プレッシャーを和らげてあげてください。保護者のリラックスした態度が、子供の安心に繋がります。
結果通知の時期と確認方法
テストの結果は、通常テスト実施日から3〜5日後に、サピックス公式サイトのマイページ上で発表されます。
合格した場合は、マイページから入室手続きに関する案内を確認できます。クラス分けの結果も同時に通知されます。
【サピックス】入室テストに不合格だった場合の対応

万が一、結果が不合格だったとしても、決して落ち込む必要はありません。次のチャンスに向けて前向きに行動することが大切です。
再テストの機会と申し込み
サピックスの入室テストは、何度でも再挑戦が可能です。不合格だったからといって、二度と受けられないわけではありません。次のテスト日程(例:3ヶ月後、半年後)を目標に、気持ちを切り替えて対策を再開しましょう。
不合格の原因分析と学習計画の見直し
テスト結果には、どの分野で点数が取れなかったのかが示されています。この結果は、お子様の弱点を教えてくれる貴重なデータです。
- ・どの単元が苦手だったのか?
- ・時間配分は適切だったか?
- ・ケアレスミスはなかったか?
これらを親子で冷静に分析し、次の学習計画に活かしましょう。苦手分野を重点的に復習することが、次回の合格に繋がります。
他の塾や通信教育の検討
サピックスは素晴らしい塾ですが、すべてのお子様にとって最適な塾とは限りません。もし何度か挑戦しても難しい場合や、お子様の性格に合わないと感じた場合は、他の選択肢を検討する良い機会と捉えましょう。
早稲田アカデミー、日能研、四谷大塚といった他の大手塾や、Z会のような質の高い通信教育など、お子様が輝ける場所は他にもたくさんあります。
同じ大手塾でも、指導スタイルや雰囲気はそれぞれ異なります。他の塾の特徴はこちら。
まとめ
サピックスの入室テストは、確かに簡単なテストではありません。しかし、その特徴を正しく理解し、お子様の学年や発達段階に合わせた適切な対策を計画的に行えば、合格は決して不可能な目標ではありません。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- ・テストは思考力・応用力が問われる相対評価であり、合格基準点は毎回変動する。
- ・新4年生のテストは特に競争が激しいため、早期からの準備が重要。
- ・過去問は非公開。「きらめき算数脳」などのサピックス系教材が最良の対策問題となる。
- ・不合格でも再挑戦は何度でも可能。結果を分析し、次の対策に活かすことが大切。
何よりも大切なのは、お子様が前向きな気持ちで挑戦できるよう、保護者の方がサポートしてあげることです。この記事が、皆様のサピックス合格への道のりを照らす一助となれば幸いです。




-36.jpg)




-63.jpg)
-62.jpg)