「中学受験の過去問って、いつから始めればいいの?」 「周りの子がもう過去問を解き始めているみたいで、なんだか焦ってしまう…」
小学6年生の秋、本格的な受験シーズンを前に、多くの保護者の方が同じような悩みを抱えています。過去問が志望校合格の鍵を握ることは分かっていても、その最適な開始時期や正しい進め方が分からず、不安に感じてしまいますよね。
この記事では、中学受験のプロとして、そんな保護者の方々の疑問や不安に一つひとつお答えします。
- ・過去問を始めるべき具体的な時期
- ・入試本番までの理想的なスケジュール
- ・成績が伸びる正しい過去問のやり方
- ・取り組むべき年数や回数の目安
この記事を最後まで読めば、過去問演習に関する全ての疑問が解消され、お子様を合格へと導くための明確な道筋が見えてくるはずです。焦らず、一歩ずつ着実に進めていきましょう。
結論:中学受験の過去問は小6の9月から

結論からお伝えすると、中学受験の過去問演習を始める時期は、小学6年生の9月が一般的です。
多くの塾では、夏期講習までに受験に必要な単元のおおよその学習を終えます。そのため、基礎固めが一段落し、入試本番までの残り時間も十分にある9月が、過去問演習をスタートするのに最適なタイミングとされています。
もちろん、これはあくまで一般的な目安です。お子様の学習状況や志望校のレベルによって、最適な開始時期は少しずつ異なります。
過去問対策を始める前に、志望校の決め方や学習計画について整理しておくことも重要です。あわせてこちらもご覧ください。
志望校のレベル別で見る開始時期
すべての受験生が、一律に9月からスタートするわけではありません。志望校の難易度によって、適切な開始時期は変わってきます。
- ・難関校・上位校を目指す場合: 基礎力が高く、塾のカリキュラムも前倒しで進んでいるお子様は、夏休み頃から少しずつ過去問に触れ始めるケースも少なくありません。早い段階で志望校の出題傾向を掴み、じっくりと対策に時間をかけることができます。
- ・中堅校を目指す場合: 9月からのスタートが最も標準的なペースです。焦る必要は全くありません。まずは夏休みまでに学習した基礎知識の定着を最優先し、9月から計画的に過去問演習へ移行しましょう。
基礎固めが終わっていない場合の進め方
もし、9月になっても「まだ基礎的な単元に不安が残っている…」という場合は、過去問演習よりも基礎固めを優先してください。
土台がぐらついたまま過去問を解いても、思うように点数が取れず、お子様の自信を失わせてしまうだけです。過去問は、あくまで基礎力が身についていることを前提とした「実践演習」です。
ただし、志望校の傾向を知るために、一度だけ最新年度の過去問を解いてみるのは良い方法です。どの単元が頻出で、自分に何が足りないのかを把握する「実力診断」として活用し、その後の学習計画に役立てましょう。本格的な演習は、基礎が固まった10月からでも決して遅くはありません。
過去問演習の効果を最大化するには、まず算数の基礎力を固めておくことが不可欠です。偏差値が上がらない原因と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
基礎の定着に不安がある場合は、中学受験生専門の指導で弱点を効率的に補える「学研の家庭教師」を活用するのも一つの方法です。学習のペース管理や弱点のフォローまで、お子さまに合わせてサポートします。
9月開始で間に合わない?と焦る必要はない理由
「本当に9月からで間に合うの?」と不安に思うかもしれませんが、心配は無用です。多くの受験生が9月から過去問演習をスタートします。
大切なのは、始める時期よりも「正しいやり方で、どれだけ質を高められるか」です。ただ量をこなすだけでは、成績は伸びません。後ほど詳しく解説する効果的な解き直しや分析をしっかり行えば、9月からのスタートでも合格力を十分に高めることができます。
周りと比べて焦るのではなく、お子様のペースで着実に進めていくことが何よりも重要です。
「低学年から準備していないともう遅いのでは?」と不安に思う保護者も少なくありません。実際には、小学6年生から受験準備を始めても十分に間に合うケースがあります。その具体的な進め方については、こちらの記事をご覧ください。
中学受験│過去問演習の年間スケジュールと進め方

過去問演習は、やみくもに進めても効果は半減してしまいます。入試本番から逆算し、時期ごとに目標を設定して計画的に取り組むことが合格への近道です。
ここでは、9月開始を想定した標準的な年間スケジュールをご紹介します。
9月〜10月:基礎と並行し週1ペースで
この時期の目標は、志望校の出題傾向を把握し、本番の時間配分に慣れることです。
- ・ペース: 週に1年分を目安に、無理のない範囲で進めましょう。まだ基礎学習や塾の課題も多いため、過去問演習とのバランスを取ることが大切です。
- ・取り組み方: まずは第一志望校の過去問から始め、問題形式や難易度、頻出単元などを肌で感じましょう。この段階では、点数に一喜一憂する必要はありません。時間内に解ききれなくても大丈夫です。
11月〜12月:実践力を高める集中期間
この時期は、合格者平均点を超えることを目標に、実践力を一気に高める重要な期間です。
- ・ペース: 週に2〜3年分を目安にペースを上げ、第一志望校だけでなく併願校の過去問にも取り組み始めましょう。
- ・取り組み方: 「解く」こと以上に「解き直し」に時間をかけ、自分の弱点を徹底的に分析・克服していきます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを明確にし、類題を解くなどして知識の定着を図りましょう。
1月〜入試直前:最終調整と弱点克服
入試直前期の目標は、新しい知識を詰め込むことではなく、これまで培ってきた力を本番で最大限発揮するための最終調整です。
- ・ペース: 体調管理を最優先し、無理な計画は立てません。
- ・取り組み方: これまで解いた過去問で間違えた問題や、間違いノートを見直す作業が中心となります。最新年度の過去問に挑戦して「捨て問」を見極める練習をしたり、本番さながらのシミュレーションをしたりするのも効果的です。自信を持って本番に臨めるコンディションを整えることを最優先しましょう。
中学受験│過去問の正しいやり方と効果的な使い方
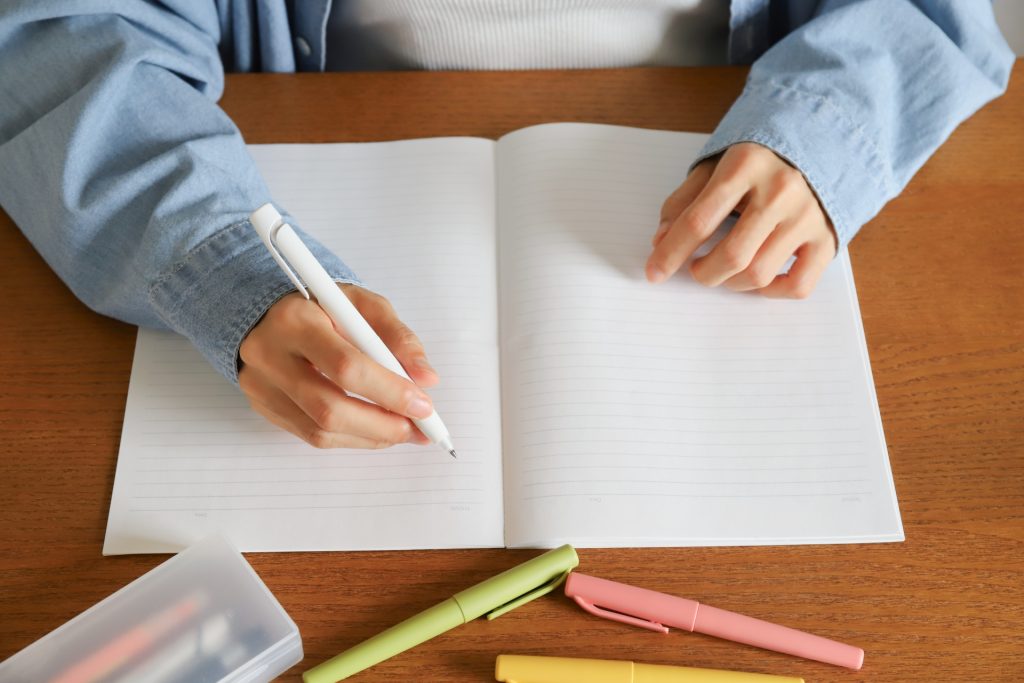
過去問演習で最も大切なのは、解きっぱなしにしないことです。点数を上げるためには、「解く→分析・解き直し→繰り返す」というサイクルを回すことが不可欠です。
正しい過去問の取り組み方を知ることは、合格への大きな一歩です。詳しい解き方のポイントはこちらの記事も参考にしてください。
1回目:時間を計り本番同様に解く
過去問に初めて取り組む際は、本番の試験と全く同じ環境を再現することが重要です。
- ・準備するもの
- ・筆記用具
- ・志望校の解答用紙(公式サイトからダウンロードできる場合が多いです)
- ・時計(ストップウォッチ)
- ・ルール
- ・必ず本番と同じ制限時間を計り、途中で中断しない。
- ・辞書や参考書は見ない。
- ・静かで集中できる環境で行う。
この緊張感が、時間配分の感覚を養い、本番で実力を発揮する練習になります。事前に合格最低点を調べておき、それを意識しながら解くのも良いでしょう。
効果的な解き直しと間違いノートの作り方
過去問演習の成果は、解き直しの質で決まると言っても過言ではありません。以下の手順で、丁寧な解き直しを心がけましょう。
- ・1. 丸付けと点数計算: まずは自己採点をして、現在の実力を客観的に把握します。配点が分からない場合は、正答率で評価しても構いません。
- ・2. 間違いの原因分析: 間違えた問題一問一問について、なぜ間違えたのかを分析します。原因は主に以下の3つに分類できます。
- ・知識不足:そもそも解き方を知らなかった、公式を忘れていた。
- ・ケアレスミス:計算ミス、漢字の間違い、問題文の読み間違い。
- ・時間不足:時間が足りずに解けなかった、焦ってミスをした。
- ・3. 解説を読んで理解する: 解説をじっくり読み、正しい解法を理解します。「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で説明できるレベルまで落とし込みましょう。
- ・4. 自力で再度解いてみる: 解説を理解したら、何も見ずに自分の力でもう一度解いてみます。ここでスラスラ解ければ、その問題は克服できたと言えるでしょう。
これらの分析結果を記録するために「間違いノート」を作成するのがおすすめです。ノートに問題のコピーを貼り、間違えた原因、正しい解法、注意すべきポイントなどを書き込んでおけば、自分だけの最強の参考書になります。
2回目以降:時間内に満点を目指す
同じ年度の過去問に2回目、3回目と取り組む際は、「時間内に満点を取る」という意識で臨むことが大切です。
1回目で解けなかった問題を確実に解けるようにするのはもちろん、解けた問題も「もっと速く、正確に解けないか」を考えながら取り組みます。この練習を繰り返すことで、解答のスピードと精度が飛躍的に向上し、本番での得点力に繋がります。
中学受験│過去問は何年分・何校分・何回解く?

「過去問は、一体どれくらいの量をこなせばいいの?」というのも、よくある質問です。ここでは、取り組むべき年数・校数・回数の目安をご紹介します。
第一志望校は最低5年、できれば10年分
最も力を入れるべき第一志望校の過去問は、最低でも5年分、可能であれば10年分に取り組むのが理想です。
多くの年数に取り組むことで、問題形式や頻出分野といった一貫した「傾向」だけでなく、数年単位で起こる「変化」まで掴むことができます。これにより、あらゆるパターンに対応できる盤石な対策が可能になります。
併願校は3〜5年分を目安に取り組む
併願校については、受験する可能性の高さ(優先順位)に応じて量を調整しましょう。
合格の可能性が高い「安全校」や、第一志望校と問題傾向が似ている学校であれば3年分程度でも十分な場合があります。一方で、合格ラインぎりぎりの「チャレンジ校」や、第一志望校とは出題傾向が大きく異なる学校については、5年分ほど取り組んでおくと安心です。
繰り返し解く回数は最低2〜3周が基本
一度解いただけでは、知識はなかなか定着しません。同じ年度の過去問は、最低でも2周、できれば3周繰り返すことを基本としましょう。
- ・1周目:力試しと傾向把握
- ・2周目:解けなかった問題の克服と知識の定着
- ・3周目:解答のスピードと精度を高め、完璧に仕上げる
このサイクルを回すことで、過去問の効果を最大限に引き出すことができます。
中学受験│過去問(赤本)はいつ買う?発売時期

過去問演習に欠かせないのが、通称「赤本」です。購入時期についても知っておきましょう。
赤本の発売時期は4月〜7月頃
赤本とは、主に声の教育社や英俊社から出版されている、中学校の過去入学試験問題集の通称です。
これらの過去問集は、例年4月頃から7月頃にかけて順次発売されます。志望校の赤本がいつ発売されるか気になる場合は、出版社の公式サイトで確認できます。
(参考:声の教育社 https://www.koeno.co.jp/)
購入タイミングは夏休み明けの9月でOK
発売されるとすぐに買いたくなるかもしれませんが、実際に過去問演習を始める9月頃に購入すれば全く問題ありません。
早く手に入れても、本格的に使い始めるのは秋以降になることがほとんどです。人気校の赤本が売り切れることは滅多にありませんが、どうしても心配な場合は夏休み中に購入しておくと良いでしょう。
最新版だけでなく過年度分も入手しよう
最新版の赤本には、通常3〜5年程度の過去問しか収録されていません。第一志望校の過去問に10年分取り組みたい場合などは、最新版だけでは足りなくなります。
その場合は、古本屋やフリマアプリなどを活用して、過年度版の赤本を探す必要があります。また、通っている塾によっては過去の赤本を貸し出してくれる場合もあるので、一度相談してみるのも良いでしょう。
中学受験│過去問演習のよくある悩みと解決策

過去問演習を進めていると、さまざまな壁にぶつかります。ここでは、多くの受験生親子が抱える悩みとその解決策をご紹介します。
点数が取れない・解けない時の対処法
「過去問を解き始めたけど、全然点数が取れない…」これは、誰もが通る道です。最初は合格最低点に遠く及ばなくても、全く気にする必要はありません。大切なのは、その後の対処です。
- ・原因を分析する: 点数が取れない原因は、「基礎知識の不足」なのか、それとも「問題形式への不慣れ」なのかを見極めましょう。
- ・基礎に戻る勇気を持つ: もし基礎力不足が原因なら、遠回りに見えても、該当単元の復習に戻ることが最も効果的です。
- ・満点を目指さない: 中学受験は満点を取る必要はありません。合格最低点を意識し、「解けるはずの問題」を確実に得点できているかを確認しましょう。
- ・解ける問題から解く練習: 難しい問題に時間を使いすぎず、自分が解ける問題から手をつけて得点を確保する練習も重要です。
計画通りに進まず間に合わない場合
「計画を立てたのに、思うように進まない…間に合わないかも…」と焦ってしまうこともあるでしょう。そんな時こそ、冷静に優先順位をつけることが大切です。
- ・第一志望校を最優先する: まずは第一志望校の対策に集中しましょう。併願校の対策は、その次です。
- ・取り組む内容を絞る: すべての年度を完璧にこなすのが難しい場合は、「直近3年分だけは3周する」「苦手な算数だけは5年分解く」など、やるべきことを絞りましょう。
- ・完璧を目指さない: 計画通りに進まないことに罪悪感を抱く必要はありません。限られた時間の中で、合格の可能性を1%でも上げるために何ができるかを考え、柔軟に計画を修正していきましょう。
いつまでに終わらせるべきかという目標
「過去問は、いつまでに終わらせればいいの?」という疑問もよく聞かれます。
一つの目安として、一通りの過去問演習(1周目)は12月中に終えることを目標にすると良いでしょう。そして、1月はこれまで間違えた問題の解き直しや、体調管理を含めた最終調整の期間と位置づけるのが理想的なスケジュールです。
ただし、これもあくまで目安です。12月末までに終わらせることを目標に計画を立てることで、余裕を持った直前期を迎えることができます。
まとめ
今回は、中学受験の過去問を始める時期や、効果的な使い方について詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- ・開始時期の基本: 過去問演習は、小学6年生の9月から始めるのが一般的です。基礎固めが終わっていない場合は、焦らず基礎を優先しましょう。
- ・量の目安: 第一志望校は最低5年分(できれば10年分)、併願校は3〜5年分を目安に取り組みましょう。
- ・質の高い演習: 点数に一喜一憂せず、本番同様の環境で解き、丁寧な「解き直し」で間違えた原因を分析することが最も重要です。
- ・繰り返しの重要性: 同じ年度の過去問を最低2〜3周繰り返すことで、知識が定着し、得点力がアップします。
- ・焦らないこと: 計画通りに進まなくても、周りと比べても焦る必要はありません。お子様のペースを大切に、優先順位をつけて着実に取り組みましょう。
過去問演習は、お子様が自分の実力と向き合い、大きく成長できる貴重な機会です。保護者の方は、点数という結果だけでなく、その過程でのお子様の頑張りを認め、励まし、一番のサポーターでいてあげてください。
この記事が、皆様の合格への道のりを照らす一助となれば幸いです。




-40.jpg)
-61-320x180.jpg)

-55-320x180.jpg)
-41-320x180.jpg)
-61.jpg)
-41.jpg)