中学受験の天王山とも言われる小学6年生の夏休みを迎え、「いよいよ過去問に挑戦!」と考えているご家庭も多いのではないでしょうか。 しかし、いざ過去問を前にすると、「いつから始めればいいの?」「何年分解けば合格できる?」「思うように点数が取れないけど、このままで大丈夫?」といった、たくさんの疑問や不安が湧いてくるものです。
過去問演習は、ただ問題を解くだけでは効果が半減してしまいます。正しいやり方で、計画的に取り組むことが、志望校合格への道を切り拓く鍵となります。
この記事では、中学受験における過去問演習の専門家として、そんな保護者の皆様の悩みに応えるための「過去問のやり方完全ガイド」をお届けします。
- ・過去問を始めるべき最適な時期と量
- ・合格を引き寄せる正しい進め方4ステップ
- ・点数が取れない時の具体的な対処法
- ・時期別の学習スケジュール
これらの情報を網羅的に解説しますので、ぜひ最後までお読みいただき、お子様の過去問演習を成功に導いてください。
中学受験│過去問はいつから何年分?時期と量の目安

過去問演習を始めるにあたって、まず押さえておきたいのが「いつから、どのくらいの量をこなすべきか」という点です。やみくもに始めるのではなく、戦略的な計画を立てることが、限られた時間を有効に使うための第一歩です。
過去問を始める時期について詳しくは、こちらの記事で解説しています
開始時期は小学6年生の夏休みから9月
過去問演習を始める最適な時期は、小学6年生の夏休みから9月頃が一般的です。
多くの塾では、夏休み前までに中学受験に必要な一通りの単元学習を終えます。基礎が固まっていない段階で過去問に挑戦しても、解けない問題が多すぎてしまい、お子様の自信を失わせる原因になりかねません。
まずは基礎学力の定着を最優先し、その上で夏休み以降に本格的な過去問演習へ移行するのが最も効率的な進め方です。9月から過去問を始めても、入試本番までには十分な時間がありますので、焦る必要はありません。
第一志望校は最低10年分を3回繰り返す
最も力を入れるべき第一志望校の過去問は、最低でも10年分は用意しましょう。これを、最低3回繰り返して解くことを目標にしてください。
- ・なぜ10年分?: 学校によっては数年単位で出題傾向が変わることがあります。長期間の過去問を分析することで、一貫した出題方針や近年の傾向変化まで掴むことができます。
- ・なぜ3回繰り返す?・ 回数ごとに目的が異なります。
- ・1回目: 時間を計って解き、学校の出題傾向、難易度、問題量を知る(実力診断)
- ・2回目: 苦手分野を克服できているか確認し、時間配分を意識して解く練習
- ・3回目: 解法を完全に定着させ、ケアレスミスをなくし、合格者平均点以上を目指す
併願校は3〜5年分を1〜2回が目安
併願校については、お子様の学力や志望順位に応じて調整しますが、一般的には3〜5年分を1〜2回解いておけば十分でしょう。
全ての学校で10年分を3回繰り返すのは、時間的に非常に困難です。あくまで最優先は第一志望校であることを念頭に置き、併願校対策は効率的に進めることが大切です。
ただし、出題形式が独特な学校や、第一志望校と傾向が大きく異なる学校を併願する場合は、少し多めに演習しておくと安心です。
過去問対策を効果的に進めるには、志望校選びの軸を明確にしておくことも大切です。学校選びの考え方はこちらの記事で整理しています。
中学受験│過去問演習の正しい進め方4ステップ

過去問の効果を最大限に引き出すためには、正しい手順で取り組むことが不可欠です。ここでは、「準備」「実践」「分析」「復習」という4つのステップに分けて、具体的な進め方を解説します。
準備:過去問の入手とコピー・整理のやり方
まずは過去問演習をスムーズに進めるための準備を整えましょう。
- ・過去問の入手: 「声の教育社」や「東京学参」から出版されている、いわゆる「赤本」を書店やオンラインで購入するのが一般的です。解説が詳しいものを選ぶと、復習の際に役立ちます。
- ・過去問のコピー: 原本に直接書き込むのではなく、必ずコピーして使いましょう。実際の入試問題に近いB4サイズに拡大コピーするのがおすすめです。解答用紙も、本番と同じサイズに拡大すると、記述スペースの感覚を掴む練習になります。
- ・ノートとファイルの準備: 「過去問演習ノート(直しノート)」を1冊用意しましょう。また、解き終わった問題と解答用紙は、学校別・年度別にファイルで整理しておくと、後で見返す際に非常に便利です。
実践:本番同様の環境で時間を計って解く
いよいよ過去問を解く段階です。ここでは「本番さながらの環境」を徹底することが重要です。
- ・時間を厳守する: 必ずタイマーを使い、試験時間と全く同じ時間で解きます。時間が来たら、たとえ途中でも鉛筆を置きましょう。
- ・本番に近い環境を作る: 静かな部屋で、机の上には筆記用具と問題・解答用紙以外は置かないようにします。本番の緊張感をシミュレーションすることが目的です。
- ・途中で答えを見ない: 分からない問題があっても、すぐに答えを見たり、保護者がヒントを出したりするのはNGです。最後まで自分の力で解き切る経験が、本番での粘り強さにつながります。
分析:自己採点と間違いの原因分析方法
解き終わったら、すぐに自己採点と分析に移ります。ここが学力向上の最も重要なポイントです。
まずは、赤ペンで丸つけをします。配点が記載されていない場合は、大まかに問題数で総得点を割って計算するか、塾の先生に相談してみましょう。
そして、点数に一喜一憂するのではなく、「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析します。間違いの原因は、主に以下の4つに分類できます。
- ・知識不足: 用語や公式を覚えていなかった、解法を知らなかった。
- ・ケアレスミス: 計算ミス、漢字の書き間違い、問題文の読み間違いなど、注意すれば防げたミス。
- ・時間不足: 時間が足りずに、手をつけることができなかった。
- ・応用力不足: 知識はあるものの、問題の意図を汲み取れなかったり、複雑な条件を整理できなかったりした。
この原因分析こそが、次の復習の質を大きく左右します。
復習:効果的な解き直しと直し方のコツ
分析が終わったら、最後の仕上げである「復習」です。過去問は解きっぱなしにせず、解き直しまでを1セットと考えましょう。
- ・間違えた問題は必ず解き直す: 答えをただ写すのではなく、解説をよく読み、理解した上で、もう一度自力で解けるか確認します。
- ・「直しノート」を作成する: 間違えた問題をノートに貼り、「間違いの原因」と「正しい解法・ポイント」を自分の言葉でまとめます。このノートが、自分だけの最強の参考書になります。
- ・正解した問題も見直す: 偶然正解した問題や、もっと効率的な解き方がなかったかを確認することも大切です。特に算数では、よりスマートな解法を身につけることで、試験時間を短縮できます。
特に算数の得点力は合否を大きく左右します。偏差値が伸び悩む原因と具体的な対策については、こちらの記事も参考にしてください。
中学受験│過去問が解けない・点数が取れない時の対処法
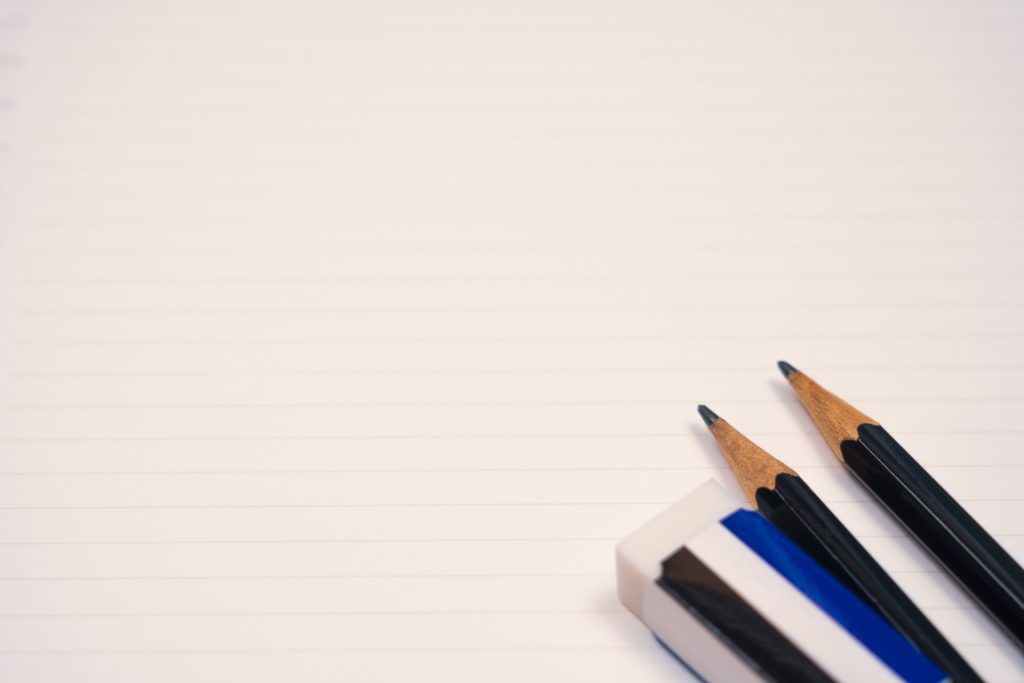
「いざ過去問を解いてみたものの、合格点にまったく届かない…」これは、多くの受験生と保護者が直面する壁です。しかし、点数が取れないこと自体は問題ではありません。大切なのは、その後の対処法です。
初めての点数が合格点に届かないのは普通
まず、保護者の皆様に知っておいていただきたいのは、初めて解く過去問で合格点に届かないのは当たり前だということです。
特に演習を始める9月頃は、まだ全範囲の知識が定着しきっていなかったり、その学校特有の出題形式に慣れていなかったりします。
初めての過去問演習の目的は、高得点を取ることではなく、「志望校の傾向を知り、自分の弱点を発見すること」です。点数の低さに落胆せず、「ここが伸びしろだね」と前向きな声かけをしてあげてください。
原因別|基礎力不足と時間配分の見直し
点数が伸び悩む原因を冷静に分析し、それぞれに合った対策を講じましょう。
- ・基礎力不足が原因の場合: 特定の単元で失点が多い場合は、勇気を持ってその単元まで戻り、テキストや問題集で復習しましょう。焦って過去問ばかり解き続けても、土台がなければ応用力は身につきません。
- ・時間配分が原因の場合: 「あと10分あれば解けたのに…」という場合は、時間配分の戦略を見直す必要があります。大問ごとの目標時間を設定したり、解けそうにない問題は後回しにする「捨てる勇気」を身につけたりする練習が効果的です。
- ・問題形式に慣れていない場合: これは、演習量をこなすことで解決できます。同じ学校の過去問を繰り返し解くことで、問題のパターンや時間配分の感覚が自然と身についていきます。
子供のやる気を引き出すための関わり方
過去問が解けず、お子様がやる気をなくしてしまうこともあります。そんな時こそ、保護者のサポートが重要になります。
- ・結果だけでなくプロセスを褒める: 点数という結果だけを見るのではなく、「最後まで諦めずに頑張ったね」「この前の間違いが、今日は解けるようになったね」など、努力の過程を具体的に褒めてあげることが大切です。
- ・感情的に叱らない: 点数が悪いからといって、「こんな点数で合格できるわけないでしょ!」などと感情的に叱るのは絶対にやめましょう。お子様を追い詰めるだけでなく、過去問への苦手意識を植え付けてしまいます。
- ・一緒に計画を立て、伴走する: 「次はこの単元を復習してから、もう一度挑戦してみようか」というように、お子様と一緒に今後の計画を立て、保護者も伴走する姿勢を見せることで、お子様は安心して学習に取り組むことができます。
過去問を繰り返しても点数が伸びず不安な場合は、専門家のサポートを取り入れるのも有効です。学研の家庭教師なら、志望校に合わせたカリキュラムで効率的に対策が進められます。
中学受験│時期別・過去問のスケジュールと進め方

過去問演習は、時期によってその目的や重点を置くべきポイントが異なります。戦略的にスケジュールを立て、計画的に進めることで、学習効果を最大化できます。
夏休み(〜8月):傾向把握と1周目の開始
この時期の目的は、「敵を知ること」です。 まずは第一志望校の過去問を1〜2年分解いてみましょう。合格点を取る必要はありません。どんな問題が出るのか、時間は足りるのか、難易度はどのくらいか、といった志望校の全体像を肌で感じることが目標です。ここで見つかった大きな苦手単元は、夏休み中に集中的に復習しておきましょう。
秋(9月〜11月):本格的な演習と弱点克服
この時期は、過去問演習を本格化させ、学力を一気に引き上げる最も重要な期間です。 週に1〜2年分のペースで第一志望校の過去問(1周目)を進め、間違えた問題の解き直しと、関連単元の復習にじっくり時間をかけます。10月頃からは、併願校の過去問にも着手し始めましょう。この時期の頑張りが、合格を大きく左右します。
直前期(12月〜1月):時間配分と戦略の最終調整
入試本番が目前に迫るこの時期は、新しい問題に手を出すよりも、これまでの復習と反復演習に重点を置きます。
- ・第一志望校の過去問の2周目、3周目に取り組む
- ・本番と全く同じ時間で解き、時間配分の最終チェックを行う
- ・「直しノート」を繰り返し見直し、知識を完璧に定着させる
体調管理に万全を期しながら、自信を持って本番に臨むための最終調整を行いましょう。
中学受験の過去問に関するQ&A

最後に、保護者の皆様からよく寄せられる過去問に関する質問にお答えします。
Q. 過去問演習が終わらない場合は?
A. 優先順位をつけて、すべてを完璧にやろうとしないことが大切です。
計画通りに進まないことはよくあります。そんな時は、第一志望校の対策を最優先してください。併願校については、志望順位の低い学校の演習年数を減らしたり、2周目を省略したりするなど、柔軟に計画を修正しましょう。「終わらせること」が目的ではなく、「合格に必要な力をつけること」が目的です。
Q. 配点がわからない時の採点方法は?
A. まずは塾の先生に相談するのが最も確実です。
それが難しい場合は、以下の方法で概算点を出すことができます。
- ・選択問題: 総得点と問題数から、1問あたりの配点を大まかに計算する。
- ・記述問題: 学校の採点基準は公表されていませんが、解答の要素(キーワードや必須の論理展開)がどれだけ含まれているかに応じて、自分で基準を決めて部分点を与えます。厳しめに採点しておくのが無難です。
Q. 2回目以降の取り組み方は?
A. 1回目とは目的意識を変えて取り組むことが重要です。
- ・2回目の目的 1回目で間違えた問題が解けるようになっているか、弱点が克服できているかを確認します。また、より実践的な時間配分を意識して、合格者平均点を目指します。
- ・3回目の目的 解法パターンを体に染み込ませ、ケアレスミスをゼロに近づけるための最終確認です。満点を取るつもりで臨みましょう。
Q. 何校分の過去問を解くべきですか?
A. 一般的には3〜5校程度が目安ですが、お子様の学習状況やキャパシティによります。
受験パターン(チャレンジ校、実力相応校、安全校)にもよりますが、多くの学校の過去問に手を出しすぎると、一つひとつが中途半端になりがちです。第一志望校と、出題傾向が似ている併願校を優先し、お子様の負担にならない範囲で計画を立てましょう。
低学年から準備をしていないご家庭でも、まだ十分に巻き返しは可能です。小6からの受験準備についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ
今回は、中学受験における過去問の正しいやり方について、網羅的に解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- ・開始時期と量: 小学6年生の夏休み〜9月に開始し、第一志望校は最低10年分を3回、併願校は3〜5年分を1〜2回が目安です。
- ・正しい進め方: 「準備→実践→分析→復習」の4ステップを徹底することが、学力向上の鍵です。特に「分析」と「復習」に時間をかけましょう。
- ・点数が取れない時: 初めての点数が低くても焦る必要はありません。原因を冷静に分析し、基礎に戻る勇気を持つことが大切です。保護者は結果を叱るのではなく、プロセスを褒めて伴走してあげてください。
- ・計画的なスケジュール: 夏休みは「傾向把握」、秋は「本格演習と弱点克服」、直前期は「最終調整」と、時期ごとに目的意識を持って取り組みましょう。
過去問演習は、お子様にとって苦しい時期かもしれません。しかし、志望校の出題者からの「こんな生徒に入学してほしい」というメッセージを読み解き、合格に近づくための最も効果的な学習法です。
この記事を参考に、親子で力を合わせて過去問演習を乗り越え、笑顔の春を迎えられることを心から応援しています。




-41.jpg)
-40-320x180.jpg)
-61-320x180.jpg)


-55-320x180.jpg)
-40.jpg)
-42.jpg)