「日能研の授業、うちの子には早すぎるかも…」「宿題が終わらず、親子で毎日ヘトヘト…」 大切なお子様を想い、中学受験のために日能研へ通わせ始めたものの、思うように学習が進まない様子を見て、このように悩んでいませんか?
「このままで本当に大丈夫だろうか」「もしかして、うちの子だけがついていけていないのでは?」と、不安や焦りを感じ、孤独感を抱えている保護者の方は少なくありません。特に、学習が本格化する新4年生や、受験の天王山といわれる5年生では、その悩みは一層深くなりがちです。
この記事では、日能研の元スタッフや現役講師、そして同じ悩みを乗り越えてきた多くの保護者の声をもとに、お子様が「ついていけない」と感じる原因を徹底分析します。
さらに、学年別・科目別の具体的な対策から、家庭でできるサポート方法、そして「転塾」や「中学受験そのものを見直す」という選択肢まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、お子様に合った次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。
日能研で「ついていけない」と感じる5つの原因

まず、なぜお子様が日能研の学習でつまずいてしまうのか、その背景にある主な原因を5つ見ていきましょう。原因を正しく理解することが、解決への第一歩です。
授業のスピードと進度の速さ
日能研の授業は、中学受験に必要な膨大な範囲を限られた時間で終わらせるため、非常にスピーディーに進みます。 特に、一度学習した単元を期間を空けて再び学ぶ「スパイラル方式」というカリキュラムを採用しているため、一つひとつの単元をじっくり深掘りする時間が少ないのが特徴です。
理解が追いつかないまま次の単元に進んでしまい、「分かったつもり」が積み重なることで、徐々についていけなくなるケースが多く見られます。
授業進度の速さは、多くの保護者が感じる悩みのひとつです。日能研全体の特徴やカリキュラムの仕組みを理解しておくと、つまずきの背景が見えやすくなります。
宿題(栄冠への道)の量と難易度
日能研の家庭学習の要となる教材が「栄冠への道」です。これは授業内容の定着を図るための重要な問題集ですが、その量が多く、難易度の高い問題も含まれているため、多くのお子様や保護者にとって大きな負担となっています。
特に、共働きのご家庭や、お子様が他の習い事をしている場合、宿題をこなすだけで手一杯になり、苦手分野の復習まで手が回らないという状況に陥りがちです。
基礎定着不足による応用問題の壁
授業では理解できたように感じても、基礎的な知識や解法が完全に定着していないと、応用問題になった途端に手も足も出なくなります。
日能研のテストでは、単なる知識の暗記だけでは解けない思考力を問う問題が多く出題されます。基礎が曖昧なままでは、これらの問題に対応できず、成績が伸び悩む大きな原因となります。
クラス昇降のプレッシャーとモチベーション低下
日能研では、定期的(多くは2ヶ月に1回)に実施される「全国公開模試」の成績によってクラスが変動します。クラスが上がることは大きな喜びと自信につながりますが、逆にクラスが下がってしまうと、お子様は大きなプレッシャーや劣等感を感じてしまいます。
このクラス降格がきっかけで、「自分はできないんだ」と思い込み、勉強へのモチベーションを失ってしまうお子様は少なくありません。
カリキュラムが合わない可能性(無駄が多いと感じる点)
日能研のカリキュラムは、幅広い範囲を網羅的に学べるというメリットがある一方、お子様の志望校や学力レベルによっては「無駄が多い」と感じられることがあります。
例えば、最難関校を目指しているわけではないのに、難しすぎる問題に時間を費やしてしまったり、逆に基礎をじっくり固めたいのに、次々と新しい単元に進んでしまったりと、カリキュラムとお子様のニーズが合っていないケースです。
【学年別】日能研でついていけない壁の乗り越え方

「ついていけない」という悩みは、学年によってその内容や深刻さが異なります。ここでは、各学年で直面しがちな「壁」と、それを乗り越えるための対策を解説します。
予科教室・新4年生の壁と対策
本格的な中学受験勉強がスタートするこの時期は、「学習習慣の確立」が最大のテーマです。
- ・壁: 小学校とは全く異なる授業のスピードや宿題の量に戸惑い、勉強のペースを掴めない。ノートの取り方や復習の仕方が分からず、非効率な学習に陥りがち。
- ・対策まずは完璧を目指さず、塾のサイクルに慣れることを最優先しましょう。
- ・学習計画を立てる: 「月曜日は算数の栄冠、火曜日は国語の復習」など、親子で1週間の学習計画を立て、勉強を習慣化させましょう。
- ・ノートの取り方を指導する: 先生の板書を写すだけでなく、自分が分からなかった点やポイントをメモする習慣をつけさせることが大切です。
- ・基礎の徹底: 難しい応用問題に手を出す前に、授業で習った基本問題の解き直しを徹底し、基礎固めに専念しましょう。
5年生の壁と対策(天王山)
5年生は、学習内容の質・量ともに急激に増え、「中学受験の天王山」と呼ばれます。
- ・壁: 算数では「割合」「速さ」など抽象的な概念が増え、理科や社会も知識の暗記だけでは対応できない問題が増加。苦手科目が一気に表面化し、成績の差が開きやすい時期。
- ・対策苦手分野を放置せず、効率的な学習で乗り切ることが重要です。
- ・苦手分野の特定と克服: 公開模試の結果を分析し、どの単元が苦手なのかを正確に把握しましょう。夏休みなどの長期休暇を利用して、集中的に復習することが効果的です。
- ・学習の優先順位付け: 全ての課題を完璧にこなすのは不可能です。子どもの学力に合わせて「これは必ずやるべき問題」「これはできなくても仕方ない問題」と、宿題の取捨選択を行いましょう。
- ・親子でのメンタルケア: 成績が伸び悩み、子どもがスランプに陥りやすい時期です。結果だけでなく、努力の過程を認め、励ます言葉をかけるなど、精神的なサポートが不可欠です。
6年生の壁と対策(直前期)
志望校合格に向けた最終段階。過去問演習が本格化し、精神的なプレッシャーも最大になります。
- ・壁: 過去問を解いても合格点に届かず焦る。新しいことを学ぶ時間はなく、弱点補強と得点力アップの両立に悩む。周りの雰囲気にのまれ、自信を失いがち。
- ・対策志望校対策に特化し、一点でも多く得点する戦略を立てましょう。
- ・志望校の過去問分析 出題傾向を分析し、「合格者平均点」と「自分の得点」を比較。どの分野であと何点取れば合格ラインに届くのか、具体的な目標を設定します。
- ・「捨てる勇気」を持つ 入試本番では満点を取る必要はありません。どうしても解けない「捨て問」を見極め、解ける問題に時間を集中させる練習も重要です。
- ・体調管理と自信の醸成 直前期は体調管理が最優先です。また、「これだけやってきたんだから大丈夫」とお子様が自信を持って本番に臨めるよう、最後まで励まし続けましょう。
日能研の算数でついていけない時の克服法

「日能研の算数についていけない…」という悩みは、最も多く聞かれるものの一つです。算数は積み重ねの教科であり、一度つまずくと取り返すのが大変です。ここでは、算数嫌いを克服するための具体的な方法をご紹介します。
計算力の不足を補うトレーニング
応用問題が解けない原因が、実は単純な計算力不足であるケースは非常に多いです。日能研の教材「計算と漢字」などを活用し、毎日5〜10分でも良いので、時間を計って計算練習を続けましょう。正確さとスピードが向上すれば、テストで使える時間が増え、見直しの余裕も生まれます。
文章題・応用問題の解き方のコツ
文章題が苦手な子は、問題文の状況を正しくイメージできていません。問題文を読みながら、図や線分図、表などを描いて情報を「見える化」する練習をしましょう。複雑な問題も、要素を分解して整理することで、解法の糸口が見つかりやすくなります。
図形問題のイメージ力を養う方法
図形問題、特に立体図形は、頭の中だけでイメージするのが難しい分野です。実際に紙を折ったり切ったり、粘土や積み木で立体を作ってみるなど、手を動かして感覚的に理解する経験が大切です。また、補助線の引き方にはパターンがあります。テキストの例題を参考に、どこに線を引けば解きやすくなるのかを学ぶことも有効です。
日能研の算数テキスト・教材の活用法
日能研には多くの算数教材がありますが、すべてを完璧にこなす必要はありません。お子様のレベルに合わせて、効果的に活用しましょう。
- ・本科教室(テキスト): 授業の核となる教材です。まずはここの基本問題や例題を、何も見ずに自力で解けるようにすることを目標にしましょう。
- ・栄冠への道: 復習用の問題集です。基本問題である「学びの基本」は必ず解き、応用問題である「考えよう」は、お子様の余力や志望校のレベルに応じて取り組むか判断しましょう。
- ・算数強化ツール: 特定の単元を強化するためのオプション教材です。苦手分野がはっきりしている場合に、集中的に取り組むと効果的です。
家庭でできる具体的な学習サポート方法
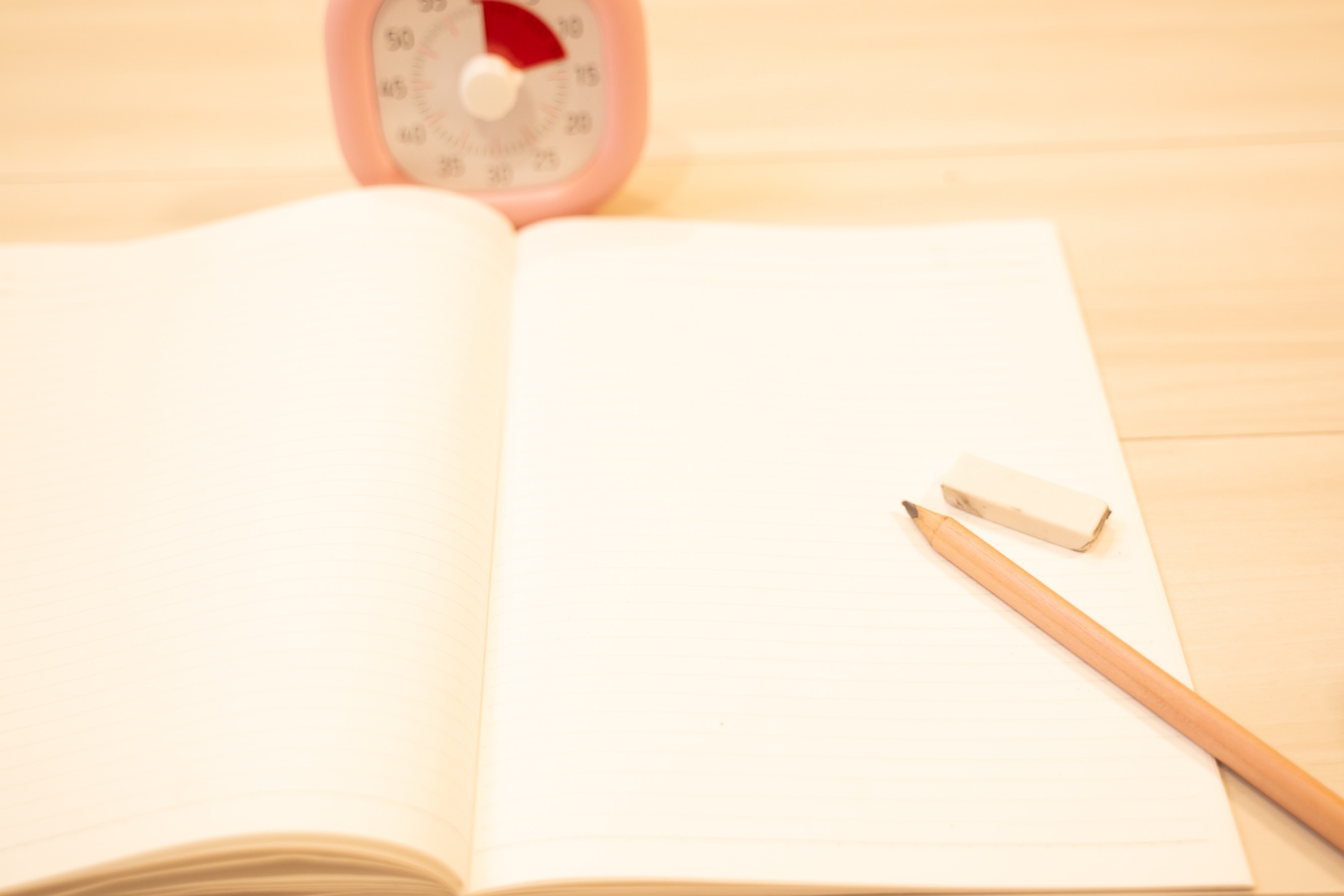
塾の授業だけでなく、家庭でのサポートがお子様の成績を大きく左右します。親が先生のように教える必要はありません。お子様が自走できる「環境」を整えることが、保護者の最も重要な役割です。
復習中心の学習サイクルの確立
中学受験の勉強は「予習」よりも「復習」が圧倒的に重要です。 「授業で習う→その日のうちに復習する→週末に一週間の内容をもう一度復習する」という学習サイクルを確立しましょう。特に、授業で分からなかった部分を放置せず、その日のうちに解決する習慣をつけることが、ついていけなくなるのを防ぐ最大のポイントです。
宿題の優先順位付けと取捨選択
「栄冠への道」などの宿題は、すべてを完璧にこなそうとすると親子で疲弊してしまいます。お子様の学力や残り時間を考え、取り組むべき問題に優先順位をつけましょう。
- 最優先: 授業で扱った問題の解き直し、テキストの基本問題
- 優先: 栄冠への道の基本問題
- 余力があれば: 栄冠への道の応用問題、発展問題
時には「この問題はやらなくていい」と判断する「やらない勇気」も、中学受験を乗り切るためには必要です。
テストの振り返りと解き直しの徹底
テストは成績に一喜一憂するためのものではなく、お子様の弱点を発見するための「宝の山」です。 テストが返却されたら、必ず解き直しをさせましょう。その際、なぜ間違えたのかを分析することが重要です。
- ・計算ミスなのか?
- ・知識を忘れていたのか?
- ・時間が足りなかったのか?
- ・問題の意味を取り違えたのか?
原因を特定し、次に同じ間違いをしないための対策を立てることで、学力は着実に向上します。
日能研の先生・スタッフへの相談方法とタイミング
家庭だけで悩みを抱え込まないでください。日能研の先生や教室スタッフは、受験指導のプロであり、最も身近な相談相手です。
定期的に開催される保護者会や個人面談の機会を積極的に活用しましょう。それ以外でも、子どもの様子で気になることがあれば、電話や連絡ノートで気軽に相談することをおすすめします。その際は、「家でこういう様子なのですが、授業ではどうですか?」「この単元を苦手としていますが、家庭でできる対策はありますか?」など、具体的に質問すると、的確なアドバイスがもらえます。
日能研を続けるかの判断基準と今後の選択肢

様々な対策を試みても状況が改善しない場合、日能研を続けるべきか、他の選択肢を検討すべきか、という大きな決断に迫られます。
転塾を検討すべきサイン
以下のサインが見られる場合は、お子様にとって日能研が合っていない可能性があり、転塾を真剣に検討するタイミングかもしれません。
- ・お子様の心身に不調が出ている: 「塾に行きたくない」と頻繁に言う、腹痛や頭痛を訴えるなど、精神的なストレスが身体症状として現れている場合。
- ・家庭学習が崩壊している: 宿題が終わらず、親子喧嘩が絶えない。家庭が安らぎの場でなくなっている。
- ・半年以上、成績が下降し続けている: 様々な対策を講じても、クラスが下がり続けるなど、明確な改善が見られない。
- ・カリキュラムと子どもの特性が合わない: じっくり考えたいタイプの子が、日能研のスピード感についていけず、常に焦っている。
個別指導や家庭教師の併用が有効なケース
「日能研の集団授業の雰囲気は好きだけど、特定の科目だけがどうしても苦手…」という場合は、転塾ではなく、個別指導や家庭教師を併用するのが非常に有効です。 苦手な算数だけを個別指導でフォローしてもらう、日能研の宿題の進め方を見てもらうなど、集団塾のメリットを活かしつつ、弱点をピンポイントで補強できます。
実際に塾と併用する形でサポートを取り入れるご家庭が増えています。具体的にどんな場面で効果を発揮するのかは、中学受験に家庭教師がおすすめな理由で詳しく解説しています。
苦手科目の克服や宿題の進め方に不安がある場合は、専門家に頼るのが最も効率的です。
学研の家庭教師なら、日能研対策に精通したプロ講師が、お子様に合わせた学習プランを提案します。
他塾(サピックス・早稲アカ)との比較
転塾を考えるなら、他の大手塾との違いを知っておくことが重要です。
- ・SAPIX(サピックス): 最難関校に圧倒的な実績を誇ります。授業の進度が非常に速く、復習中心のカリキュ-ラムと大量の教材が特徴。競争意識が高く、トップ層の生徒にとっては最高の環境ですが、ついていくのは非常に大変です。
- ・早稲田アカデミー :「熱血指導」で知られ、宿題の管理や学習フォローが手厚いのが特徴。競争を促す仕組みが多く、体育会系の雰囲気が合う子には伸びる環境です。
日能研の網羅的なカリキュラムや雰囲気が合わないと感じる場合、これらの塾の特性がお子様に合うかどうか、慎重に見極める必要があります。
サピックスや早稲田アカといった競合塾はそれぞれ独自の強みと学習スタイルを持っています。詳しい内容は以下の記事で解説しています。
中学受験そのものを見直す選択肢
時には、「中学受験から撤退する」という決断が、お子様とご家庭にとって最善の選択となることもあります。 中学受験は、あくまで子どもの将来の選択肢の一つに過ぎません。受験勉強の過度なストレスでお子様が自信を失い、勉強嫌いになってしまっては本末転倒です。
公立中学校に進学し、高校受験でリベンジするという道も立派な選択肢です。大切なのは、世間の評価や親の見栄ではなく、お子様自身が笑顔でいられる道を選んであげることです。
日能研についていけない悩みに関するQ&A

最後に、保護者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
今からでも立て直しは間に合いますか?
はい、正しい原因分析と適切な対策を講じれば、立て直すことは十分に可能です。 特に、学年が低ければ低いほど、軌道修正はしやすいです。重要なのは、焦って応用問題に手を出すのではなく、つまずきの原因となっている単元まで勇気を持って戻り、基礎から徹底的にやり直すことです。一人で難しい場合は、塾の先生や個別指導などの力を借りることを検討しましょう。
子どものやる気がない場合はどうすれば?
無理強いは逆効果です。まずは、なぜやる気が出ないのか、その原因を探ることが大切です。 勉強が難しすぎて自信を失っているのかもしれませんし、他に興味があることがあるのかもしれません。まずは簡単な問題から解かせて「できた!」という成功体験を積ませたり、志望校の文化祭に連れて行ってモチベーションを高めたりするなど、お子様の心に寄り添ったアプローチを試みてください。
中学受験をしない場合、通塾は無駄?
一概に無駄とは言えません。日能研で学ぶことで、高いレベルの学力や学習習慣が身につくことは事実であり、それは高校受験やその先の学習においても大きな財産となります。 ただし、中学受験をしないと決めたのであれば、高校受験に特化した塾や、公立中高一貫校対策コースなど、より目的に合った環境に移る方が効率的である場合もあります。
まとめ
日能研の学習についていけないという悩みは、決して特別なことではありません。多くのお子様と保護者が通る道です。
大切なのは、「ついていけない」という現状を責めるのではなく、その原因を冷静に分析し、お子様に合った対策を一つひとつ試していくことです。
この記事でご紹介した、
- ・5つの原因の特定
- ・学年別・科目別の対策
- ・家庭でのサポート方法
などを参考に、お子様とじっくり向き合ってみてください。
そして、時には塾の先生や専門家の力を借り、さらには転塾や中学受験からの撤退という選択肢も視野に入れながら、お子様にとって本当に幸せな道は何かを考えることが最も重要です。
この記事が、悩めるあなたの心を少しでも軽くし、前向きな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。




-42.jpg)




-41.jpg)
-43.jpg)