医学部の学費は他学部と比べて非常に高いため、多くのご家庭が奨学金の活用を検討することでしょう。本記事では、医学部生が入学後に利用できる奨学金の一覧を紹介するだけでなく、国の制度や自治体によるもの、大学独自のものや民間財団の奨学金制度などを提供元別にわかりやすく解説します。実際の貸与額や受けられる条件なども踏まえて、自分に合った制度選びに役立つ情報を網羅的に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
医学部で使える奨学金一覧

医学部で利用できる奨学金には、「給付型」「貸与型」「返済免除条件付き」の3つの区分があります。それぞれの制度には将来の返済や進路に関わる特徴や注意点もあるため、しっかりと理解しておくことが重要です。ここではまず、各タイプの基本的な違いを整理し、制度選びの前提知識を身につけましょう。
給付型奨学金とは(返済不要)
給付型奨学金は、返済が一切不要な支援制度です。主に家計が厳しい世帯や、学業成績が優秀な学生を対象としています。日本学生支援機構(JASSO)や各大学、民間財団など、多様な団体が給付型奨学金を提供しており、生活費や学費の一部または全額をサポートします。
受給には家計基準や学力基準などの厳しい審査があり、応募者全員が受給できるわけではありません。支給額は制度によって異なり、月額数万円から数十万円まで幅広く設定されています。
給付型は卒業後の経済的負担がない点が最大の魅力ですが、採用枠が限られているため、早めの情報収集と準備が不可欠です。
貸与型奨学金とは(返済が必要)
貸与型奨学金は、将来的に返済が必要なタイプの奨学金です。代表的なものに日本学生支援機構(JASSO)の「第1種(無利子)」と「第2種(有利子)」があり、貸与月額や利息の有無など、制度ごとに特徴があります。
無利子型は成績や家計基準が厳しく、有利子型は比較的利用しやすいのが特徴です。私立医学部では月額最大16万円など高額の貸与も可能ですが、借りすぎると卒業後の返済負担が大きくなるため、慎重な計画が必要です。保護者からは「借金になるのでは?」と心配されることも多いため、返済シミュレーションや将来の収入見通しを踏まえて利用を検討しましょう。
返済免除条件付きの奨学金もある
一定の条件を満たすと返済が免除されるタイプの奨学金も存在します。
たとえば、卒業後に地域医療に従事することを条件に返済が免除される「地域枠」や、都道府県の医学生修学資金などが代表例です。これらは貸与型でありながら、指定の地域や医療機関で一定期間(例:9年間)勤務すれば返済が不要となるため、実質的に給付型となるケースもあります。
ただし、途中で辞退した場合は一括返還や利息が発生することもあるため、制度ごとの詳細やリスクを必ず募集要項で確認してください。また、近年では弘前大学に代表されるように入学時点で地域枠入試を選ぶと、必ず奨学金制度が付帯する場合もあるので、将来を見越した受験が必要となります。
代表的な公的奨学金制度

ここでは、医学部生が利用できる代表的な「公的機関による奨学金制度」について紹介します。主に日本学生支援機構(JASSO)を中心に、国が支援する制度の種類や特徴を解説します。多くの学生が申請対象となる重要な制度群であり、それぞれの違いを順に見ていきましょう。
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構(JASSO)は、全国の大学生が最も利用している奨学金制度です。
貸与型奨学金には「第1種(無利子)」と「第2種(有利子)」があり、どちらも入学前や在学中に申し込めます。第1種は成績や家計の条件が厳しいものの、無利子で月額3万円から最大6.4万円(私立医学部の場合)まで選べます。第2種は有利子で、月額3万円から16万円まで幅広く設定されており、利率は上限3%ですが変動します。
また、返済不要の給付型奨学金もあり、家計基準や成績基準を満たすと授業料減免と併せて支援が受けられます。申請は「予約採用」と「在学採用」があり、申込時期や必要書類の確認が重要です。JASSOの奨学金は、医学部生にとってまず検討すべき基本的な制度です。
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯などを対象に、給付型奨学金と授業料減免をセットで提供する公的支援です。
この制度は医学部だけを対象としたものではありませんが、もちろん医学部生も利用でき、家庭の経済状況によっては授業料や入学金の全額または一部が免除され、月額の給付金も受けられます。JASSOと連携して運用され、入学後の申請も可能です。制度の併用可否は大学によって異なるため、詳細は大学窓口で確認してください。
矯正医官修学資金など医療系支援制度
医療系の特定職種に就くことを前提とした奨学金制度もあります。
たとえば法務省の「矯正医官修学資金制度」では、大学3年次以降の医学科生を対象に月額15万円を貸与し、卒業後に一定期間(3年以上)矯正医官として勤務すれば返済が免除されます。
制度の目的は刑務所などの医療体制強化であり、利用者は国家公務員試験合格や研修後の配属が求められます。他にも防衛医科大学校や自治医科大学など、進路に条件がある代わりに学費全額免除や給与支給など手厚い支援が受けられる制度もあります。進路が限定される分、将来設計をよく考えて慎重に検討しましょう。
自治体による医学部向け奨学金・地域枠制度

ここでは、都道府県などの自治体が実施している奨学金制度や、医学部特有の「地域枠」制度について解説します。医師不足の地域を支援する目的で設けられており、貸与型であっても返済免除となるケースが多いのが特徴です。医学部進学後に申請できる自治体制度も多数あるため、以下で具体例を交えて紹介します。
地域枠奨学金制度と返還免除の仕組み
地域枠とは、卒業後に特定地域で医師として勤務することを条件に奨学金の返還が免除される制度です。多くは都道府県や大学が連携して実施しており、「一定年数(例:9年間)」の勤務義務が課されます。
返還免除が受けられる一方で、途中辞退時には一括返還+利息が発生する場合があるため注意が必要です。地域枠は大学入試段階で専用の入試枠が設けられていることが多く、入学後の奨学金とは別に扱われることもあります。「医師として地元に貢献したい」「経済的な支援を受けたい」両方を希望する家庭にとって、有力な選択肢となります。
都道府県の医学生修学資金の具体例(東京都・長野県など)
各自治体が独自に提供している医学生向けの修学資金制度も充実しています。
たとえば「東京都地域医療医師奨学金」は、年額280万円(6年間で最大1,680万円)の貸与があり、指定医療機関での勤務により返済免除となります。長野県や鹿児島県など全国の地方自治体でも類似の制度があり、返済免除条件や募集人数は自治体ごとに異なります。
貸与金額や対象学年、申請タイミング(大学入学後や学年進行中など)もさまざまです。詳細は各自治体の公式サイトや大学の窓口で必ず確認しましょう。
参考:東京都福祉保健局「東京都地域医療医師奨学金(特別貸与奨学金)」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/sonota/tiikiiryoushiensenta/isishougakukin/tokubetushougakukin
長野県「長野県医師修学資金」
https://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/kenko/iryo/ishikakuho/shugaku.html
鹿児島県「鹿児島県医師修学資金」
https://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-fukushi/doctorbank/taisaku/syuugakutaiyo1.html
大学独自の医学部奨学金制度

ここでは、大学が独自に設けている奨学金制度について紹介します。私立大学では学費が高額な分、返済不要の高額給付型奨学金も存在します。各大学ごとに制度内容・応募条件・給付額が異なるため、代表的な大学を取り上げて紹介します。
私立医学部の高額支援例と特徴
順天堂大学の特待生制度
順天堂大学の特待生制度は、医学部を含む各学部で入学試験の成績優秀者を対象に学費の大幅な減免を行うものです。
医学部の場合、一般選抜A方式二次試験の成績上位10名に対し、1年次は入学金200万円のみの負担となり、授業料・施設設備費・教育充実費(計90万円)が全額免除されます。2年次以降は各年100万円の学費となり、6年間の総額は700万円に抑えられます。結果として、通常よりも1,380万円もの学費が減免される計算です。
ただし、減免の継続には在学中の学業成績が基準を満たしていることが条件で、成績によっては減免額が変更される場合もあります。特待生の人数や選抜基準、詳細な流れは大学公式サイトで随時公表されているため、志望者は最新情報を確認することが重要です。
東北医科薬科大学の地域医療支援資金
東北医科薬科大学医学部では、「地域医療支援資金」として最大3,000万円にのぼる高額な修学資金制度を提供しています。この制度は、卒業後に指定地域で医師として一定期間勤務することを条件に、貸与された資金の返還が免除される仕組みです。
申請の流れや対象学年、勤務義務年数、違約時の返還条件など、詳細は大学の募集要項に記載されています。勤務義務を果たさない場合は一括返還や利息が発生することがあるため、利用前に必ず内容を確認し、自分のキャリアプランと照らし合わせて慎重に判断することが重要です。地域医療に貢献したい学生にとっては、非常に魅力的な支援制度です。
国際医療福祉大学の奨学金制度
国際医療福祉大学医学部では、初年度300万円、2年目以降は年280万円の給付型奨学金制度が用意されています。入試成績や家計状況などの条件を満たした学生が対象となり、返還義務はありません。
奨学金の継続には、毎年の学業成績や出席状況など、大学が定める基準を満たす必要がありますが、経済的な負担を大きく軽減できるだけでなく、学業に専念できる環境が整えられるでしょう。
また、大学独自の給付型・貸与型奨学金も複数あり、希望者は複数の制度を併用できる場合もあるため、詳細は大学の公式サイトや募集要項で確認してください。
北里大学の特待制度
北里大学医学部では、特待生制度として「第1種」と「第2種」の2つの区分を設けています。第1種特待生は入学金・授業料・施設設備費・教育充実費の全額(6年間で約3,890万円)が免除され、第2種特待生が免除されるのはその半額(約1,945万円)です。
若干名が対象で、入学試験の成績上位者から選抜されます。特待生の資格は毎年の成績や出席状況によって見直され、基準を満たさない場合は資格喪失となるので注意が必要です。
また、在学時にも成績優秀者10名程度に翌年度授業料200万円免除の特待生制度があります。これらの制度は、学業成績を維持することで継続可能なため、経済的支援と学業へのモチベーション向上の両立が期待できるでしょう。
帝京大学・近畿大学などの給付型支援
帝京大学医学部や近畿大学医学部でも、返済不要の給付型奨学金制度が設けられています。
支援額は少額〜中額で、年間数十万円から100万円程度の給付が多いですが、経済的支援としては十分役立ちます。応募条件や採用人数、支援金額は大学ごとに異なり、成績優秀者や経済的困難な学生を対象としたものが中心です。
これらの奨学金は、学費負担の軽減だけでなく、学業への意欲向上にもつながるため、多くの学生が利用しています。詳細は大学公式サイトで最新情報を確認してください。
国公立医学部にもある授業料免除・支援制度

東京大学・京都大学などの授業料免除制度
東京大学や京都大学をはじめとする国公立大学では、家計状況や学業成績に応じて授業料が全額または半額免除される制度が整備されています。これは国公立大学ならではの「授業料そのものの減額制度」であり、経済的に困難な学生でも安心して学業に専念できる環境を提供しています。
授業料免除の申請は入学後に可能で、申請後は大学による審査が行われます。免除が認められると、原則として1年間または半年間の授業料が減免され、継続して利用する場合は一定期間ごとに再申請が必要です。2025年度からは多子世帯(子ども3人以上を扶養する世帯)であれば、世帯年収に関係なく授業料と入学金の一定額までが無償化されるなど、支援の幅も広がっています。これにより、より多くの学生が経済的な不安なく進学できるようになっています。
地域連携型の奨学金制度
一部の国公立大学では、自治体と連携した地域医療従事者育成を目的とした奨学金制度が導入されています。
たとえば信州大学では、医師確保を目指し、返済免除型の奨学金を用意しています。これは条件付き貸与制度で、卒業後に指定された地域の医療機関で一定期間勤務することを条件に、貸与された奨学金の返済が免除されます。
ただし、勤務義務を果たさず辞退した場合は、原則として一括返還や利息の支払いが求められるため、利用には慎重な判断が必要です。
こうした制度は、地域医療に貢献したい学生にとって大きなチャンスであり、経済的な支援と将来のキャリア形成を両立できる選択肢となっています。
民間財団の医学部生奨学金制度
医学部生向けの奨学金は、公的機関や大学独自のものだけでなく、民間団体や財団法人が提供する制度も数多く存在します。多くは返済不要の給付型で、経済的支援や医療人材育成を目的としており、家計状況や学業成績、志望理由などを重視して選考される傾向があります。
代表的な財団として、佐々木泰樹育英会、大塚敏美育英奨学財団、伊藤忠育英財団、住友生命福祉文化財団、武田科学振興財団、岸本基金、公益財団法人小川賢太郎奨学財団などが挙げられます。給付額は月額数万円から年間100万円を超えるものまで幅広く、選考基準や対象人数は財団ごとに異なります。
応募は大学経由の場合が多いため、まずは大学の奨学金窓口で情報を集めましょう。募集要項や締切は年度ごとに変わるため、各財団の公式サイトも必ず確認してください。
以下は民間財団の参考サイトになります
- ・佐々木泰樹育英会
https://sasakitaijuikueikai.or.jp - ・大塚敏美育英奨学財団
https://www.otsukafoundation.org/ - ・伊藤忠育英財団
https://www.itofound.or.jp - ・小川賢太郎奨学財団
https://ogawa-shogakuzaidan.or.jp/ - ・岸本基金
https://www.senri-life.or.jp/business/grants/application/
医学部奨学金を選ぶときのポイントと注意点
医学部の奨学金制度は種類も多く、条件も複雑です。自分に合った制度を選ぶには、制度ごとの特徴やリスクを正しく理解することが大切です。ここでは、制度を検討する際に特に注目しておきたいポイントを整理しました。ぜひ制度選びの参考にしてください。
| チェックポイント | 内容 |
| ✅ 返済義務の有無 | 給付型・貸与型・返還免除型など、制度ごとの返済条件を確認しましょう。条件を満たせなかった場合、返済が必要になることもあります。 |
| ✅ 勤務条件の有無 | 卒業後に地域医療へ従事することを条件に、返済が免除される制度もあります。将来の進路に関わるため、内容をよく確認しましょう。 |
| ✅ 申請時期の確認 | 入学前に申し込む「予約採用」、入学後に申請する「在学採用」などがあり、期限を逃すと利用できなくなる可能性があります。 |
| ✅ 書類準備の早期対応 | 成績証明書や所得証明など、準備に時間がかかる書類もあるため、早めに必要書類を把握しておくと安心です。 |
| ✅ 学費以外の出費 | 授業料だけでなく、教材費・交通費・生活費なども6年間で大きな負担になります。総合的な費用を見積もりましょう。 |
| ✅ 他制度との併用 | 奨学金だけで賄えない場合は、教育ローンや他の支援制度の活用も視野に入れましょう。 |
まとめ
医学部には多様な奨学金制度があり、公的支援から大学独自、自治体や民間財団まで幅広く活用できます。制度ごとに返済義務や勤務条件、申請時期が異なるため、早めの情報収集と比較検討が欠かせません。家計状況や将来の進路に合わせて自分に合った制度を見つけることが、安心して学業に集中するための第一歩です。
本記事を参考に、ご家庭に最適な制度選びを進めてみてください。




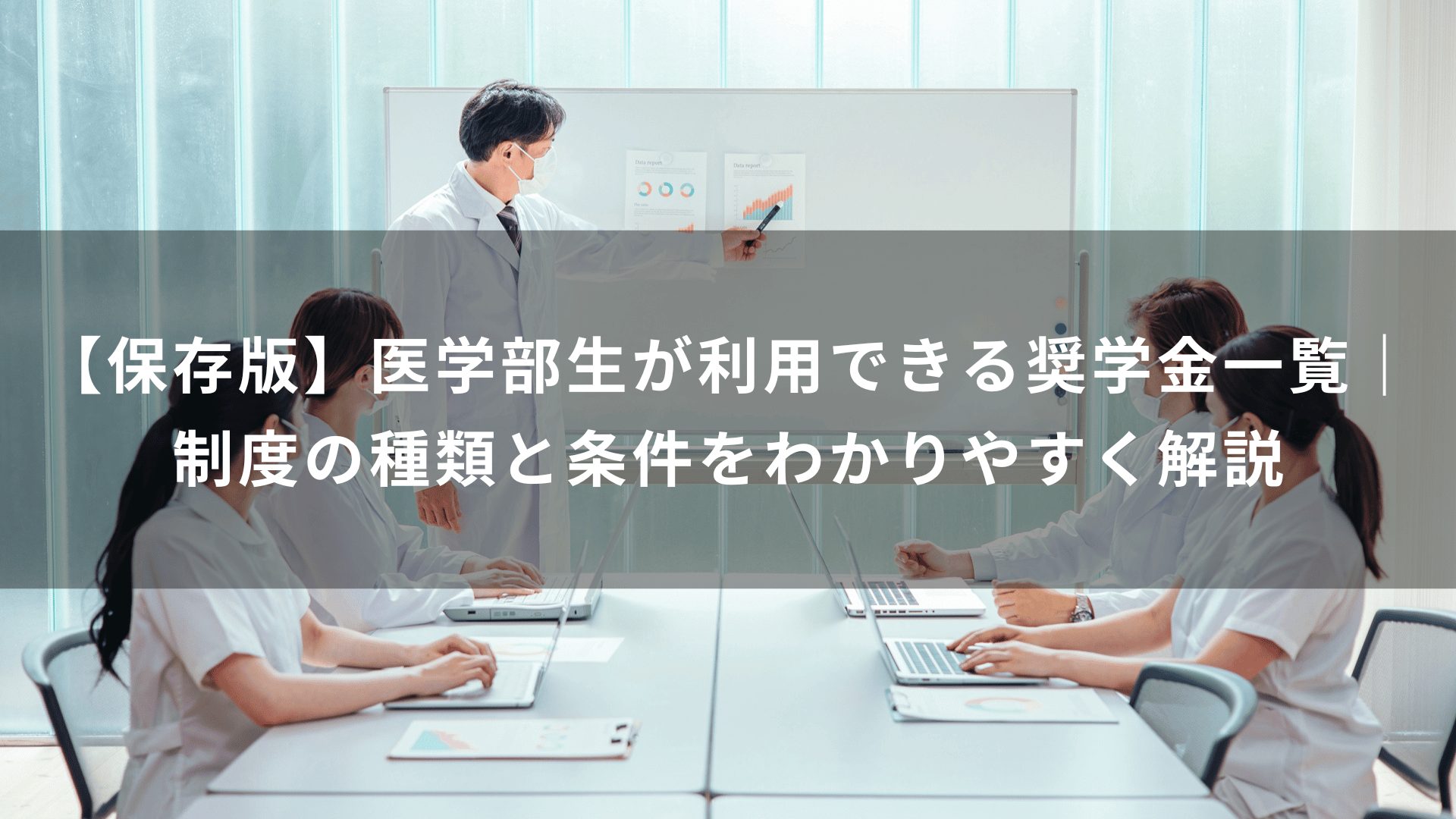
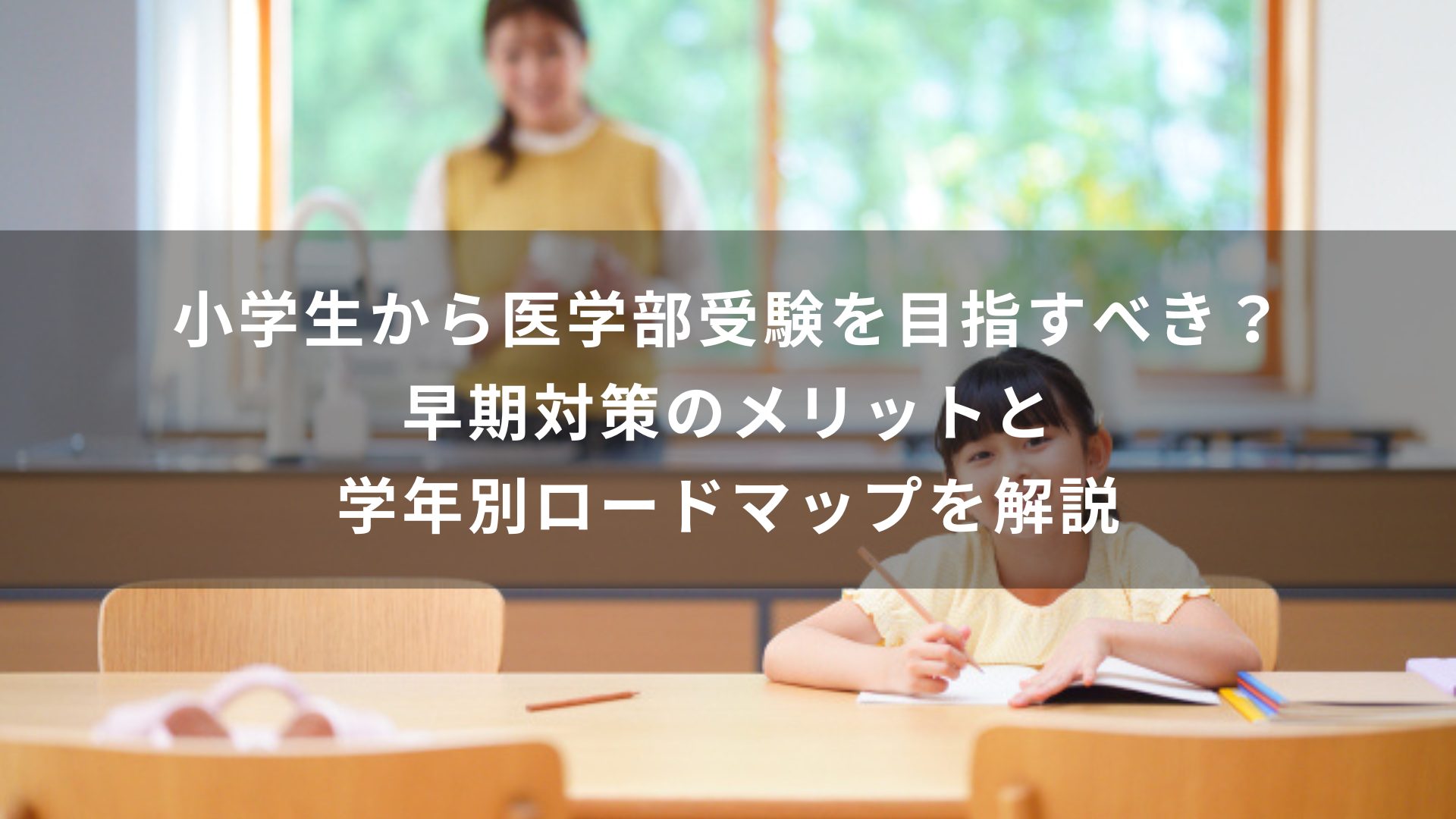
.jpg)