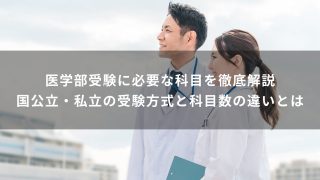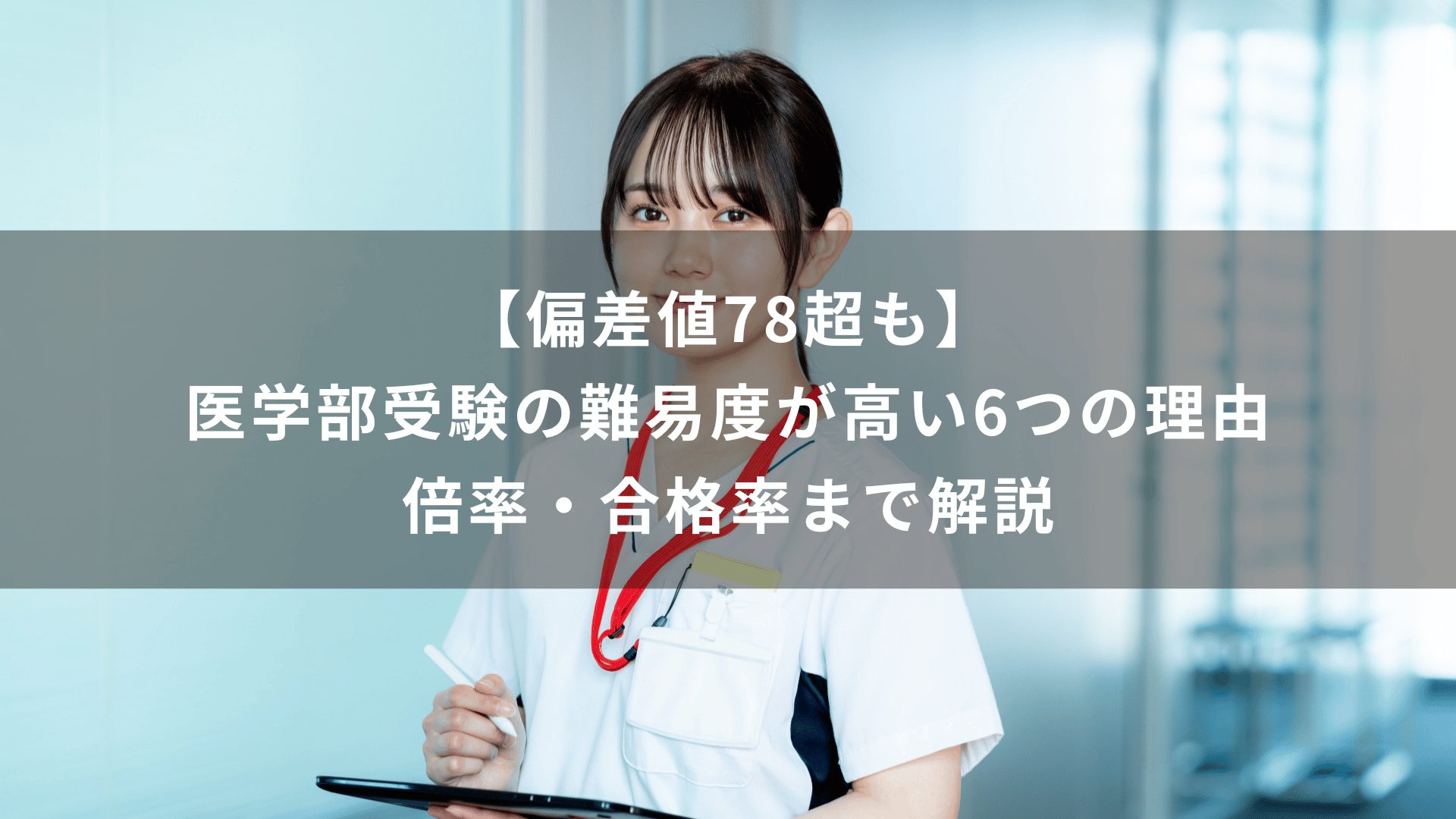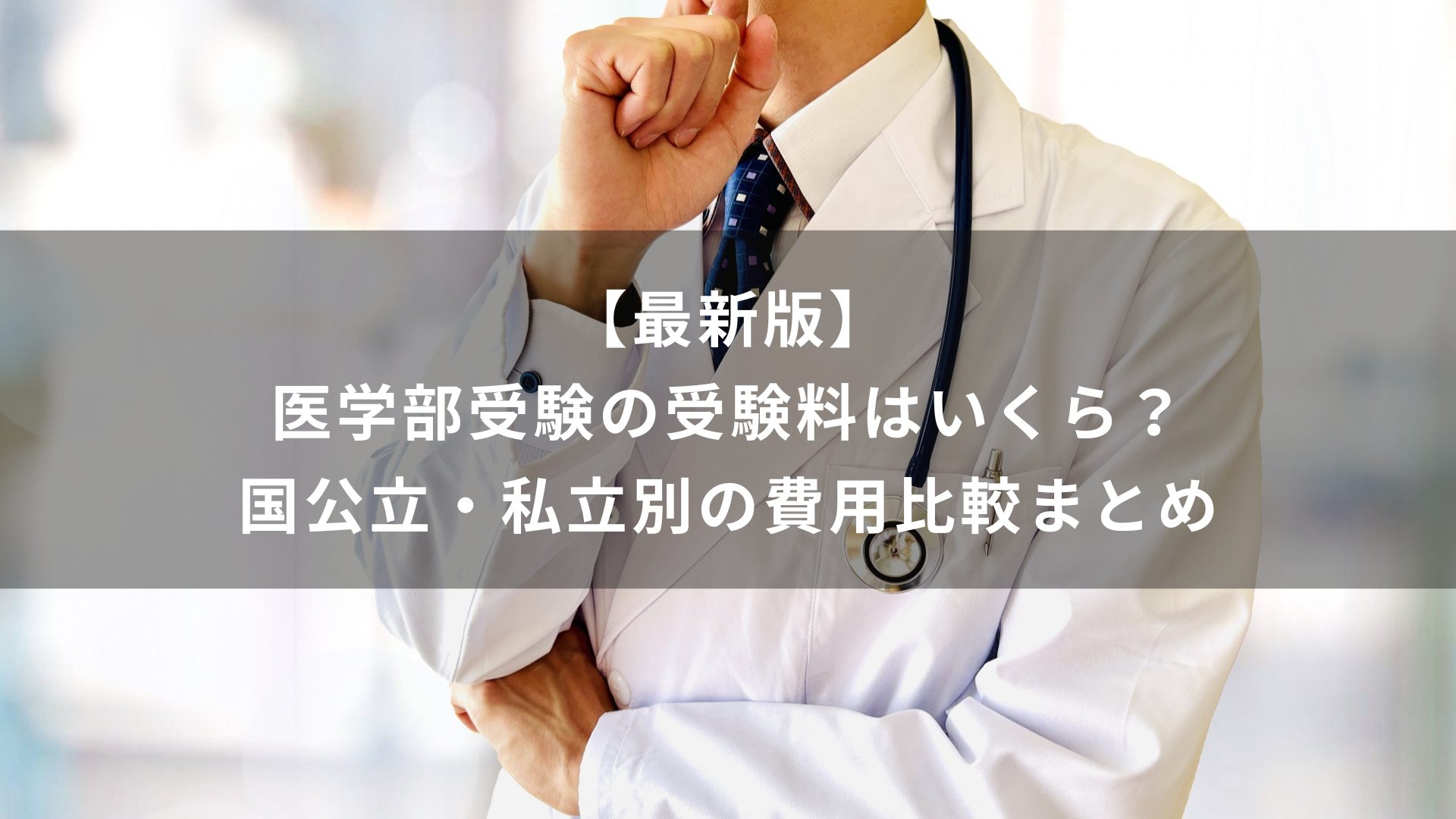「医学部に行きたいけど、理科の選択科目はどれを選べばいいんだろう…」 「物理と生物、どっちが有利なの?」 「科目選択で失敗して、受験できる大学が減るのは避けたい…」
医学部合格という高い目標を掲げるあなたにとって、理科の科目選択は受験戦略の根幹をなす、非常に重要な決断です。この選択一つで、学習の負担や受験可能な大学の数が大きく変わってしまうことも少なくありません。
この記事では、医学部受験における理科の科目選択で悩んでいるあなたのために、物理・化学・生物それぞれの特徴から、国公立・私立大学ごとの傾向、そしてあなたに合った科目の選び方まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、後悔しない科目選択のための知識が身につき、自信を持って受験勉強のスタートラインに立つことができるでしょう。
医学部受験理科の科目選択パターン

医学部受験の理科は、大学入学共通テスト(以下、共通テスト)と大学ごとの個別試験(二次試験)で課されます。まずは、どのような科目選択のパターンがあるのか、基本をしっかり押さえましょう。
基本は「化学」+1科目の組み合わせ
医学部受験における理科選択の王道は、「化学」を軸に、もう1科目を「物理」または「生物」から選ぶという組み合わせです。
なぜなら、ほとんどの国公立・私立大学医学部で、理科2科目が必須となっており、そのうち「化学」が必須、もしくは化学の知識を前提とした問題が出題されるケースが非常に多いからです。
特別な理由がない限り、「化学」を選択科目に入れるのが基本戦略となります。したがって、多くの受験生は以下の2つのパターンのどちらかを選ぶことになります。
- 物理・化学選択
- 生物・化学選択
物理・化学選択のメリットと注意点
物理と化学を選択するパターンは、医学部受験において最もスタンダードな組み合わせと言えます。
メリット
・受験できる大学が最も多い
ほとんどすべての医学部を志望校の選択肢に入れることができます。志望校がまだ決まっていない、あるいは選択肢を広く持ちたい受験生にとって最大のメリットです。
・高得点を狙いやすい
物理は一度原理を理解すれば、計算によって明確な答えを導き出せる問題が多いです。そのため、ケアレスミスさえなければ満点も狙いやすく、得点が安定しやすい傾向にあります。
・学習の応用が効きやすい
物理で培われる論理的思考力や計算力は、化学の理論分野や数学の学習にも良い影響を与えます。
注意点
・高度な数学力が必要
物理の問題を解くには、数Ⅲまでの知識を含む高い計算力や数学的な思考力が不可欠です。数学が苦手な受験生には、大きな負担となる可能性があります。
・理解に時間がかかることがある
公式をただ暗記するだけでは太刀打ちできず、物理現象の根本的な理解が求められます。理解に至るまで時間がかかる場合があるため、早期からの対策が必要です。
医学部受験で物理を選ぶ場合の勉強法や参考書の選び方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
生物・化学選択のメリットと注意点
生物と化学を選択するパターンは、特に暗記が得意な受験生に人気があります。
メリット
・暗記や知識の整理が得意な人に向いている
生物は暗記すべき事項が非常に多い科目です。コツコツと知識を積み上げ、整理するのが得意な受験生にとっては、学習を進めやすいでしょう。
・入学後の学習に直結する
医学部入学後は、生化学や解剖学、生理学など、生物学の知識が基礎となる講義が多くあります。受験勉強で得た知識が直接役立つ場面が多いのは、大きなモチベーションになります。
・数学が苦手でも挑戦しやすい
物理ほど高度な計算力は要求されません。計算問題も出題されますが、基本的な四則演算や比の計算が中心です。
注意点
・受験できる大学が一部制限される
ごく一部の大学では、物理が必須、あるいは物理・化学選択が前提となっている場合があります。志望校によっては、生物選択では受験できない可能性があるため、事前の確認が必須です。
・高得点が取りにくい場合がある
知識問題だけでなく、実験考察や論述問題も多く出題されます。採点基準が曖昧になりがちで、満点を取るのが難しい科目と言われています。また、細かい知識の抜け漏れが失点に繋がりやすいです。
物理・生物選択が可能な大学
「化学が苦手だから、物理と生物で受験したい」と考える方もいるかもしれません。しかし、「物理・生物」の組み合わせで受験できる医学部は非常に少ないのが現状です。
この組み合わせを認めている大学は、筑波大学(医学類)などごく一部に限られます。化学を避けるという選択は、志望校の選択肢を大幅に狭めてしまうリスクがあるため、基本的にはおすすめできません。
生物を選択する際のメリット・デメリットや勉強の進め方について、くわしくはこちらで解説しています。
物理選択と生物選択の有利不利を比較

「結局、物理と生物、どっちが有利なの?」これは多くの受験生が抱く疑問です。ここでは、様々な角度から両者の有利・不利を徹底比較します。
受験可能な大学数での比較
結論から言うと、受験可能な大学の数では「物理選択」が有利です。 ほとんどの大学は「物理・化学・生物から2科目選択」としていますが、一部の国公立大学(例:群馬大学、佐賀大学など)では、二次試験で物理が必須となる場合があります。
そのため、志望校の選択肢を最大限に広げたいのであれば、物理を選択する方が安全と言えるでしょう。ただし、生物選択が不利になる大学は少数派であり、大半の大学は生物選択でも問題なく受験できます。
高得点の狙いやすさでの比較
高得点の安定性や満点の狙いやすさでは、「物理選択」に分があると言われています。
ただし、これはあくまで一般論です。生物が得意で、知識を完璧にインプットできる受験生であれば、生物で高得点を取ることも十分に可能です。
学習時間と他教科への影響
学習に必要な総時間には、個人差があるため一概には言えませんが、科目特性による違いはあります。
自分の学習スタイルや、数学・国語といった他教科とのバランスを考えて選択することが重要です。
入学後の学習との関連性
医学部入学後の学習という観点では、「生物選択」の方が直接的に役立つ場面が多いです。解剖学、生理学、生化学といった基礎医学の分野は、高校生物の知識が前提となります。
一方で、物理選択が不利になるわけではありません。CTやMRIといった高度な医療機器の原理を理解する上では、物理学の知識が役立ちます。どちらの科目で学んだことも、将来医師になる上で無駄になることはありません。
ここまで読んでも「物理と生物、どちらが自分に向いているのか…」と迷う受験生は少なくありません。志望校の出題傾向や配点、そしてあなた自身の学習特性を踏まえた科目選びは、一人で決めるのが難しいこともあります。そんな時は、医学部受験を熟知した学研の家庭教師にご相談ください。
物理・化学・生物の科目別特徴と対策

ここでは、各科目の特徴と、医学部受験で合格点を取るための対策のポイントを解説します。
物理の特徴と求められる能力
物理とは、自然界の現象を支配する法則を、数式を用いて体系的に理解する学問です。
特徴
力学、熱力学、波動、電磁気学の4分野から構成されます。公式を暗記するだけでなく、なぜその公式が成り立つのかという現象の根本的な理解が求められます。
求められる能力
論理的思考力
数学的な処理能力(特に微積分)
空間認識能力
対策のポイント
まずは教科書レベルの基本事項を完璧に理解することが最優先です。その後、標準的な問題集を繰り返し解き、解法パターンを身につけましょう。難関大学を目指す場合は、応用問題集にも取り組み、思考力を養う必要があります。
化学の重要性と学習範囲
化学とは、物質の構造や性質、変化を原子・分子レベルで解明する学問です。
特徴
理論化学、無機化学、有機化学の3分野からなり、学習範囲が非常に広いのが特徴です。計算問題と知識問題がバランス良く出題されます。医学部受験では、ほぼすべての大学で必須となる最重要科目です。
求められる能力
- 計算力
- 膨大な知識を整理・暗記する能力
- 論理的な思考力
対策のポイント
まずは理論化学を固め、計算問題の基礎を築きましょう。無機・有機化学は、知識の暗記が中心となりますが、単なる丸暗記ではなく、周期表や反応の原理と関連付けて体系的に覚えることが重要です。特に有機化学の構造決定は、医学部入試の頻出問題です。
医学部受験における化学の戦略や分野別の勉強法、参考書ルートについては、こちらの記事をご覧ください。
生物の特徴と求められる能力
生物とは、生命現象の仕組みや多様性について探求する学問です。
特徴
遺伝、体内環境、動物・植物の反応、生態系など、非常に幅広い分野を扱います。知識の暗記が学習の中心ですが、近年は実験考察問題や論述問題の比重が高まっています。
求められる能力
- 膨大な知識を正確に暗記する能力
- 情報を整理し、体系的に理解する能力
- 実験データや長文を読み解く読解力・考察力
- 考えを簡潔にまとめる記述力
対策のポイント
教科書や資料集を隅々まで読み込み、太字の用語だけでなく、図やグラフ、実験内容まで正確に理解することが大切です。知識をインプットするだけでなく、問題演習を通じて、考察力や記述力をアウトプットする練習を積み重ねましょう。
国公立と私立医学部の理科科目の違い

国公立大学と私立大学では、入試の仕組みや問題の傾向が異なります。理科の対策においても、その違いを意識することが重要です。
国公立医学部の受験科目と傾向
国公立大学医学部は、共通テストと二次試験の合計点で合否が決まります。
- ・共通テスト…理科は基礎を付さない科目(物理、化学、生物、地学)から2科目選択が基本です。
- ・二次試験…理科は「物理、化学、生物から2科目選択」とする大学がほとんどです。問題形式は記述・論述式が中心で、思考力や表現力が問われる難易度の高い問題が多く出題されます。大学によっては、特定の科目を必須としている場合があるため、志望校の募集要項は必ず確認しましょう。
私立医学部の受験科目と傾向
私立大学医学部は、大学独自の個別試験で選抜が行われます。
- ・個別試験…理科は「物理、化学、生物から2科目選択」が主流です。問題形式はマークシート方式が多く、解答のスピードと正確性が求められます。
- ・大学ごとの傾向…私立医学部は、大学ごとに出題傾向が大きく異なるのが特徴です。特定の分野が頻出であったり、非常に細かい知識が問われたりすることもあります。過去問研究を徹底し、志望校に特化した対策を行うことが合格の鍵となります。
理科1科目で受験できる大学
理科の負担を減らしたいと考える受験生の中には、「理科1科目で受験できないか?」と考える人もいるでしょう。
結論として、理科1科目で受験できる医学部は存在しますが、非常に少数です。 例えば、帝京大学や東海大学(一部の入試方式)などが該当しますが、募集人数が少なかったり、他の科目の配点が高かったりと、特殊な入試形式であることが多いです。
理科1科目入試は、選択肢が限られるだけでなく、その大学に受験生が集中するため、かえって高倍率になる可能性もあります。基本的には、理科2科目をしっかりと対策するのが王道です。
国公立/私立の受験方式や必要科目の全体像はこちらの記事をご覧ください。
タイプ別おすすめの理科科目選択

ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、最終的には「自分に合った科目」を選ぶことが何よりも大切です。あなたのタイプ別に、おすすめの科目選択を提案します。
数学や物理が得意な受験生
- 【おすすめの選択】物理・化学
- 理由…物理で高得点を狙える可能性が高く、得意な数学力を最大限に活かせます。物理の学習が化学の理論分野の理解を助けるなど、科目間の相乗効果も期待できます。受験できる大学の数が最も多く、戦略的な選択と言えます。
暗記や情報整理が得意な受験生
- 【おすすめの選択】生物・化学
- 理由…生物の膨大な知識量を着実にインプットできるあなたの強みを活かせます。コツコツと努力を積み重ねることで、安定した得点源にすることが可能です。入学後の学習にも繋がりやすく、モチベーションを維持しやすいでしょう。
志望校の選択肢を広く持ちたい場合
- 【おすすめの選択】 物理・化学
- 理由…前述の通り、物理・化学選択はほぼ全ての医学部を受験対象にできます。現時点で特定の志望校が決まっていない場合や、受験直前期に志望校を変更する可能性を考慮すると、最もリスクの少ない選択です。
併願校の戦略から考える科目選択
- ・第一志望校だけでなく、併願する可能性のある大学の入試科目も必ず確認しましょう。
- ・例えば、国公立大学が第一志望で生物・化学を選択した場合、併願する私立大学で物理が必須だと、受験の機会を失ってしまいます。
- ・自分の学力や大学のレベルを考慮し、現実的な併願パターンをいくつか想定した上で、科目選択を行うのが賢明です。
主要大学医学部の理科入試科目一覧
【注意】以下の情報は記事執筆時点のものです。必ず各大学が発表する最新の募集要項を公式サイトで確認してください。
国公立大学医学部の二次試験科目
| 大学名 | 理科の科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 物理、化学、生物、地学から2科目選択 | 理科3科目での受験も可能 |
| 京都大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 大阪大学 | 物理、化学が必須 | 生物選択では受験不可 |
| 東北大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 名古屋大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 九州大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 北海道大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 千葉大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 東京医科歯科大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
私立大学医学部の個別試験科目
| 大学名 | 理科の科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 東京慈恵会医科大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 日本医科大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 順天堂大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 大阪医科薬科大学 | 物理、化学、生物から2科目選択 | – |
| 帝京大学 | 物理、化学、生物から1科目選択 | 英語、国語、数学、理科から高得点2科目を採用 |
共通テストで必要な理科科目
国公立大学医学部を受験する場合、共通テストでは基本的に「物理」「化学」「生物」「地学」の中から2科目を選択する必要があります。多くの受験生は、二次試験で使う科目と同じ2科目を選択します。
私立大学医学部では、共通テスト利用入試を実施している大学も多く、その場合も理科2科目が必要となるのが一般的です。
医学部理科選択のよくある質問
最後に、医学部の理科選択に関してよく寄せられる質問にお答えします。
理科3科目での受験は可能か?
可能です。しかし、実施している大学は非常に少ないです。 例えば、東京大学(理科三類)では、理科2科目に加え、もう1科目を「アドバンスト理科」として選択し、合計3科目で受験する方式があります。ただし、3科目分の学習負担は非常に大きく、他の科目の学習時間を圧迫するリスクがあるため、よほど理科に自信がある受験生以外にはおすすめできません。
科目選択はいつまでに決めるべきか?
理想は高校2年生の夏から秋にかけてです。 この時期に科目を決定できれば、高校2年生のうちから受験を意識した学習をスタートでき、大きなアドバンテージになります。遅くとも、高校3年生に進級する春までには必ず決定しましょう。これ以上遅れると、十分な演習時間を確保するのが難しくなります。
途中で選択科目を変更できるか?
物理的に不可能ではありませんが、極めて困難であり、推奨しません。 例えば、高校3年生の夏に生物から物理に変更する場合、1年以上かけて物理を学んできた他の受験生に追いつくのは至難の業です。学習の遅れを取り戻すために膨大な時間が必要となり、他の科目の勉強にも深刻な影響が出ます。
科目選択は、あなたの医学部受験の成否を左右する重要な決断です。安易に決めず、この記事で紹介した様々な視点からじっくりと考え、後悔のない選択をしてください。
まとめ
今回は、医学部受験における理科の科目選択について、有利・不利の比較から具体的な対策まで詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
理科の科目選択は、医学部合格への長い道のりの第一歩です。あなたの強みを最大限に活かせる科目を選び、自信を持って受験勉強に臨んでください。応援しています!




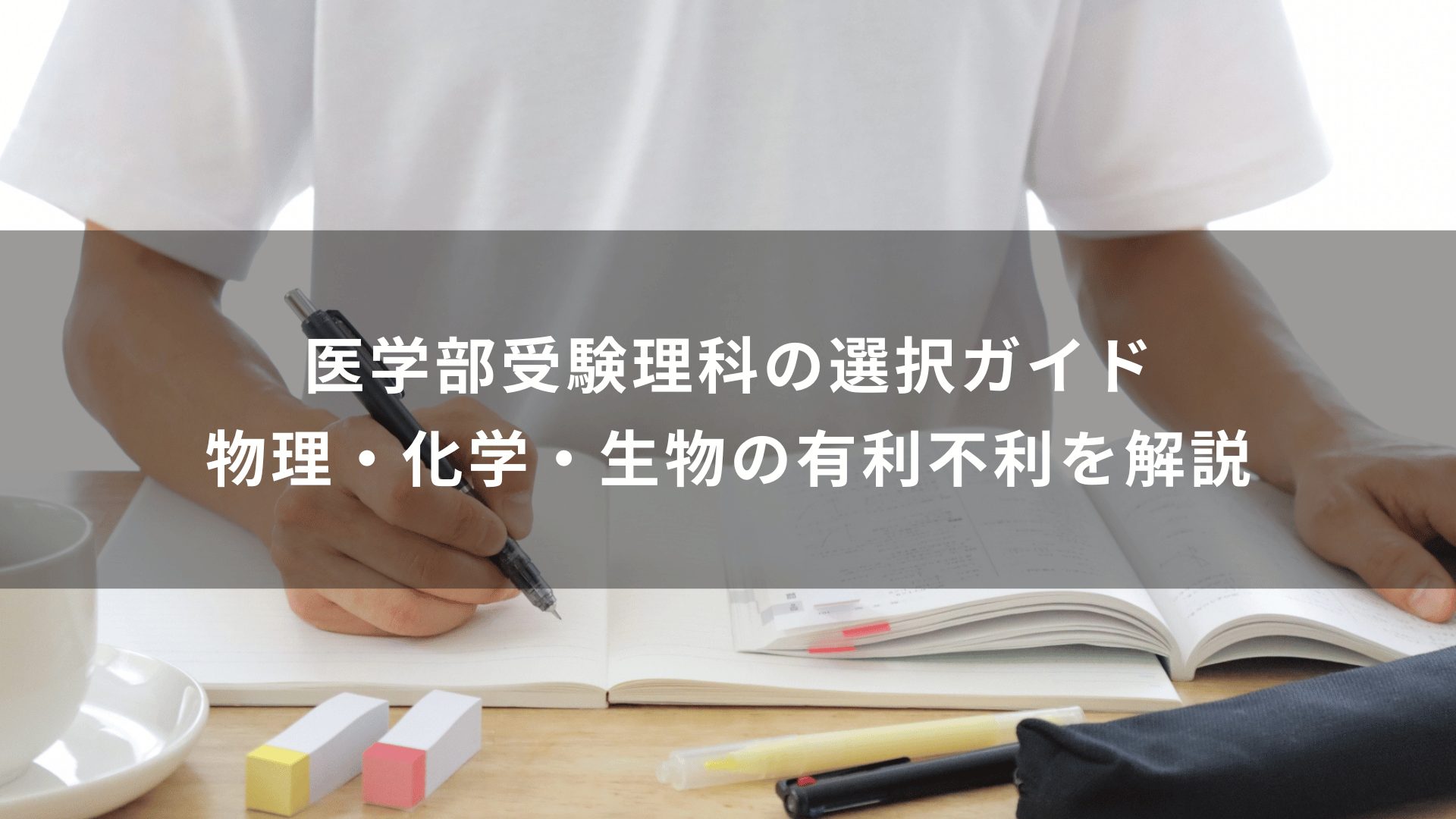
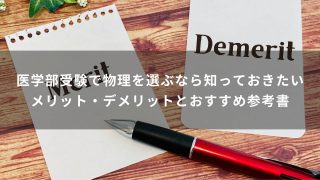
-8-320x180.jpg)

-7-320x180.jpg)