医学部入試において、学力試験と同じくらい重要視される「志望理由書」。いざ書こうとしても、「何から手をつければいいか分からない」「医師になりたい気持ちをどう文章にすれば…」と悩んでしまう受験生は少なくありません。
この記事では、医学部受験を控えたあなたが、ライバルと差がつく質の高い志望理由書を書き上げるための全てを解説します。
評価される構成の作り方から、文字数・テーマ別の豊富な例文、やってはいけないNG例まで、この記事さえ読めば、自信を持って志望理由書を完成させることができます。あなたの熱意を伝えるための第一歩を、ここから始めましょう。
医学部志望理由書を書く前の3つの準備

優れた志望理由書は、いきなり書き始めても完成しません。合格を掴むためには、事前の準備が何よりも重要です。以下の3つのステップを丁寧に行うことで、内容に深みと説得力が生まれます。
自己分析で「医師を志す理由」を深掘りする
なぜ自分は医師になりたいのか。この問いに対する答えが、志望理由書の核となります。漠然とした憧れを、自分だけの具体的な物語に落とし込むために、以下の質問に答える形で自己分析を進めてみましょう。
- ・きっかけ
- →医師という職業を初めて意識したのはいつ、どんな出来事がきっかけでしたか?(例:自身の病気や怪我、家族の闘病、医療ドラマやドキュメンタリー、本など)
- ・原体験
- →医療の現場に触れた経験はありますか?(例:病院でのボランティア、職場体験、オープンキャンパスでの模擬授業など)
- ・理想の医師像
- →どのような医師になりたいですか?(例:患者に寄り添う臨床医、新しい治療法を開発する研究医、地域医療を支える総合診療医など)
- ・興味のある分野
- →医学のどの分野に特に興味がありますか?(例:がん治療、再生医療、救急医療、小児科、精神科など)
- ・自身の強み
- →あなたの長所や得意なことは何ですか?それは医師という仕事にどう活かせると考えますか?(例:コミュニケーション能力、探究心、忍耐力、科学的思考力など)
これらの問いに答えることで、あなたの志望動機がより明確になり、文章にオリジナリティが生まれます。
志望大学のアドミッションポリシーを読み解く
アドミッションポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を示す方針のことです。これを理解せずに志望理由書を書くことは、相手の求めるものを知らずにプレゼントを選ぶようなものです。
志望大学の公式サイトで必ずアドミッションポリシーを確認し、以下の点を読み解きましょう。
- ・建学の精神・理念
- →大学がどのような歴史を持ち、何を大切にしているか。
- ・教育目標・カリキュラム
- →どのような医師を育成しようとしているか。特徴的な授業や実習はあるか。
- ・求める学生像
- →「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」など、具体的にどのような能力を持つ学生を求めているか。
アドミッションポリシーに書かれている言葉を自分の言葉で解釈し、自分の強みや目標が大学の方針と合致していることをアピールすることが、合格への近道です。
志望大学の雰囲気や実際の校風、教育現場を体感した上で文章を磨くと説得力がさらに増します。OCでは具体的に「何を見るべきか」「どんな質問をすべきか」が分かります。
大学ごとの文字数や提出要件を確認する
志望理由書は、大学によって求められる形式が異なります。出願前に必ず募集要項を隅々まで確認してください。
- ・文字数
- →200字、400字、800字、1000字以上など、指定された文字数に合わせて内容を調整する必要があります。
- ・様式
- →大学所定の用紙か、Web出願システムへの入力か。手書きか、PC作成か。
- ・提出の有無
- →そもそも志望理由書の提出が必要かどうかも大学によります。特に国公立大学の一般入試前期日程では不要な場合も多いですが、推薦入試や後期日程、私立大学では必須となるケースがほとんどです。
これらの要件を把握し、計画的に準備を進めることが大切です。
志望理由書だけでなく、自己推薦書で「あなた自身の強み」をどう伝えるかも合否を大きく左右します。両方をバランスよく仕上げることが重要です。
評価される医学部志望理由書の書き方
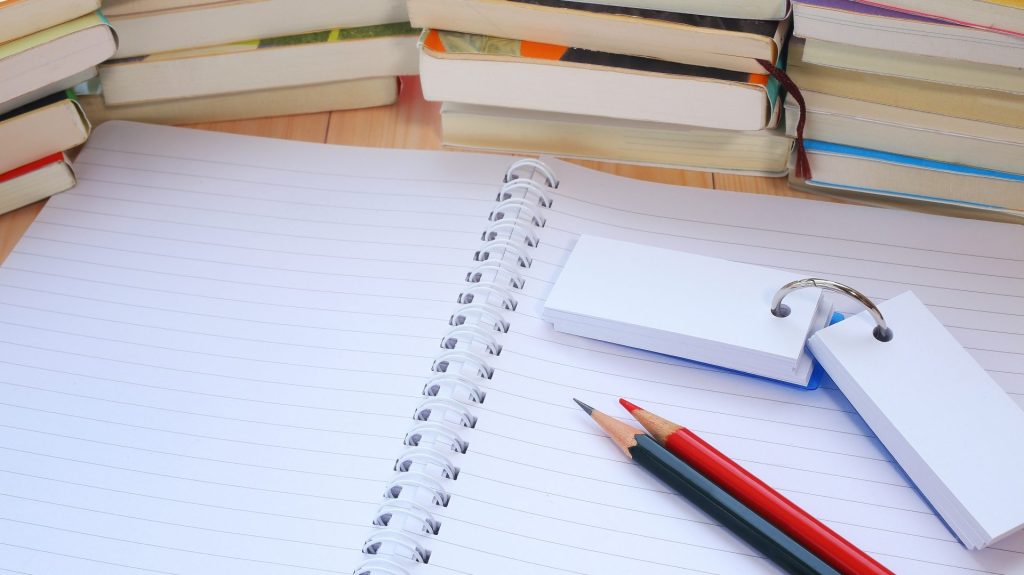
準備が整ったら、いよいよ執筆です。ここでは、評価者の心に響く志望理由書の基本的な書き方を、構成から具体的なフレーズまで解説します。
基本構成は「序論・本論・結論」
志望理由書は、「序論・本論・結論」の3部構成で書くのが基本です。この流れを意識することで、論理的で分かりやすい文章になります。
- ・序論(結論)
- →私が医師を志望する理由
- ・本論(具体例)
- →医師を志望するきっかけとなった具体的なエピソード
- →なぜ「この大学」で学びたいのか
- ・結論(将来の展望)
- →入学後の抱負と、将来どのように社会や医療に貢献したいか
この構成に沿って、あなたの熱意を伝えましょう。
読み手の心を掴む「書き出し」の具体例
書き出しは、読み手の第一印象を決める重要な部分です。最初に結論(医師を志す理由)を簡潔に述べることで、読み手は何について書かれているのかをすぐに理解できます。
- ・きっかけを提示する書き出し
- →「私が医師を志すようになったのは、祖父が地域医療に貢献する姿を間近で見てきた経験がきっかけです。」
- ・将来の目標を提示する書き出し
- →「私は、最先端のがん研究を通じて、一人でも多くの患者様を救うことができる研究医になることを目標としています。」
- ・問題意識を提示する書き出し
- →「現代社会が抱える心の病に寄り添い、精神的な側面から人々を支える精神科医になりたいと強く考えています。」
説得力を持たせる「本論」の組み立て方
本論は、志望理由書の中で最も重要なパートです。ここでは、「なぜ医師なのか(Why Doctor?)」と「なぜこの大学なのか(Why this University?)」の2点を、具体的なエピソードを交えて論理的に結びつける必要があります。
- 医師を志したきっかけ(原体験)を具体的に記述する
- ただ「病気で苦しむ人を助けたい」と書くのではなく、「〇〇という病気を患った際、担当医の□□な姿勢に感銘を受け、自分も患者の心に寄り添える医師になりたいと思った」のように、固有名詞や感情を交えて書きましょう。
- 大学の研究・カリキュラムと自分の目標を結びつける
- 「貴学の〇〇研究室は、私が関心を持つ△△分野で国内トップクラスの実績を誇ります。また、□□という独自の臨床実習プログラムを通じて、早期から地域医療の現場を体験できる点に強く惹かれました。」のように、大学の特色を具体的に挙げ、それが自分の目標達成にどう繋がるのかを説明します。
自分だけのストーリーと、徹底した大学研究を組み合わせることで、本論に説得力が生まれます。
熱意が伝わる「結び」のフレーズ集
結びでは、これまでの内容をまとめ、入学後の学習意欲と将来への貢献意欲を力強く宣言します。
- ・「貴学の充実した教育環境のもとで主体的に学びを深め、将来は〇〇として地域医療に貢献できる人材になりたいです。」
- ・「これまでの探究活動で培った粘り強さを活かし、貴学での6年間の学びを通して、人々の健康と未来に貢献できる医師になることをお約束します。」
- ・「オープンキャンパスで感じた貴学の活気ある雰囲気の中で、仲間と切磋琢磨しながら、理想の医師像の実現に向けて邁進する所存です。」
【文字数・テーマ別】医学部志望理由書例文集
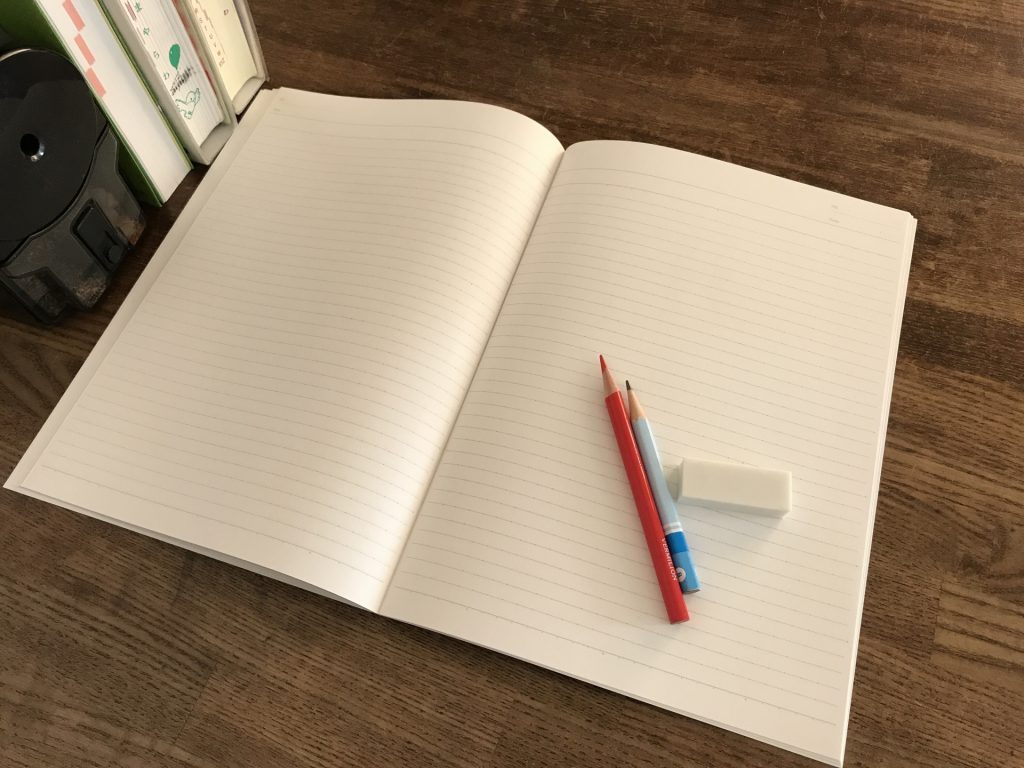
ここでは、様々な状況に合わせた志望理由書の例文を紹介します。あくまで参考として、あなた自身の言葉で書き換える際のヒントにしてください。
文字数別の例文(200字・400字・800字)
200字の例文
私が医師を志望するのは、小児科医として子どもたちの未来を守りたいからです。幼少期に入院した際、不安な私を励まし続けてくれた医師の姿に感銘を受けました。貴学の充実した小児医療プログラムと地域連携実習に魅力を感じています。入学後は主体的に学び、患者とその家族に寄り添える医師を目指します。(198字)
400字の例文
私が医師を志す理由は、自身の怪我の経験から、患者の心身両面の痛みを理解できる整形外科医になりたいと考えたからです。高校時代、部活動で重傷を負い、長期のリハビリを経験しました。その際、身体の回復だけでなく、精神的な不安にも寄り添ってくれた医師の存在が大きな支えとなりました。 貴学は、スポーツ医学の分野で先進的な研究を行っており、私が目指す医師像を実現するための最適な環境だと確信しています。また、早期から臨床現場に触れられるカリキュラムにも強く惹かれています。 入学後は、自身の経験を活かし、患者一人ひとりの背景を深く理解しようと努め、将来はスポーツを愛する人々を支える医師として地域社会に貢献したいです。(389字)
800字の例文
私は、最先端のゲノム医療を駆使して、個別化医療の発展に貢献する研究医になることを強く志望します。 この目標を抱いたきっかけは、祖母が希少がんを患った経験にあります。標準治療では効果が見られず、為すすべなく病状が進行していく姿を目の当たりにし、個々の患者の遺伝子情報に基づいた治療法の確立が急務であると痛感しました。この経験から、ただ病気を治すだけでなく、治療法の選択肢そのものを増やす研究の道に進みたいと考えるようになりました。 数ある大学の中で貴学を志望する理由は、国内有数のゲノM研究センターを有し、基礎研究から臨床応用まで一貫した研究体制が整っている点にあります。特に、〇〇教授が主導する△△プロジェクトは、私が目指す個別化医療の実現に直結するものであり、その最前線で学ぶ機会を得たいと熱望しています。また、貴学の「学生リサーチ・プログラム」は、学部生時代から主体的に研究活動に参加できる貴重な機会であり、私の探究心を最大限に発揮できる環境だと確信しています。 高校時代には、生物部に所属し、遺伝子組み換え技術に関する探究活動に3年間取り組みました。試行錯誤を繰り返す中で、粘り強く課題に取り組む力と、論理的に考察する力を養いました。この経験で培った探究心と忍耐力は、貴学での高度な研究活動においても必ずや活かせると考えています。 入学後は、一日も早く専門知識を吸収し、研究室での活動に積極的に参加したいです。そして将来的には、貴学で得た知見と技術を基盤に、一人でも多くの難病患者に希望の光を届けられるような、新しい治療法を開発する研究医として世界に貢献したいです。(795字)
テーマ・切り口別の例文
地域医療への貢献
私が医師を志望するのは、生まれ育ったこの〇〇県の医療に貢献したいという強い思いがあるからです。祖父が訪問診療を受ける姿を見て、在宅医療の重要性と、それを支える医師の存在の大きさを実感しました。貴学は、県内唯一の医学部として地域医療教育に特に力を入れており、1年次から始まる地域医療実習は、私の目標にとって不可欠な経験だと考えています。貴学で地域が抱える医療課題を深く学び、将来は地域住民から信頼される総合診療医として、この地の医療を支えていきたいです。
研究医志望
私は、iPS細胞を用いた再生医療の研究を通じて、現在は治療困難な神経疾患の治療法を確立したいと考えています。高校の探究授業で再生医療の可能性に触れ、その魅力に深く引き込まれました。貴学の〇〇研究所は、神経再生研究の分野で世界的な成果を挙げており、第一線で活躍される先生方のもとで最先端の知識と技術を学びたいと熱望しています。学部時代から研究活動に積極的に参加し、将来的には基礎研究の成果を臨床へと繋げる架け橋となる研究医を目指します。
自身の原体験(病気・怪我)
私が医師を目指す原点は、中学時代にアトピー性皮膚炎に悩んだ経験にあります。症状の辛さだけでなく、周囲の視線に傷つき、心を閉ざしかけた時期がありました。そんな私を救ってくれたのは、皮膚の治療だけでなく、私の悩みにも真摯に耳を傾けてくれた皮膚科の先生でした。この経験から、患者の心にも寄り添える医師になりたいと強く思うようになりました。貴学の「コミュニケーション教育」に力を入れている点に惹かれました。患者様のQOL(生活の質)向上に貢献できる皮膚科医を目指します。
入試形態別の例文(一般・推薦・地域枠)
- ・一般入試
- →学力に加え、人間性や将来性をアピール。原体験や将来の目標を具体的に記述する。
- ・推薦入試
- →高校時代の活動(部活動、生徒会、ボランティア、探究活動など)と志望理由を結びつけ、リーダーシップや主体性を強調する。
- ・地域枠
- →その地域の医療課題(医師不足、高齢化など)への深い理解を示し、卒業後もその地域に残り、貢献したいという強い意志を明確に表明する。
大学別の例文(国公立・私立)
- ・国公立大学
- →「地域医療への貢献」「最先端の研究」など、公共性や研究志向をアピールすると響きやすい傾向があります。税金で運営されていることを意識し、社会にどう還元したいかを述べましょう。
- ・私立大学
- →「建学の精神」や「独自の教育理念」への共感を強く示すことが重要です。創設者の思想や、大学が掲げる特定の医師像(例:「良き臨床医」など)と自分の目標が一致していることをアピールしましょう。
志望理由書に盛り込むべき3つの必須要素

どのようなテーマや文字数であっても、評価される志望理由書には共通する3つの必須要素があります。自分の文章にこれらが含まれているか、必ず確認してください。
なぜ医師になりたいのか(きっかけ・原体験)
あなただけのオリジナルなストーリーが最も重要です。「人の役に立ちたい」という誰もが書く理由だけでは不十分。具体的なエピソードを交え、「あなたでなければならない理由」を語りましょう。これが志望理由全体の土台となります。
なぜこの大学でなければならないのか
「最先端の医療が学べるから」といった理由は、どの大学にも当てはまります。その大学の「アドミッションポリシー」「カリキュラム」「研究室」「教員」「附属病院の特色」などを徹底的に調べ、自分の目標達成のために「この大学でなければならない」という熱意を具体的に示してください。
入学後にどう貢献できるか(自身の強み)
大学は、ただ教えるだけでなく、共に学び成長してくれる学生を求めています。あなたの強み(例:探究心、協調性、リーダーシップなど)を、大学での学びにどう活かし、学生コミュニティにどう貢献できるかをアピールしましょう。将来、その大学の卒業生として社会で活躍する姿をイメージさせることが大切です。
評価を下げてしまう志望理由書のNG例

熱意があっても、書き方一つで評価を下げてしまうことがあります。以下のNG例に当てはまっていないか、提出前に必ずチェックしましょう。
抽象的で具体性に欠ける表現
- ・NG例: 「人の役に立つ仕事がしたいので、医師になりたいです。」
- ・なぜNGか?: 具体的でなく、誰にでも言える内容です。なぜ「医師」でなければならないのかが伝わりません。
- ・改善ポイント: 医師を志した具体的なきっかけやエピソードを盛り込みましょう。
他の大学でも通用するありきたりな理由
- ・NG例: 「貴学の最先端の設備で、高度な医療を学びたいです。」
- ・なぜNGか?: 多くの医学部が最先端の設備を持っています。その大学ならではの魅力に言及できていません。
- ・改善ポイント: その大学「独自」のカリキュラムや研究、理念に触れ、「ここでしか学べない」理由を明確にしましょう。
医師の仕事への理解不足が感じられる内容
- ・NG例: 「天才的な手術で、多くの命を救うスーパードクターになりたいです。」
- ・なぜNGか?: 医師の仕事は手術だけではありません。チーム医療、地道な研究、患者とのコミュニケーションなど、多岐にわたる仕事への理解が浅いと見なされる可能性があります。
- ・改善ポイント: 医師の仕事の多様性や厳しさを理解した上で、どのような形で貢献したいかを現実的に述べましょう。
アドミッションポリシーとの不一致
- ・NG例: 地域医療への貢献を重視する大学に対し、基礎研究への興味だけをアピールする。
- ・なぜNGか?: 大学が求める学生像と、あなたの目指す方向性が異なると判断され、ミスマッチだと思われてしまいます。
- ・改善ポイント: 必ずアドミッションポリシーを読み込み、大学の方針と自分の目標が合致していることを示すようにしましょう。
医学部志望理由書のよくある質問

最後に、受験生が抱きがちな疑問にお答えします。
特別な経験がない場合、何を書けば良いか?
特別なボランティア経験や受賞歴は必須ではありません。大切なのは、日常の中での気づきや学びを深掘りすることです。
- ・学校の授業で感じた生命科学への興味
- ・読書(医療関連の書籍や論文)から得た問題意識
- ・家族や友人との対話の中で感じたこと
- ・ニュースで見た医療問題に対する自分の考え
など、身近な出来事から「なぜ医師になりたいのか」という問いに繋げていくことができます。経験の大小ではなく、そこから何を考え、学んだかが重要です。
志望理由が思いつかない時の対処法
どうしても筆が進まない時は、一度机から離れて、インプットを増やしてみましょう。
- ・もう一度自己分析をする
- →友人や先生に自分の長所を聞いてみるのも有効です。
- ・大学のオープンキャンパスや説明会に参加する
- →在学生や教員の話を聞くことで、具体的なイメージが湧きます。
- ・OB・OG訪問をする
- →実際に医療現場で働く先輩の話は、大きなヒントになります。
- ・医療関連の書籍やドキュメンタリーに触れる
- →様々な医師の姿を知ることで、自分の目指す方向性が見つかるかもしれません。
焦らず、多角的な視点から情報を集めることが突破口になります。
志望理由書と面接試験の関連性
志望理由書は、面接試験の「台本」や「設計図」になると心得てください。面接官は、あなたが提出した志望理由書を元に質問をします。
- ・「志望理由書に書かれている〇〇という経験について、もう少し詳しく教えてください。」
- ・「なぜ〇〇大学ではなく、本学を志望したのですか?」
- ・「入学後、〇〇という目標を達成するために、具体的にどう学びたいですか?」
書いた内容について、どんな角度から深掘りされても答えられるように準備しておく必要があります。一貫性のある回答ができるよう、志望理由書は必ずコピーを取っておき、面接直前まで読み込みましょう。
志望理由書は面接・小論文と“内容整合”が命。想定質問・頻出テーマはこちら。
まとめ
医学部の志望理由書は、単なる作文ではありません。あなたという人間を大学にプレゼンテーションするための、最も重要なツールの一つです。
この記事で紹介したポイントをまとめます。
- ・徹底した準備: 自己分析、大学研究、要件確認が成功の鍵。
- ・論理的な構成: 「序論・本論・結論」で分かりやすく伝える。
- ・3つの必須要素: 「なぜ医師か」「なぜこの大学か」「どう貢献できるか」を盛り込む。
- ・具体性: 自分だけのエピソードでオリジナリティを出す。
- ・熱意: 将来への展望を語り、入学意欲を力強く示す。
志望理由書を作成する過程は、自分自身と深く向き合い、「なぜ医師になりたいのか」という原点を再確認する貴重な機会です。あなたのこれまでの経験、学び、そして未来への熱意を、自信を持って言葉にしてください。この記事が、あなたの合格への道を切り拓く一助となれば幸いです。応援しています。




-1.jpg)
-3-1-320x180.jpg)

-320x180.jpg)
-4-320x180.jpg)
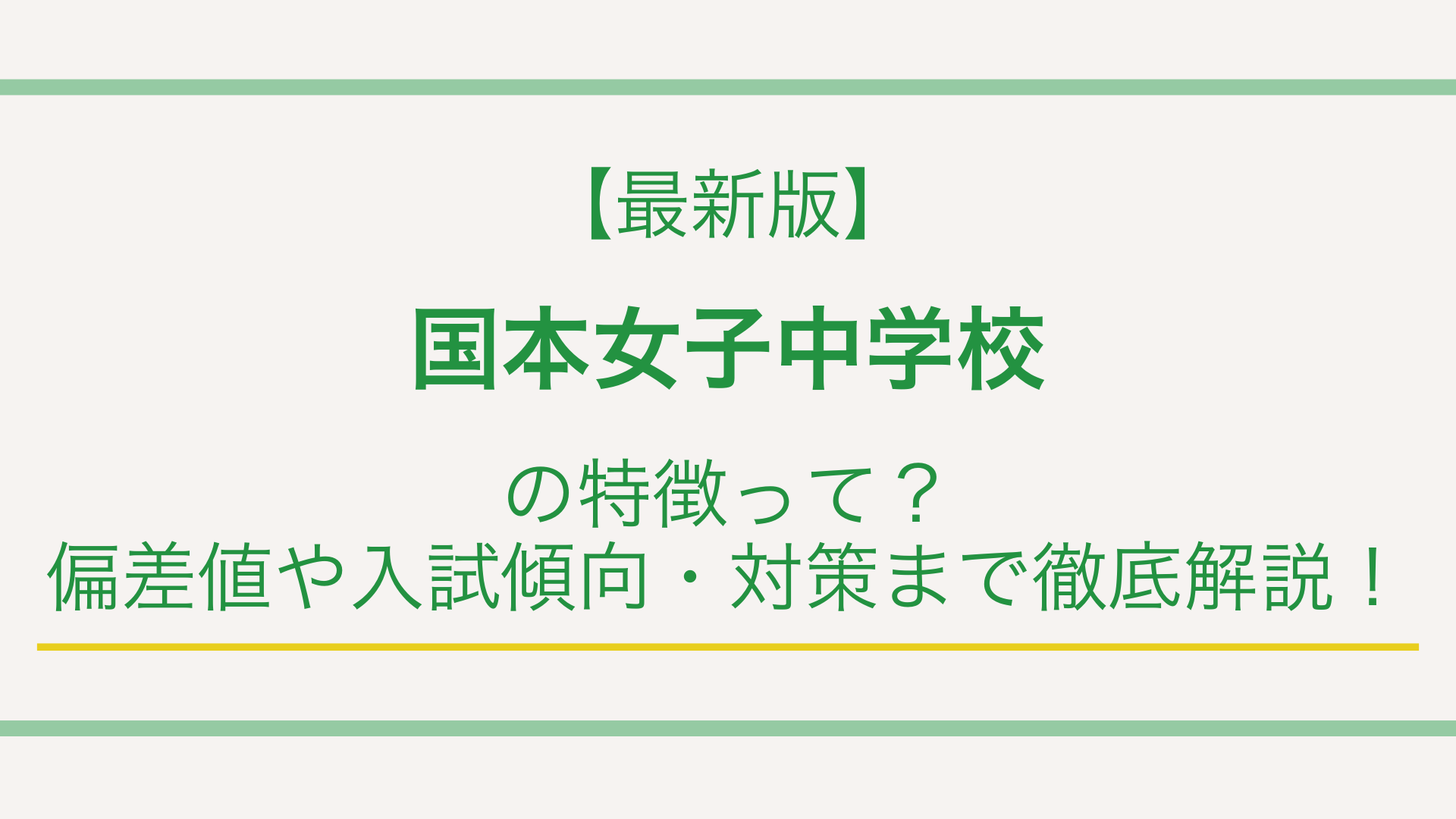
-2-1.jpg)