「将来、人の命を救う医師になりたい」 その強い想いを胸に、最難関である医学部受験へ挑もうとしているあなたへ。
「医学部に入るには、一体何から始めればいいんだろう?」 「合格までに、どれくらいの勉強時間が必要なの?」
そんな疑問や不安を抱えているのは、あなただけではありません。この記事では、医学部合格を目指すすべての受験生と、それを支える保護者の方々のために、医師になるまでの全ロードマップから、具体的な勉強時間、学年別の学習計画、科目別対策まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、漠然としていた「医学部合格」という目標が、実行可能な計画へと変わるはずです。さあ、一緒に合格への第一歩を踏み出しましょう。
医師になるには?医学部合格から先の全ロードマップ

まず理解しておきたいのは、医学部合格はゴールではなく、医師になるためのスタートラインだということです。ここでは、医学部入学から専門医として活躍するまでの、長い道のりの全体像を掴んでおきましょう。
ステップ1:医学部入学から卒業まで(6年間)
医学部では、6年間かけて医師になるための専門知識と技術を学びます。
- ・教養課程(1〜2年次): 物理学、化学、生物学といった自然科学系の基礎科目に加え、語学や人文科学など幅広い教養を身につけます。
- ・基礎医学(2〜4年次):解剖学、生理学、生化学など、人体の構造や機能に関する専門的な学問を学びます。この時期の知識が、後の臨床医学の土台となります。
- ・臨床医学(4〜6年次): 内科、外科、小児科といった各診療科の知識を学び、病院での臨床実習(ポリクリ)が始まります。実際の医療現場で、指導医のもと患者さんと接しながら実践的なスキルを磨きます。
ステップ2:医師国家試験の合格
医学部を卒業(または卒業見込み)すると、医師国家試験の受験資格が得られます。この試験に合格して初めて、医師免許が交付されます。
医師国家試験は、医学部6年間の集大成となる非常に重要な試験です。合格率は例年90%前後と高い水準ですが、これは医学部での厳しい学修を乗り越えた学生が受験するためです。決して簡単な試験ではありません。 (参考:厚生労働省「第118回医師国家試験の合格発表について」)
ステップ3:研修医(初期・後期)としての勤務
医師免許を取得した後は、研修医として病院で働きながら、実践的な臨床能力を身につけていきます。
- ・初期臨床研修(2年間): 内科、外科、救急、小児科、産婦人科、精神科、地域医療など、様々な診療科をローテーションで回り、基本的な診療能力を習得します。
- ・後期臨床研修(3〜5年間): 自身の専門としたい診療科(専攻)を決め、その分野の専門的な知識と技術を深く学びます。
ステップ4:専門医資格の取得とキャリア形成
後期研修を修了し、各学会が実施する試験に合格すると、「専門医」の資格を取得できます。例えば、「内科専門医」「外科専門医」などがこれにあたります。
専門医資格は、その分野における高い専門性を持つ医師であることの証明です。資格取得後は、勤務医として病院でキャリアを積んだり、研究の道に進んだり、開業医として独立したりと、様々なキャリアパスが開かれます。医師という職業は、生涯にわたって学び続けることが求められる仕事なのです。
医学部合格に必要な勉強時間は約5000時間

医学部合格という高い壁を越えるためには、どれくらいの勉強が必要なのでしょうか。
一般的に、現役で医学部に合格するために必要な総勉強時間は、高校3年間で約5000時間と言われています。これはあくまで目安ですが、最難関突破には圧倒的な学習量が不可欠であることを示しています。
学年別の総勉強時間と1日の学習目安
約5000時間という時間を、学年別に分解してみましょう。
| 高校1年生 | 平日:3時間 / 休日:5時間 | 約1,200時間 |
| 高校2年生 | 平日:4時間 / 休日:7時間 | 約1,600時間 |
| 高校3年生 | 平日:5時間 / 休日:10時間 | 約2,200時間 |
| 合計 | – | 約5,000時間 |
もちろん、これは一例です。部活動や学校行事との兼ね合いもありますが、早期から学習習慣を確立し、毎日コツコツと勉強時間を積み重ねることが合格への鍵となります。特に、高1・高2でいかに基礎を固められるかが、高3での伸びを大きく左右します。
医学部合格者の1日の勉強スケジュール例(平日・休日)
では、実際に医学部に合格した受験生は、どのような1日を過ごしていたのでしょうか。ここでは、高校3年生のスケジュール例を紹介します。
平日のスケジュール例
- 06:00~07:00:起床、朝食、計算・英単語の暗記
- 07:00~08:00:通学(リスニング、単語帳)
- 08:30~16:00:学校の授業(内職はせず、授業内容を完璧に理解する)
- 16:00~17:00:移動、休憩
- 17:00~19:00:塾または自習室で勉強(数学の演習など)
- 19:00~20:00:夕食、休憩
- 20:00~23:00:自宅で勉強(理科・英語の復習、問題演習)
- 23:00~23:30:入浴、明日の準備
- 23:30~06:00:就寝
休日のスケジュール例
- 07:00~08:00:起床、朝食
- 08:00~12:00:午前中の勉強(過去問演習など、集中力が必要な科目)
- 12:00~13:00:昼食、休憩
- 13:00~18:00:午後の勉強(苦手科目の克服、分野別の演習)
- 18:00~19:00:夕食、休憩
- 19:00~22:00:夜の勉強(暗記科目の総復習、1日の振り返り)
- 22:00~23:00:自由時間、入浴
- 23:00~07:00:就寝
合格者は、睡眠時間をしっかり確保し、集中力を維持する工夫をしています。自分に合ったリズムを見つけ、継続可能な計画を立てることが重要です。
勉強時間を最大化するためのタイムマネジメント術
限られた時間の中で勉強時間を確保するためには、工夫が必要です。
- ・スキマ時間を活用する: 通学中の電車やバス、休み時間、寝る前の15分など、細切れの時間を有効活用しましょう。単語帳や一問一答形式の問題集は、スキマ時間の学習に最適です。
- ・朝の時間を有効活用する: 夜遅くまで勉強するよりも、少し早起きして朝に勉強する「朝活」がおすすめです。朝は脳がリフレッシュされており、思考力や集中力が高まりやすいため、数学の難問や長文読解などに取り組むのに適しています。
- ・やることリストを作成する: 1日の終わりに、翌日やるべきことをリストアップしておきましょう。朝起きてすぐに勉強に取り掛かることができ、計画的に学習を進められます。
- ・スマホの利用時間を制限する :スマートフォンは最大の時間泥棒になり得ます。勉強中は電源を切る、別の部屋に置く、アプリで利用時間を制限するなど、意志の力だけに頼らない仕組みを作ることが大切です。
【学年別】医学部受験の勉強スケジュールと対策
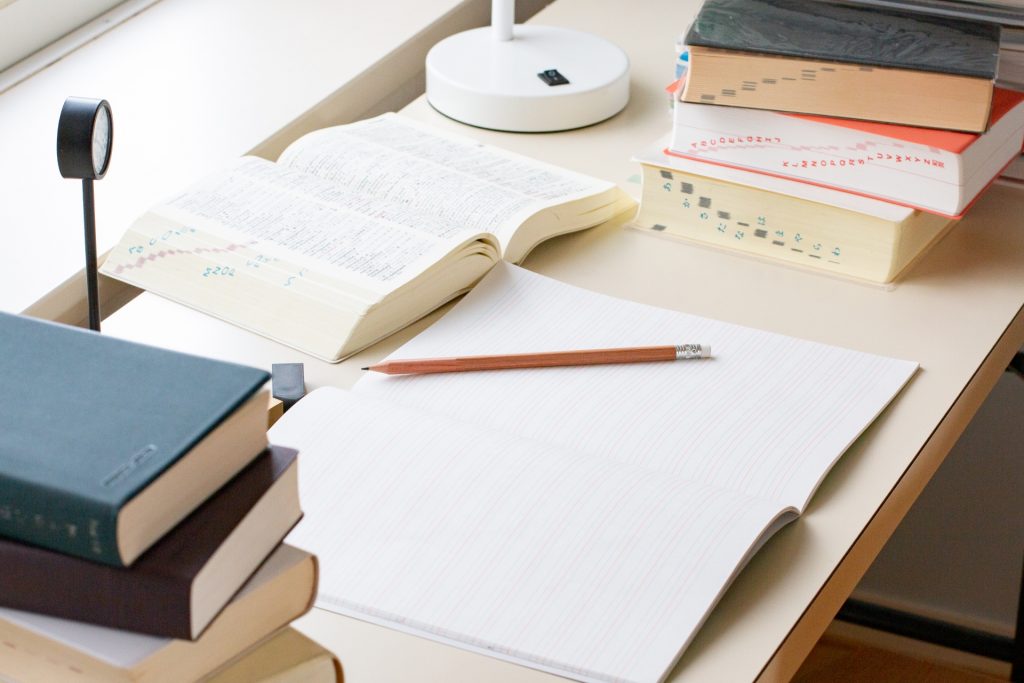
医学部合格という長期戦を制するためには、学年ごとに適切な目標を設定し、計画的に学習を進めることが不可欠です。
中学生でやるべきことと成績の目安
「医学部を目指すなら、中学生のうちから準備が必要?」と考える方もいるでしょう。結論から言うと、中学時代は高校受験の勉強を通して、基礎学力と学習習慣を身につけることが最も重要です。
- ・目標とすべき成績: 具体的な目標としては、学校の定期テストで常に上位5%以内を目指しましょう。特に英語と数学は、高校での学習の土台となるため、苦手を作らないことが大切です。
- ・やるべきこと
- →学校の授業を大切にする :まずは日々の授業内容を完璧に理解し、定期テストで高得点を取ることを目標にしましょう。
- →高いレベルの高校を目指す: 医学部への進学実績が豊富な高校を目指すことで、質の高い授業を受けられ、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境に身を置くことができます。
- →読書習慣をつける :国語力はすべての科目の基礎となります。また、面接や小論文で問われる倫理観や思考力を養う上でも、読書は非常に有効です。
高校1年生の勉強法と基礎固めの進め方
高校1年生は、本格的な受験勉強の土台を作る最も重要な時期です。ここでサボってしまうと、後で取り返すのが非常に困難になります。
- ・目標: 英数国の主要3教科の基礎を完璧に固めることが最優先課題です。特に、数学(ⅠA・ⅡB)と英語は、できる限り先取り学習を進めましょう。
- ・勉強法
- →予習・授業・復習のサイクルを確立する: 学校の授業を最大限に活用し、その日のうちに復習して知識を定着させる習慣をつけましょう。
- →理系科目を疎かにしない: 文系科目も重要ですが、医学部受験の合否は理系科目で決まると言っても過言ではありません。物理・化学・生物の基礎をしっかり理解しておきましょう。
- →模試を定期的に受験する: 自分の学力を客観的に把握し、苦手分野を早期に発見するために、模試をペースメーカーとして活用しましょう。
高1から医学部合格を意識した勉強を始めたい方には、より詳しい勉強法や時間の使い方についてもご覧ください。
高校2年生の勉強法と苦手克服プラン
高校2年生は、中だるみしがちな時期ですが、受験の天王山とも言えます。この1年間でライバルと大きく差をつけることができます。
- ・目標: 全科目の基礎を完成させ、苦手分野を完全に克服することが目標です。高3の夏までに、応用問題に取り組めるレベルに到達しているのが理想です。
- ・勉強法
- →理科の対策を本格化させる 医学部受験では、理科2科目が必要となる場合がほとんどです。高2のうちに全範囲の学習を終え、問題演習に入れるように計画を立てましょう。
- →苦手科目から逃げない 模試の結果を分析し、苦手な単元や分野をリストアップして、集中的に時間を割いて克服しましょう。夏休みなどを利用して、基礎から徹底的に復習するのが効果的です。
- →志望校の情報を集め始める 国公立か私立か、どの大学に興味があるかなど、少しずつ情報収集を始めるとモチベーションアップに繋がります。
高2から医学部受験を始めたい方には、逆転合格を目指すための年間学習計画と勉強法をまとめた記事も参考になります。
高校3年生・受験生の年間学習計画
いよいよ受験本番の1年です。計画的に、かつ戦略的に学習を進める必要があります。
春(4月~6月):基礎の総復習と穴の洗い出し
- ・全教科の基礎事項を総ざらいします。特に、高1・高2で習った範囲に漏れがないか、問題集を使って徹底的に確認しましょう。
- ・苦手分野は、参考書の例題レベルからやり直し、完璧に理解できるまで繰り返します。
夏(7月~8月):応用力養成と苦手克服
- ・夏休みは、1日10時間以上の勉強時間を確保し、応用問題や標準〜発展レベルの問題集に挑戦する時期です。
- ・特に、合否を分ける数学と理科に多くの時間を割き、得点力を一気に高めましょう。
秋(9月~11月):過去問演習と実践力強化
- ・志望校の過去問に本格的に取り組み始めます。時間を計って本番同様の環境で解き、傾向を分析して対策を立てることが重要です。
- ・複数の大学の過去問を解くことで、様々な形式の問題に対応できる力を養います。
冬(12月~2月):共通テスト対策と最終調整
- ・12月からは、大学入学共通テストの対策に重点を置きます。国語や社会も含め、時間配分やマークミス対策など、本番を想定した演習を繰り返します。
- ・共通テスト後は、私立大学の入試や国公立大学の二次試験に向けて、志望校の過去問演習と最終的な知識の確認を行います。
より詳しい勉強時間の目安や年間スケジュールについては、こちらの記事で徹底解説しています。
科目別!医学部受験の効率的な勉強法と参考書
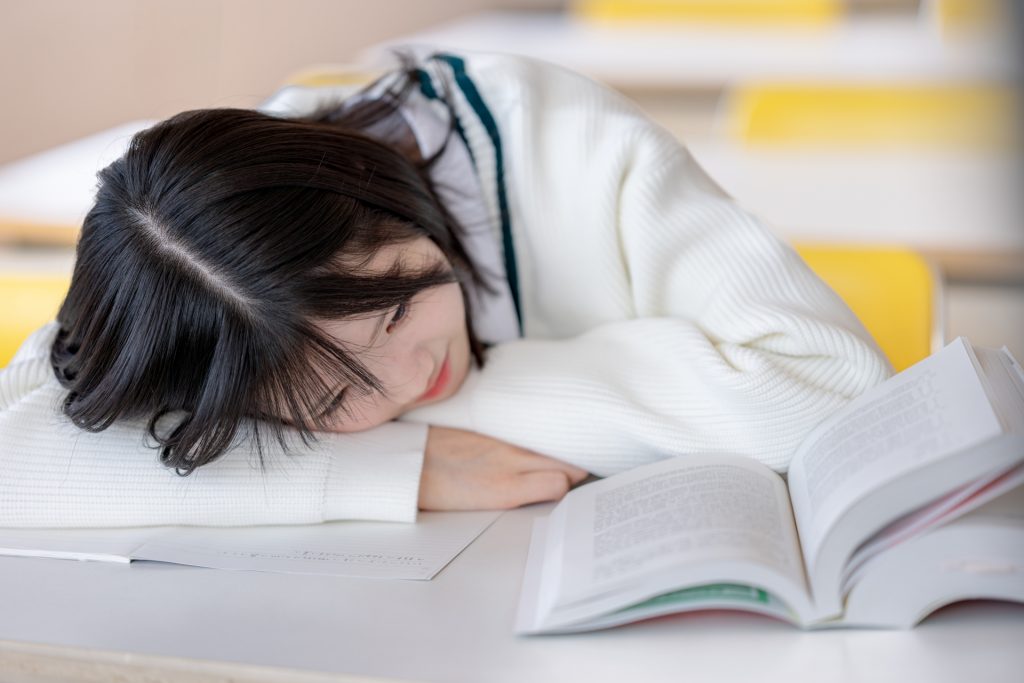
医学部受験では、どの科目も高いレベルが要求されます。ここでは、主要科目ごとの対策ポイントとおすすめの参考書を紹介します。
英語の対策ポイントとおすすめ参考書
医療現場では英語の論文を読む機会も多く、英語力は非常に重視されます。
- ・対策ポイント :単語・文法・構文解釈の基礎を徹底的に固めることが最も重要です。その上で、長文読解の演習を積み、速読力と精読力をバランス良く鍛えましょう。自由英作文や和文英訳が出題される大学も多いため、早期から対策が必要です。
- ・おすすめ参考書
- →単語帳:『鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁』
- →文法書:『Next Stage 英文法・語法問題』
- →構文解釈:『英文読解の透視図』
数学(ⅠA・ⅡB・Ⅲ)の対策ポイントと参考書
数学は、論理的思考力を測る上で重要な科目であり、多くの医学部で配点が高く設定されています。
- ・対策ポイント: 解法の暗記ではなく、公式や定理の本質的な理解を心がけることが大切です。典型問題の解法パターンをマスターした上で、応用問題にじっくり取り組む時間を確保しましょう。計算ミスをなくすための日々のトレーニングも欠かせません。
- ・おすすめ参考書
- →網羅系:『Focus Gold(フォーカスゴールド)』シリーズ
- →演習系:『大学への数学 1対1対応の演習』シリーズ
- →応用系:『やさしい理系数学』
理科(物理・化学・生物)の選択と対策
多くの大学で、物理・化学・生物の中から2科目を選択します。
理科の選択方法
- ・物理: 計算力と論理的思考力が求められます。一度理解すれば高得点で安定しやすいですが、苦手な人には厳しい科目です。
- ・化学: 暗記分野と計算分野がバランス良く出題されます。比較的、努力が点数に結びつきやすい科目と言えます。
- ・生物: 暗記量が多く、考察問題や記述問題も出題されます。知識の正確性と深い理解が求められます。
基本的には、自分が最も得意で高得点を狙える科目を選ぶのがセオリーです。ただし、大学によっては選択科目を指定している場合があるため、志望校の募集要項を必ず確認しましょう。
対策ポイント
どの科目を選択するにせよ、まずは教科書レベルの知識を完璧にすることが大前提です。その上で、標準的な問題集を繰り返し解き、知識の定着と応用力を養いましょう。
- ・おすすめ参考書
- →化学:『化学の新研究』、『化学重要問題集』
- →物理:『物理のエッセンス』、『良問の風 物理』
- →生物:『大森徹の最強講義117講 生物』、『生物重要問題集』
国語・社会の共通テスト対策
国公立医学部を目指す場合、共通テストで国語と社会も必要になります。二次試験に比べて配点は低いことが多いですが、決して疎かにはできません。
- 対策ポイント 高3の夏までは英数理に集中し、秋以降に本格的な対策を始めるのが効率的です。過去問や予想問題集を繰り返し解き、時間配分と出題形式に慣れることが重要です。特に社会は、短期間で点数を伸ばしやすい科目なので、戦略的に学習しましょう。
国公立と私立医学部の違いと受験戦略

医学部には国公立大学と私立大学があり、それぞれに大きな違いがあります。
学費と奨学金制度の比較
最も大きな違いは学費です。
- ・国公立大学: 6年間の総額は約350万円と、比較的安価です。
- ・私立大学 :大学によって大きく異なりますが、6年間の総額は2,000万円~5,000万円程度が一般的です。
ただし、私立大学でも成績優秀者向けの特待生制度や、地域医療への貢献を条件に学費が減免される「地域枠」、各種奨学金制度が充実しています。学費だけで諦めず、利用できる制度がないか積極的に調べましょう。
奨学金制度の種類や条件について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
入試科目と難易度の違い
- ・国公立大学: 大学入学共通テストで5教科7科目(または6教科8科目)が課され、さらに大学独自の二次試験(主に英数理)があります。幅広い学力が求められるため、苦手科目を作らないことが重要です。
- ・私立大学: 多くは3教科(英語、数学、理科2科目)での受験となります。科目数が少ない分、各科目で非常に高いレベルの学力が求められます。また、大学ごとに問題の傾向が大きく異なるため、志望校に特化した対策が不可欠です。
より詳しい内容は以下の記事をご覧ください。
志望校の選び方と過去問対策の始め方
志望校を選ぶ際は、偏差値だけでなく、様々な要素を総合的に考慮しましょう。
- ・志望校選びのポイント
- →偏差値、難易度
- →国公立か私立か(学費)
- →立地(一人暮らしをするか)
- →大学のカリキュラムや研究内容
- →入試科目と問題の傾向(自分との相性)
- →附属病院の規模や特徴
過去問対策は、高3の秋から本格的に始めるのが一般的です。まずは志望度の高い大学の過去問を数年分解いてみて、出題傾向や難易度、時間配分を体感しましょう。その上で、自分の弱点を分析し、今後の学習計画に反映させていくことが合格への近道です。
医学部受験でよくある質問(Q&A)

最後に、医学部受験生が抱きがちな疑問にお答えします。
塾や予備校はいつから通うべき?選び方のポイント
「医学部受験に特化した塾や予備校に通うべき?」という質問は非常に多いです。
- ・通い始める時期: 高校2年生の夏休みや秋頃から通い始める人が多いですが、決まった時期はありません。学校の授業だけでは不安を感じた時や、より高いレベルの環境で学びたいと思った時が最適なタイミングです。
- ・選び方のポイント
- →医学部専門、または医学部コースがあるか 豊富な情報量と合格ノウハウを持っています。
- →指導形式(集団授業か個別指導か) 自分の学習スタイルに合った方を選びましょう。
- →合格実績 自分の志望校レベルの合格者がどれくらいいるかを確認しましょう。
- →学習環境(自習室の有無など) 集中して勉強できる環境が整っているかは重要です。
公立中学・高校からでも合格できる?
「進学校じゃないと医学部は無理?」と不安に思う必要はありません。
結論から言うと、公立中学・高校からでも医学部合格は十分に可能です。実際に、多くの合格者が公立校の出身です。 ただし、そのためには以下の点が重要になります。
- ・早期からの情報収集と計画: 進学校に比べて受験情報が少ない場合があるため、自分で予備校のサイトや説明会などを活用し、積極的に情報を集める必要があります。
- ・高いレベルでの自己管理能力: 周りに流されず、高い目標を維持し、自分で学習計画を立てて実行する強い意志が求められます。
面接・小論文対策はいつから、どう進める?
医学部入試では、学力試験に加えて面接や小論文が課されることがほとんどです。
- ・対策を始める時期: 高校3年生の夏以降、共通テスト対策と並行して進めるのが一般的です。
- ・対策方法
- →情報収集: まずは医療ニュースや生命倫理に関する本を読み、知識を蓄えましょう。志望大学の「アドミッション・ポリシー(求める学生像)」を読み込むことも必須です。
- →自己分析 :「なぜ医師になりたいのか」「なぜこの大学なのか」といった根本的な問いについて、自分の言葉で語れるように深く考えをまとめましょう。
- →実践練習: 学校の先生や予備校の講師に協力してもらい、模擬面接や小論文の添削を繰り返し行いましょう。
小論文対策の頻出テーマ・効率的な勉強法についてはこちらの記事をご覧ください。
現役合格と浪人のメリット・デメリット
医学部受験では、浪人して合格する人も少なくありません。
- ・現役合格のメリット: 1年早く医師としてのキャリアをスタートでき、学費や生活費の負担も少なくて済みます。
- ・浪人のメリット :1年間、受験勉強だけに集中できるため、学力を大幅に伸ばすことが可能です。現役時代には手が届かなかった、よりレベルの高い大学を目指せるチャンスがあります。
どちらが良いというわけではありません。まずは現役合格を目指して全力を尽くし、その結果を踏まえて次の選択を考えるのが良いでしょう。浪人を選択する場合も、明確な目標と強い意志を持って臨むことが成功の鍵です。
まとめ
今回は、「医学部に入るには」という大きなテーマについて、医師になるまでの道のりから具体的な勉強法まで、詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- ・医師への道は、医学部合格後も続く長い道のり: 6年間の学修、国家試験、研修医期間を経て、専門医として一人前になります。
- ・合格に必要な勉強時間は約5000時間: 高1から計画的に学習習慣をつけ、毎日コツコツと勉強を積み重ねることが不可欠です。
- ・学年ごとに明確な目標設定が重要: 高1・高2で基礎を固め、高3で応用力と実践力を完成させるのが王道のスケジュールです。
- ・英数理の対策が合否を分ける: 特に苦手科目を作らず、全科目で高いレベルを目指す必要があります。
- ・自分に合った戦略を立てることが合格の鍵: 国公立・私立の違いを理解し、偏差値だけでなく多角的な視点で志望校を選びましょう。
医学部への道は、決して平坦ではありません。しかし、正しい知識と戦略、そして何よりも「医師になりたい」という強い情熱があれば、必ず乗り越えることができます。
この記事が、あなたの夢を叶えるための一助となれば幸いです。あなたの挑戦を心から応援しています。




-2.jpg)
-320x180.jpg)
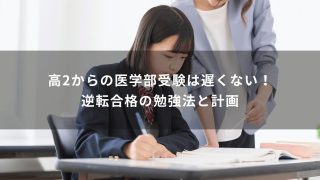
-320x180.jpg)

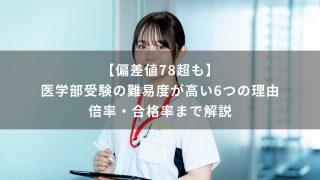
-4-320x180.jpg)
-2-1.jpg)
-3-1.jpg)